| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
2月3日に集まった面々。それぞれがあっちこっちを見ているのが面白い。集いつつも、一つの考えに簡単には
大正7年2月3日(1918日。
そのそうそうたる顔ぶれに驚かされます。洋画家もいれば日本画家もいて、詩人も歌人も美術評論家も音楽評論家もロシア文学者も浮世絵研究家もいます。当時、異分野の芸術家たちが盛んに交流したようです。
日夏耿之介(27歳)と柳沢
こういった異分野交流の結実なのでしょう、この頃、異分野のコラボレーションを強く意識した優れた作品が複数生まれています。
白秋は10年も前から「パンの会」(明治41-43年)という異分野の交流会を開いていました。
当地(東京都大田区山王)が「パルナス的中心」だった頃(大正7年頃)、東京田端(Map→)にも、作家たちのコミュニティーが生まれています。神奈川県横須賀の海軍機関学校で教師をしていた芥川龍之介が学校を辞し、執筆に専念すべく養父母のいる田端に戻ってきたのです(大正8年芥川27歳)。芥川は日曜日を面会日とし、その日には芥川を慕う小島政二郎、佐佐木茂索、滝井孝作、南部修太郎らが集い、また、室生犀星、萩原朔太郎など周辺に移り住む人も増え、“文士村”の観を呈します(「田端文士村」)。
 |
 |
| 「パンの会」の様子。右で三味線を弾くのがこの絵を描いた木村壮八、その左で頬づえつくのが谷崎潤一郎、その左で立ってスピーチするのが小山内 薫 ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:『明治文学アルバム(新潮日本文学アルバム 別冊)』 | 田端の芥川の住まいにて。小穴隆一(左)と佐佐木茂索(右。後の文藝春秋社長(2代目))の将棋を観戦する芥川と岡 栄一郎(劇作家・評論家) ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『芥川龍之介(新潮日本文学アルバム)』 |
尾﨑士郎と宇野千代とが越してきて当地(東京都大田区馬込)に一大コミュニティが誕生するのが、5年後の大正12年(「馬込文士村」)。「菊富士ホテル」から尾﨑士郎、宇野千代、広津和郎らが来て、田端から萩原朔太郎、室生犀星らが当地に来ました。馬込でのコミュニティーでは、互いに切磋琢磨と言うより、酒を飲んで騒いだり、麻雀をしたり、ダンスをしたり、相撲をしたりと、遊びまくっています。皆まだ若く駆け出しで、息抜きの期間だったのかもしれません。
どういう会であったか忘れたが、久しぶりに広津和郎氏に遇った。・・・(中略)・・・せかせか歩いてきて、私に気がつくと、私のとなりの椅子にかけ、馬込はおもしろかったね、と言った。・・・(中略)・・・いきなり馬込を持ち出されて、私はいささか面くらい気味だったが、しかし馬込が意識の上にひろがってくるのに、二秒とはかからなかった。すでに遠い記憶だが、思い出せば昨日のことのように生ま生ましい。それほど深くきざみこまれているのは、たしかに、馬込がおもしろかったからにちがいない。・・・(榊山潤『馬込文士村』の冒頭)
 |
馬込つながりの3人。右から尾﨑士郎、佐藤観次郎、榊山 潤。佐藤は尾﨑の家のすぐ近くに住んでいた編集者 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『馬込文士村 〜あの頃、馬込は笑いに充ちていた〜』(東京都大田区立郷土博物館) |
馬込の面々は、あるときは軽井沢に集い、また、ある時は伊豆湯ヶ島にこぞって出かけ(湯ヶ島には川端康成の
 |
女性だけのコミュニティーも生まれた。左より、林 芙美子、佐多稲子、吉屋信子、宇野千代。昭和11年東京新宿の吉屋邸にて。※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『馬込文士村 〜あの頃、馬込は笑いに充ちていた』(東京都大田区立郷土博物館)原典:日本近代文学館所蔵写真 |
「馬込文士村」は大正12年に尾﨑と宇野が越してきたのがきかけですが、同年(大正12年)関東大震災が起き、壊滅した東京中心部から周辺部へと人々がこぞって移動した流れで、作家たちが増えていった面があります。「阿佐ヶ谷文士村」も同様で、関東大震災の前年(大正11年)に開設された「阿佐ヶ谷駅」周辺に、震災後、作家たちも集まってきたようです。
池袋周辺に形成された芸術家の文化圏「池袋モンパルナス」も大正の終わり頃にできたというので、やはり、震災の影響があったでしょうか。モンパルナスはモンマルトルと並んで、1900年代前半、画家の溜まり場になったパリの町。池袋にもアトリエ村(貸し住居付きアトリエ群)ができ、芸術家が集まりました。長谷川利行、松本竣介、北川民次、福沢一郎、丸木
作家(全ての表現者を含む)は、自らの感性・発想・思念を信じそれを表現する人たちなので(周りに忖度して(周りの反応を恐れ)それらを押し殺したらもはや作家でなし)、集えば、当然、ぶつかり合いもあります。上述の“馬込文士村”もそうだったし、「中央亭騒動」も良い例、辻 潤の渡欧送別会のおりの一悶着もそうでした。
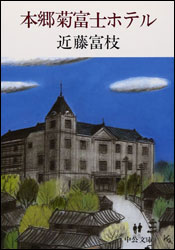 |
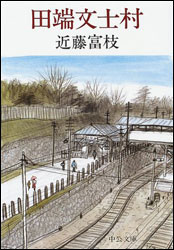 |
| 近藤富枝『本郷菊富士ホテル (中公文庫)』 | 近藤富枝『田端文士村 (中公文庫)』 |
 |
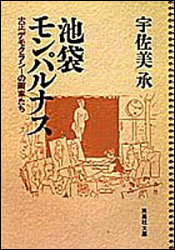 |
| 村上 護『阿佐ケ谷文士村』(春陽堂書店) | 宇佐美 承『池袋モンパルナス 〜大正デモクラシーの画家たち〜(集英社文庫)』 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 北原白秋の『桐の花』を読む→
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
・ 小島政二郎の『眼中の人』を読む→
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 萩原朔太郎の『月に吠える』を読む→
・ 榊山 潤の『馬込文士村』を読む→
・ 広津和郎の『昭和初年のインテリ作家』を読む→
・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→
・ 宇野千代の『色ざんげ』を読む→
・ 高見 順の『死の淵より』を読む→
・ 川端康成の『雪国』を読む→
・ 子母沢 寛の『勝 海舟』を読む→
・ 真船 豊の『鼬』を読む→
・ 吉屋信子の『花物語』を読む→
・ 辻 潤の『絶望の書』を読む→
■ 参考文献:
● 『長谷川 潔の世界 上 (渡仏前) (横浜美術館
※当ページの最終修正年月日
2025.2.3