








(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |

子どもの頃、室生犀星は悲惨だった。 生後一週間で寺に捨てられ、拾われた先の養母からは日々激しい折檻を受けた。 小学校の教師からも叱られどおしで、自尊心はズタズタで、子どもながらに川に飛び込んで死んでやろうとさえ思ったという。
犀星は、皆から嫌われるもの、例えば毛虫などに親しみの眼を向ける人だった。 否定され続けた自分を重ねて見ていたのかもしれない。
この 『黒髪の書』 でも、犀星は疎外されたものに目を向ける。
牢獄から出てきて世間の冷たい視線にさらされる男、身持ちのよくない乞食の妻に激しく嫉妬する乞食の夫、病的なまでに繊細な神経を持つ人、重い病に冒されつつある男、片目の犬・・・。 何かしら幸福から縁遠いものたち。
そして犀星は、彼らを見つめ、“救い” を探る。
この小説の中で、彼らは救われるだろうか? もし彼らに救いがあれば、それは犀星の救いでもあったろうし、読む我々の救いでもあるのだろう。
 |
『黒髪の書』 の第三話 「餓人伝」 の舞台の池上本門寺。夜になって風雪は強まり、お堂の縁の下に住まう人たちを容赦なく襲う (平成13年1月撮影) |
『黒髪の書』 について
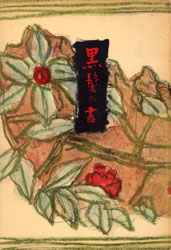 |
| 室生犀星 『黒髪の書』 |
室生犀星66歳の時の作品集。昭和30年、新潮社から出版された。 この本の出版の前に犀星には7年間のブランクがあり、これが出版されたとき、“奇跡の復活”と言われた。
タイトルには、皆かつては黒髪の人であったという意味が込もる。 人生における、老いや零落を見つめている。
室生犀星について
 |
| 室生犀星 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用しました 出典:『馬込文士村ガイドブック(改定版)』 |
逆境
明治22(1889)年8月1日、石川県金沢市で生まれる。 父は加賀藩士小畠吉種、母は吉種に仕えた女性。 犀星出生時、吉種は63歳で、世間体をはばかって生後1週間の犀星を真言宗雨宝院(map→)に捨てた。寺の住職の内妻ハツが育てる。 他にテヱ、真道、きんという三人の貰い子があり、兄弟姉妹として過ごす。花柳界に身売りした優しい義姉テヱを思って、後年 『蒼白き巣窟』 を書く(1万字近くの伏せ字あり)。
明治35年(12歳)、 高等小学校を3年で中退、義兄真道が勤める金沢地方裁判所の給仕になる。 上司の川越弥一などを真似て俳句を作り始める。 川越らが句を添削してくれた。明治37年(15歳)「北国新聞」に俳句が初掲載され、 明治40年(17歳)には「新声」で詩が首位になり、詩で身を立てる決意をする。この頃から犀星と名乗る。
翌年、養母ハツを避けて金石出張所(金石海岸)に転勤、一人暮らしを始めるが、文学への思いが高じて裁判所を退職、石川県三国町の 「みくに新聞」 に入社、新聞小説などを書くが、1ヶ月もしないで社長と衝突して退職。 翌年、赤倉を頼って上京(明治43年。21歳)、裁判所のアルバイトや詩の代作で食いつなぐ。
「朱欒」に掲載された詩でブレイク
東京での生活は2年で立ち行かなくなり、明治45年(23歳)、帰郷、定職を持たない犀星への周囲の目は冷たかった。 哀愁ある詩風となる。 「スバル」「朱欒」などに作品を発表、萩原朔太郎(26歳)を激しく感動させた。大正3年(25歳)、朔太郎、山村暮鳥と人魚詩社を設立、翌年、同人誌 「卓上噴水」 を創刊(3号で廃刊)。
大正5年(27歳)、再び上京。 朔太郎と感情詩社を設立、同人誌 「感情」 を創刊(大正8年32号まで)。 大正6年(28歳)、養父真乗(雨宝院住職。養
ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて異土の乞食となるとても
帰るところにあるまじや・・・
(『抒情小曲集』所収「小景異情」 より。初出:「朱欒」(最終号))
帰郷の際、文通相手の浅川とみ子と会い、結婚を約し、この年(大正7年2月)結婚、第二詩集はとみ子が着物を売って助けた。この頃からドストエフスキーやトルストイを耽読。人の不幸を見つめる。
家族のために書きまくる
詩だけでは食っていけず、新たな道をさぐるべく芥川龍之介に接近。ドストエフスキーの 『カラマゾフの兄弟』 に触発されて小説を書き始める。 大正8年(30歳)、瀧田樗陰に見いだされて、自伝小説 『幼年時代』『性に眼覚める頃』『或る少女の死まで』(初期三部作)を書いて成功。 翌年、33編もの小説を濫作。
若い作家をさかんに支援、同人誌「驢馬」や「四季」を支えた。 大正末から昭和初期にかけてモダニズムが隆盛、遅れを取る。 円本の恩恵で家計は安定していた。
面目躍如の「市井鬼物」
昭和9年(45歳)、「詩よ君とお別れする」の一文を発表、抒情的な作風と決別、善悪を越えた民衆の放埒なエネルギーを書く。それらは 「市井鬼物」と呼ばれ高く評価された。 全集の刊行も始まり、芥川賞の選考委員となる。
前衛を貫く
戦中は、王朝物や甚吉物(作者の分身“甚吉”を主人公にした一連の作品)で、生きることの切なさと生命への愛惜を描く。戦争を讃えるものも残した。
戦後、沈黙がちだったが、昭和30年(66歳)、 『黒髪の書』 『随筆 女ひと』 で復活。娘の朝子をモデルにした小説 『杏っ子』 がベストセラーとなる。 最晩年の 『われはうたへどやぶれかぶれ』 まで、独自な文体で前衛を貫いた。 生涯に出版した本は150冊、小説は700編、詩は1300編に及ぶ。
昭和37(1962)年(72歳)、肺ガンで死去。 墓所は石川県金沢市の野田山墓地(石川県金沢市野田町野田山1番地2 map→)( ) 。
■ 室生犀星評
・ 「室生といふ男は、見る物聞く物、何につけても、子供のやうな驚き方をする男である」 (萩原朔太郎)(「讀賣新聞」昭和12年3月10日「室生犀星を檢討する」より)
・ 「世間に気も使わなければ、気を使われようとも思っていない」(芥川龍之介)(「でき上がった人 ~室生犀星氏~」より)
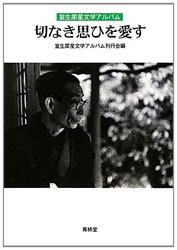 |
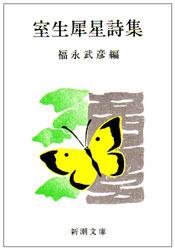 |
| 室生犀星文学アルバム 『切なき思ひを愛す』 | 『室生犀星詩集 (新潮文庫)』 |
室生犀星と馬込文学圏
昭和3年11月10日(39歳)、萩原朔太郎(42歳)の妻稲子が探した借家(現・山王四丁目13)に、東京田端から越してきた。 近くの弁天池の湿気が子どもの健康に障るのを心配し、4年後の昭和7年(43歳)、万福寺の隣に家を建てて終生住む(現・南馬込一丁目 49-5「室生マンション」 map→)。庭の地面を 「女性の肌」 にたとえ、庭作りに丹誠を込めた。 踏み石を雑巾で拭くほど。 妻を亡くした時は墓を庭に作った。 当地にいたのはおよそ33年間。万福寺に庭石の一部が移され、彼の句碑が立つ。家の離れは馬込第三小学校(北馬込一丁目)に移築され保存されている。
避暑や疎開で軽井沢へ行く際、当地の家の留守番を伊藤信吉や立原道造が務めている。
萩原朔太郎とはしばしば大げんかしながらも終生親しくし、片山広子、佐藤惣之助、竹村俊郎、平木二六、芥川龍之介、津村信夫、衣巻省三らとも親交。宇野千代・尾﨑士郎の夫婦とは肌が合わず、衣巻の家でうだうだしていた稲垣足穂をたしなめた。
馬込にある4つの小学校のうち3校(馬込小学校・馬込第三小学校など)の校歌の詞は犀星による。
参考文献
●『評伝 室生犀星』(船登芳雄 三弥井書店 平成9年発行)P.99-134、P. 183-195 ●『馬込文士村ガイドブック(改訂版)』(東京都大田区立郷土博物館編・発行 平成8年発行) P.52-53、P.70-74 ● 『大森 犀星 昭和』 (室生朝子 リブロポート 昭和63年発行) P.159-161 ●『馬込文学地図(文壇資料)』(近藤富枝 講談社 昭和51年発行) P.120-125、P.160-178 ●『馬込文士村の作家たち』 (野村裕 自費出版 昭和59発行) P.66-80 ● 『文学者たちの軽井沢(上)』(吉村裕美 軽井沢新聞社 平成21年初版参照) P.24-25 ●『馬込村文芸の会 十年の歩み』 (発行:大沢富三郎 平成6年) P.52-53、P.111 ●『眼中の人』(小島政二郎 文京書房 昭和50年発行) まえがき ●『我が愛する詩人の伝記(新潮文庫)』(室生犀星 昭和41年初版発行 昭和54年18刷参照) P.13-14 ●『室生犀星文学アルバム ~切なき思ひを愛す~』(
※当ページの最終修正年月日
2025.4.25