








(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
死が目前に迫る時、人はどんなことを思うだろう。高見 順は食道ガンを患い、2~3行書いては2~3日休み、そしてまた2~3行と、これらの詩を綴っていった。
「自分の死」は、頭で考えた死や、自分以外の死とは、また別物のようだった。叫び声をあげて逃げ出したくなるような、でも逃れることができない強烈な痛みと、悲しみと、恐怖。きれい事ではありえない。
泣け 泣きわめけ
大声でわめくがいい
うずくまって小さくなって泣いていないで
そして私の心よ
「夜の底」から死者の爪がのびてきたり、体から出るピューピューという音がやけに悲しかったり、「死よりもいやな空虚」が感じられたり、自分で命を絶つ方法を考えたり、でも死ぬことすらできないと考えたり、すでに死臭が漂ってきたり、「肉体とは無関係の心」を恨んだり・・・。 これらの言葉は、絶望の底からのうめきだろう。
この逃げ場のなさ。でも、生きていかなければならない。 高見は必死に何かを探す・・・。
当たり前のことだが、私たちだっていつかはみんな死ぬ。 皆、生まれ落ちた時から死に向かって歩き出すといってもいいだろう。赤ちゃんだって、子どもだって、ピチピチのアイドルだって、スポーツ選手だって、例外ではない。人ごとではない。
悪戦苦闘の末に高見が見い出したものは、きっと私たちの心の支えにもなるだろう。私たちも、彼と同じ「死の淵」に立っている。
『死の淵より』について
 |
昭和38年、講談社から発行された高見 順(56歳)の詩集。
■『死の淵より』 評
●「これらの詩には本当の「遊び」の境地があり、小説の永久に達しえぬ境地でありませう」(三島由紀夫)
高見 順について
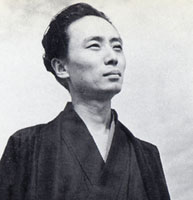 |
| 高見 順(昭和15年 33歳) ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典 :『昭和文学アルバム(1)(新潮日本文学アルバム別巻)』 |
私生児として育つ
明治40年1月30日(本当は前年(明治39年)の12月生まれ。それを高見も晩年まで知らなかった)、福井県三国町で生まれる。父は当時福井県知事だった坂本
さまざまな新しい思潮・運動から吸収
東京府立第一中学校(現・日比谷高校)時代から白樺派の作家に親しむ。校長の川田正澂(かわだ・まさずみ)の仲介で岡田顕三から個人的な育英資金を受け(岡田顕三は(株)フジクラの創業者・藤倉善八の甥で、電線事業の技術面で活躍。 後年、高見は『岡田顕三伝』の編纂に携わった)、第一高等学校(現・東京大学)をへて東京帝国大学文学部英文科に入学。築地小劇場に出入りし、擡頭してきたダダイズム、アナキズム、新たに興った文学運動(プロレタリア文学や新感覚派など)のエッセンスを吸収する。帝大卒業後、自ら立ち上げた劇団「制作座」のメンバー石田愛子と結婚、麻布の母の元を去って、当地(東京都大田区大森。大森銀座(京浜急行「大森支線(海森線)」沿いの道)近く)の家に住んだ(昭和5年23歳)。
本格的に作家生活に入る
コロンビア・レコードに就職するとともに、かねてから所属していたナルプ(日本プロレタリア作家同盟)の城南地区の責任者となる(転居の目的もそこにあった)。半非合法(非合法だった共産党とつながりがあった)の全協(全国労働組合協議会)の活動に関わり、 昭和8年2月(26歳)、治安維持法違反容疑で検挙され、大森警察に拘留され、拷問を受ける。
転向手記を書かされて起訴留保となって、3ヶ月後に出獄するが、酒場勤めを始めた妻・愛子が裕福な40男と出奔。思想的挫折と家庭崩壊のダブルパンチを食らう。痛手を紛らわすがごとくに銀座裏をさまよい、昭和10年(28歳)、銀座裏で働く水谷秋子と出会う。新しい恋愛に意欲を取り戻して書いたのが 『
昭和13年(31歳)、浅草に仕事部屋を構え大森から通った。 浅草体験を元に書かれた『
昭和14年(32歳)、長女が生まれるが、翌年、消化器系統の不良で死去。
昭和16年(34歳)、『如何なる星の下に』の挿絵を描いた
帰国後に書いた「文学非力説」(国への奉公を旗印にした威勢のいい文学論を批判。暗に文学が国策の具になることを牽制したか)は、尾﨑士郎によって「(文学が)国民感情から遊離してゆく」(あんたの言説は“非国民的”である)と批判された。満州事変後日本は戦時下であり、国は国民が一丸になることを強制していたので、高見もそれ以上は言えず謝罪めいたことを言って穏便に済ませた。高見の尾﨑に対する鬱屈は戦後も尾をひく(「文学非力説」 論争)。
体調不良と戦いながら
戦中は、陸軍報道班員としてビルマとタイに行く。 昭和18年、13年ほど住んだ大森(東京都大田区)を去って、北鎌倉に疎開。戦中、収入を補うために川端康成らと貸本屋 「鎌倉文庫」を開店、店番もした。鎌倉文庫は出版社にまで発展し、高見はその常務取締役を務めるが、執筆もこなし忙殺され、昭和22年(40歳)頃から体調が優れなくなる。
昭和33年(51歳)、『わが胸の底のここには』(Amazon→)を発行。昭和37年(55歳)には、芥川賞選考委員となる。伊藤 整や小田切 進らと日本近代文学館の設立準備も始めた。翌38年(56歳)、『いやな感じ』を出版。大杉 栄虐殺の復讐を画策するアナキストの青年が、しだいに右翼に転ぶ様を通し、激動の時代を描いた。この年、食道にガンが見つかり、以後4回手術を受ける。
昭和40年(58歳)、日本近代文学館の起工式にメッセージを寄せ、その翌日の8月17日に死去。川端康成が葬儀委員長を務めた。北鎌倉の東慶寺と福井県三国の円蔵寺に埋葬される( )。 日本近代文学館2階フロアーには、功績を顕彰して高見の胸像が置かれている。
■ 高見 順 評
●「日本における最初の現代文学」(川端康成)
●「高見 順の時代といふ時代があつた 」 (中島健蔵)
 |
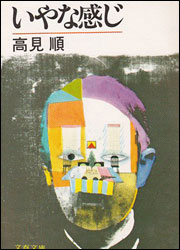 |
| 高見 順 『いやな感じ (文春文庫) 』 |
参考文献
●『高見 順 ~人と作品~』 (石光 葆 清水書院 昭和44年初版発行 昭和46年発行2刷) P.35-36、P.56-58、P.79-80、P.196-197 ●「高見 順」(平野 謙)※『新潮 日本文学小辞典』(昭和43年初版発行 昭和51年発行6刷)に収録 ●『決定版 三島由紀夫全集38』(新潮社 平成16年発行)P.667-669 ●『大田文学地図』(染谷孝哉 蒼海出版 昭和46年発行)P.63、P.101、P.157-166 ●『馬込文士村ガイドブック(改訂版)』 (編・発行:東京都大田区立郷土博物館 平成8年発行)P.46-47 ●『評伝 尾﨑士郎』(都築久義 ブラザー出版 昭和46年発行)P.171-172、P.217-221、P.286-288 ●『プロレタリア文学運動』(湯地朝雄 晩声社 平成3年発行)P.25-26 ● 『高見 順(新潮現代文学)(昭和56年発行)P.354-366 ●『高見順 日記 第六巻』(勁草社 昭和40年発行) P.295-297 ●『続 高見 順日記 第八巻』(勁草書房 昭和52年発行) P.68、 P.310-311 ● 『高見 順日記 第二巻ノ上』(勁草書房 昭和41年初版発行 昭和53年発行3刷)P.462-465 ● 『詩人 高見 順 ~その生と死~』(
※当ページの最終修正年月日
2025.4.22