








(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
愛人に泣きつかれた大助は、
しかし、いろいろ変だ。 なぜに大助は、仲間内ではあんなにも饒舌なのに、専門家の前では何も語れなくなってしまうのか? それに、明らかに話のつじつまが合わないのはどうしたことか?
それでも、仲間たちは、ついつい熱気を帯びた大助の話に引き込まれてしまう。大助への疑惑が高まっても、一人は叫ぶ。
「僕にとつては彼が実際に何をしてゐたかといふことを詮索する必要なんかちつとも無いんだ、もし彼の言葉が全部嘘だつたとしたら、おそらく人生にこんなすばらしいことはあるまいね。おれは一週間でも一日でもあいつの空想に動かされてゐたことを感謝するよ、われわれの人生がいかに彼に負ふところが多いか──考へてみたまへ。」
と。彼ら牛追村の住人にとっては、重要なのは情熱だった。 目を輝かせて語る大助を彼らは愛したのだった。 ここは、空想部落。
で、大助は、やっぱり大嘘つきなのだろうか?・・・実はこの小説、最後の最後に、どんでん返しがあります。
『空想部落』 について
 |
| 尾﨑士郎『空想部落』(圭文館版 昭和37年発行) |
尾﨑士郎38歳の時の作品。 当地(東京都大田区南馬込あたり)に住まう作家たちがモデルになっている(作中人物とモデルとなった作家の対応→)。文中の「牛追ホテル」は、大森ホテルがモデルだろう。昭和10年5月から「朝日新聞」の夕刊一面に連載された新聞小説だ。昭和11年新潮社で単行本化された。装丁は鈴木信太郎で、挿絵は長谷川春子。昭和14年には映画化。 演劇にもなった。
尾﨑士郎について
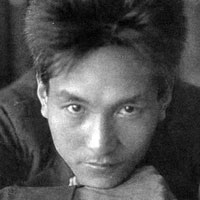 |
| 尾﨑士郎 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『宇野千代(新潮日本文学アルバム)』 |
社会主義に傾倒
明治31年2月5日、愛知県横須賀村(現・西尾市。「尾崎士郎記念館」(西尾市吉良町荻原大道通18-1 map→ HP→)生まれ。三男坊。 横浜へ養子に出されるが養家になじめず、1~2年で横須賀村に戻る。 中学の頃、ドモリを苦にして引っ込み思案になるが、川の堤防で一人発声練習をして、一躍、雄弁家になった。時々激しくドモルのが“熱意の表れ”のような効果になって人を惹き付けた。親友の大須賀健治(山川 均の最初の妻の甥)を通して「平民新聞」接し社会主義に興味を持つ。早稲田大学政治科在学中、学長人事に対する抗議行動の中心に立ち(「早稲田騒動」)、大正7年(19歳)には普選運動のリーダーとして投獄もされている。同年(大正7年)、 長兄がピストル自殺。「放蕩の末の自殺」との報道に反論した。生活の資を得るためか「東洋経済新報」や売文社をわたり歩く。 大正8年(21歳)、月謝滞納と長期欠席により大学から除籍された。
文学における「一人一党」を訴える
大正10年(23歳) 、気まぐれで書いた『獄中より』 が「時事新報」の懸賞小説で2位になり(1位は宇野千代)、文壇から注目される。 同年改造社から出された『逃避行』で早くも社会主義に対する疑問を表明。 どんな主義や理論も嫌悪し、プロレタリア文学・新感覚派といった文学運動からも距離を持つ。大正14年(27歳)、 「不同調」に参加、「文壇における一人一党」を訴えた。昭和4年(31歳)、川端康成らと「没落時代」を創刊。
国民的作家となる
昭和8年(35歳)上泉秀信のすすめで 「都新聞」に『人生劇場』を連載、一躍国民的作家となる。『空想部落』もその頃書かれた。 関心は、物事の悲劇性や、人物の心理的葛藤や情熱を表現すること。この頃の「感覚を論理の上位に置く傾向」に合致した。昭和12年(39歳)、中央公論の戦地特派員として大陸にわたり、昭和16年(43歳)には、菊池 寛や高村光太郎らとともに大政翼賛会協力会の評議員になり、同年、ペン部隊として石坂洋次郎らとともにフィリピンに派遣され、「バターン死の行進」を目撃。昭和18年(45歳)には、文学報国会の常任理事に就任した。
再び人気作家に
敗戦後の昭和23年(50歳)、戦争責任を追及され「公職に就くことと政治的発言・行動の禁止令」の対象となる(昭和25年解除)。昭和24年(51歳)、中間小説のブームに乗り、 『ホーデン侍従』(「週刊新潮」)で再び人気作家となる。
昭和39年2月19日(66歳)、腸ガンで死去。 2日前まで『小説四十六年』を書いていた。
・・・ざんむきえつくして一抹のこるところなし、人生の紅葉ここにことごとく終る、人情を知つてこれに及ばず、ただむくゆるあたはざるをかなしむのみ(尾﨑士郎「病臥日記」の最終部分)
墓所は神奈川県川崎市の春秋苑と愛知県吉良町の福泉寺( )。
■ 尾﨑士郎評
・ 「非常に純粋な人で、会って話をしていると、こちらまで、ほのぼのと、心あたたまる」(真船 豊)
・「人に愛されすぎるというのが唯一の欠点のような男」(前妻の宇野千代)
・ 「士郎さんからは、もうなにも得るものはない」(山本周五郎)
 |
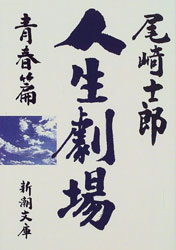 |
| 尾﨑士郎 『小説四十六年 (中公文庫)』 | 尾﨑士郎 『人生劇場(青春篇)』 |
尾﨑士郎と馬込文学圏
大正11年暮(24歳)、室伏高信(31歳)を介して、宇野千代(25歳)に会う。その夜から、菊富士ホテル(東京本郷)で同棲する。翌大正12年、当地(新井宿。東京都大田区)の下宿屋 「寿館」に転居、しばらくして、「都新聞」の文芸部長上泉秀信のすすめで納屋を改造したバンガロー風の家を作った(南馬込四丁目28-11 map→)。 そこには、連日、今井達夫、藤浦 洸、榊山 潤、吉田甲子太郎、室伏高信、坪田譲治、秋田忠義といった酒客が集う。 尾﨑のすすめで、川端康成、牧野信一、間宮茂輔らも当地入りし、 “文士村”の雰囲気が形成された。うわさが拡散する拠点にもなり、彼の家は“馬込放送局”と呼ばれた。同地在住の萩原朔太郎、衣巻省三、広津和郎などとも行き来。 宇野と別れ古賀清子といっしょになってからは、当地を点々とする(南馬込二丁目、山王一丁目、山王二丁目など)。昭和7年春頃(34歳)、大森駅東口のバー「白蛾」のマダム星野幸子と親しくなり、彼女との関わりを 『青い酒場』 『悪太郎』 『売れた酒場』 といった作品に書く(「白蛾もの」)。
戦中、伊東に疎開するが、昭和29年(56歳)、再び当地(東京都大田区山王一丁目36-26。現在 「尾﨑士郎記念館 ※リンク→」 になっている)に戻り、そこで没する。
長女の一枝さんはエッセイストとして活躍されている。
参考文献
●『評伝 尾﨑士郎』(都築久義 ブラザー出版 昭和46年発行)P.36-38、P.47-50、P.75-78、P.114、P.178-180、P.354 ●『パンとペン』(社会主義者・堺 利彦と「売文社」の闘い)(黒岩比佐子 講談社 平成22年発行)P.348 ●『山本周五郎 馬込時代』(木村久邇典 福武書店 昭和58年発行)P.59 ●『文壇資料 馬込文学地図』(近藤富枝 講談社 昭和51年発行)P.17-32 ●『大田文学地図』(染谷孝哉 蒼海出版 昭和46年発行)P.55-62 ●『空想部落』(尾﨑士郎 圭文館 昭和37年発行) ※あとがき ●『尾﨑士郎全集 第六巻』(講談社 昭和41年発行)P.7-24 ●『日本浪漫派批判序説(講談社文芸文庫)』(橋川文三 平成10年初版発行 平成24年7刷参照)P.19
謝辞
・ S.Y様から、映画 「空想部落」 の上映情報、 「空想部落の会」 の会場になった飲み屋 「吾作」 についての情報をいただきました。 ありがとうございます。
※当ページの最終修正年月日
2025.4.21