| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和10年4月9日(1935年。 立原道造(20歳)が手記に次のように書きつけています。
寺田は僕の大きらひな精神に属する。
フランス語に負ふ精神の一つの欠点──ダンディズムに満ちてゐた。彼は、身の飾りに言葉を用ゐる。
「寺田」は寺田
・・・いつも自分を偽はらずに言ふ言葉が、そのままよい言葉と一致することが出来るやうに。
と。まずは言葉に嘘があってはならないこと。どんなに無様であっても、自分の真実を“言葉”にすること。そう努力すること。その真実の“言葉”が「よい言葉」であることを立原は願いました。
 |
勝 海舟は「処世の秘訣」として、ただ一文字を挙げました。
・・・世間の人はややもすると、芳を千載に遺すとか、臭を万世に流すとかいって、それを出処進退の標準にするが、そんなけちな了見で何が出来るものか。男児世に処する、ただ誠意正心をもって現在に応ずるだけの事さ。あてにもならない後世の歴史が、狂といおうが、賊といおうが、そんな事は構うものか。要するに、処世の秘訣は誠の一字だ。(勝 海舟『氷川清話』より)
「誠」という字は、「言」(言葉)と「成」(成る)からなり、言葉通りに成立させること、つまりは嘘をつかないことを意味します。海舟は、世間的に成功することなどは「けち」なこととし、嘘をつかないことこそが生きていく上で最重要であるとしました。「勝てば官軍」とばかりに策謀を巡らせた(インチキの勅書を出したり、インチキの錦の御旗を作ったりした)倒幕勢力に抵抗した新撰組の旗印は「誠」でした。
昔の親は子どもに「嘘をつかないように」と口うるさく言ったものですが、今の親はそれよりも「成功する(結果を出すように)」でしょうか? だとしたら、言葉は危機的状況にあります。言葉が、人を蹴落としたり、人をコントロールしたり、言い逃れしたり、騙したりする道具になり下がりかねません。
「見た目が9割」とか「話し方が9割」とかいう本がもてはやされているようですが、そこに言葉(言葉の真実性)の軽視がないでしょうか? 「見た目」や「話し方」で騙そうとする人に騙されてはいけませんね。
選挙では、候補者が身振り手振りで訴える言葉(公約)より、その人が何を学び、何をして、どういう実績(結果)があったかの方が数倍重要です(というかそれが全て。耳障りのいい言葉などはいくらでも吐けるのだし)。例えば、「花粉症0」を公約にした人が当選したのなら、その人が任期中にそれを達成できたか検証されなくてはなりません。本来それはマスコミの仕事ですが、マスコミは果たしてやってくれているでしょうか? 「花粉症0」が言葉の飾りだったのなら、それを吐いた人の「誠」実性が疑われます。
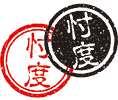 |
言葉は“生もの”なので、時間がたつと変質します。
例えば、「忖度」という言葉。すでに「詩経」(孔子が選んだともされる中国最古の詩集)にも見られ、人の心を推し量るといった好ましい印象の言葉としてずっと使われてきたようです。ところが、平成28年からの「森友学園問題」(まだ解決されていない)で、財務官僚が首相の意向を「忖度」したとされてから、「忖度」という言葉にマイナスイメージが付与されるようになります。「広辞苑(第七版)」(岩波書店。2018年発行)では、まだ、「忖度」は「他人の心中をおしはかること。推察。」としかありませんが、翌年発行の「広辞林(第四版)」(三省堂。2019年発行)では、「広辞苑」同様の「他人の気持ちをおしはかること。推測。」の他に、「地位や立場が上の者の意向を推測し、それにそうような行動をすること。」という意味が追加されています。三省堂は、さらに2022年発行の「三省堂国語辞典(第八版)」で、2つ目の意味を「有力者などの気持ちを推測し、気に入られるように行動すること。」とし、2024年発行の「現代新国語辞典」では「相手が望んでいると思われることに気を回すこと。また、そうして、言われる前にそれを行うこと。」とし、用例として「大臣への、官僚による忖度」を追加、「権力に媚びて自己保身を図るイメージ」を強調しました。一つの事件が、一つの日本語を変質させたのです。
言葉が不完全なものであることも忘れないでいたいです。嘘を言わないようにしてもどうしても多少は嘘が混ざるし(誇張があったり、言葉足らずだったり)、言葉の多義性によって受け取られ方も様々。たくさん書けば、大げさに書けば伝わるかと言えば、そうとも限りません。「悲しい」「つらい」と陳腐な言葉で表せば、「悲しさ」や「つらさ」の実感が逃げていってしまうこともあるでしょう。この言葉の不完全性にどう向き合えばいいでしょうか。志賀直哉の文章はやはりすごいです。
人は言葉で考え・思うので、より多く言葉を獲得すれば、それだけ遠くへ行ける(より豊かなイメージの中を生きることができる)ことでしょう。言葉を一つ一つ獲得していくことは背景にある自然や文化を理解し、共感することにつながります。差別に無縁でいられる人は、きっと言葉を多く持っている人なのでしょう。古語、外国語、特殊語、俗語、固有名詞(人の名、花の名、雲の名、虫や鳥の名・・・)など、短い一生ですが、一つでも多くの言葉を覚えたいです。
・・・辞典というものは、力強い仕事の支えだし、もし、まったく辞書・字典のたぐいが消滅したと仮定したら、方角もわからぬ砂漠のまん中に、たった一人、立たされてでもいるような心細さに襲われるにちがいない。
私は
葬式も墓も無用、骨は海にでも撒いてしまってほしい人間で、死んだら富士霊園に建つ文学者の墓の、自分の名の下に、使い古した『広辞苑』を一冊、埋めてくれと遺言してある。作家としての私の苦しみに、長年月、寄り添ってくれていた辞書……。一緒に無に還りたい。(杉本苑子「一緒に無に還りたい」より)
伊達騒動についての初の本格的な研究書『伊達騒動実録』の著者・
傑作ミステリー『レディ・ジョーカー』に出てくる合田警部補の知的な輪郭を、著者の高村 薫が次のようにスケッチしています。
・・・合田は日経サイエンスを放り出し、またちょっとテレビの画面を眺めた。イギリスの、電力会社の民営化に伴う原発の管理の問題。gridという一語を手近な雑誌の裏に書きつけ、辞書に手を伸ばしたところで、電話が鳴った。・・・(高村 薫『レディ・ジョーカー』より)
 |
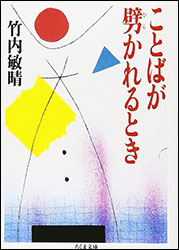 |
| 山崎雅弘『詭弁社会 〜日本を蝕む”怪物„の正体〜(祥伝社新書)』。詭弁があふれる日本。詭弁に踊らされないためのリテラシー | 竹内敏晴『ことばが |
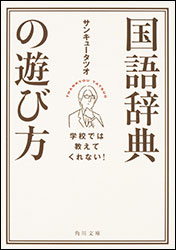 |
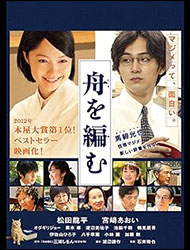 |
| サンキュータツオ『国語辞典の遊び方 〜学校では教えてくれない! 〜(角川文庫) 』 | 「舟を編む」。新しい辞書ができるまで。“変人”だからこそ、場を得て、スーパーマンとなる |
■ 馬込文学マラソン:
・子母沢 寛の『勝 海舟』を読む→
■ 参考文献:
●「火山灰まで」(立原道造)、「解題」(宇佐美 斉)『立原道造全集3』(筑摩書房 平成29年発行)P.19、P.36、P.618、P.620 ●『氷川清話(講談社学芸文庫)』(勝 海舟 編:江藤 淳、松浦 玲 平成12年初版発行 平成27年発行40刷)P.380 ●「忖度」※『平成の新語・流行語辞典』(米川明彦 東京堂出版 令和元年発行)に収録 ●『春風秋雨』(杉本苑子 読売新聞社 平成9年発行)※『一緒に無に還りたい』を収録
※当ページの最終修正年月日
2024.4.7