| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
大正13年1月29日(1924年。 、小島政二郎(29歳)が、ロマン・ローラン(58歳)の誕生日を祝って、写真の前に赤飯を供えたとのこと。その後も毎年そうしたようです。
1年前の関東大震災(大正12年9月1日)で小島も大きな打撃を受けますが、その頃ちょうど、ロマン・ローランの 『ジャン・クリストフ』(Amazon→) を読んでいて、主人公のジャンが不幸と格闘して自力で運命を切り開いていく姿に
主人公のジャンは、ベートーヴェン、ミケランジェロ、ミレー、トルストイを合体したような超人ですが、けっこう変なヤツで親しみが持てます(笑)。
 |
 |
大正7年、27歳のプロコフィエフが、ロシア革命の混乱を避けて米国へ向かう途上、5月31日から8月2日までの約2ヶ月間日本に滞在しました。そのおり、ショーペンハウエルの『意志と表象としての世界』(Amazon→)を携行。
ショーペンハウエル(wik→)は、かつて日本人にも、学生を中心によく読まれた哲学者です。当時の学生の口の端にのぼる「デカンショ」は、デカルト、カント、ショーペンハウエルの略と言われます。ショーペンハウエルについて、辻 まことが次のように書いています。
・・・私は静かな読書が好きだ。元来読書というのはそんなものじゃないだろうか、いつだったか、ショーペンハウェルについて折原
確かにショーペンハウェルの哲学は詩心をもって読まれなければならないし、またそれを読者にうながす著作だ。・・・(辻 まこと「親孝行の弁 ─おやじとおふくろの本」より)
幕末の頃を生きたショーペンハウエルは、近代の病弊(自己中心的享楽主義、没理想的な営利追求主義など)にいち早く気づき、それに抗いました。 ワーグナー、ウィトゲンシュタイン、アインシュタイン、フロイト、ユング、トルストイ、トーマス・マン、森 鴎外、堀 辰雄、萩原朔太郎、筒井康隆らにも小さくない影響を与えたようです。
 |
松竹蒲田撮影所で5歳から子役をやっていた高峰秀子は、通勤の便から13歳まで当地(東京都大田区蒲田と大森)に住んでいました。子役としてひっぱりだこで小学校へもろくに通えなかった彼女を支えたのが、蒲田尋常高等小学校(現・大田区立蒲田小学校。東京都大田区蒲田一丁目30-1 Map→)の1~2年の時の担任。彼が差入れてくれた児童雑誌「コドモノクニ」や「小学一年生」で本と出会います。本屋には「私みたいなバカが入っちゃいけない場所」と思っていたそうですが、大森の安アパートで一緒だった「川島のニイちゃん」に励まされて入れるようになり、安い本(おもに、星一つ(20銭)の岩波文庫)を買ってむさぼり読むようになります。後年、高峰は「一冊の本」として『
思うに、誰しもが持っていて(捨てちゃた人も多いかも)、一番に「宝の持ち腐れ」なのは、国語辞典、漢和辞典、英和辞典、古語辞典といった辞書の類かもしれません。言葉とそのイメージが詰め込まれている最たるものだろうからです。辞書が行き渡っていない時代にあっては、それこそ一冊で「家が一軒」建ちました。勝 海舟は、オランダ語の辞書を書き写して自分のものにしています。勝と一緒に咸臨丸で渡米した福沢諭吉と中浜万次郎(ジョン万次郎)は、米国で何はおいても「ウエブストル」(「ウエブスター」。英語の辞書)を入手しています(福沢と中浜が「ウエブスター」を最初に“輸入”した人のようだ)。英語の辞書があっても英語が分からなければ意味がありません。まだ、英和辞書がなかったようで、福沢は英蘭対訳の辞書(蘭語はオランダ語)で、英語を学んでいきました(オランダ語の素養はあった)。要はやる気で(心からワクワクできるものに出会うこと)、やる気さえあれば、どんな条件でも、学んでいけるものなのでしょうね。
小池真理子さんは小学校6年の頃、当地(東京都大田区久が原)に住んでいました。 その頃、東急池上線「千鳥町駅」前の本屋でモンゴメリーの『赤毛のアン』を買って読んだそうです。この一冊が、彼女の読書の原点なんだそうです。
 |
折口信夫は柳田国男の『遠野物語』を「世の
小林多喜二は、葉山嘉樹の『淫売婦』の読書体験を「記念すべき出来事」と22歳の時の日記に書いています。
一高時代の川端康成は、志賀直哉の短編集『夜の光』を「日本では第一の書とだいじにした」そうです。
アラスカの自然と人を撮り続けた星野道夫がその地を志ざすようになるのは、東京神田の洋書専門店でたまたま手に取った一冊の写真集がきっかけでした。「まるでぼくがやってくるのを待っていたかのように、目の前にあった」本との出会いには、運命的なものを感じます。
高村 薫さんの『レディ・ジョーカー』(Amazon→)に
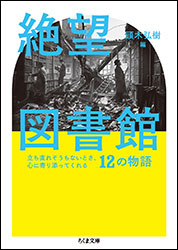 |
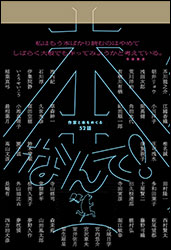 |
|
|
|
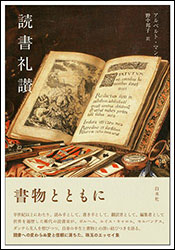 |
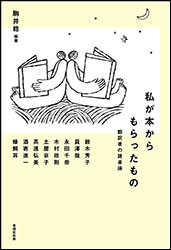 |
| アルベルト・マングェル『読書礼讃』(白水社)。訳:野中邦子。「読むこと」とは、「読者であること」とは | 『私が本からもらったもの 〜翻訳者の読書論〜』(
|
■ 馬込文学マラソン:
・ 小島政二郎の『眼中の人』を読む→
・ プロコフィエフの『彷徨える塔』を読む→
・ 辻 まことの『山の声』を読む→
・ 堀 辰雄の『聖家族』を読む→
・ 萩原朔太郎の『月に吠える』を読む→
・ 小池真理子の『欲望』を読む→
・ 志賀直哉の『暗夜行路』を読む→
・ 川端康成の『雪国』を読む→
■ 参考文献:
● 『眼中の人』(小島政二郎 文京書房 昭和50年発行) P.299-309 ●『プロコフィエフ短編集』 (サブリナ・エレオノーラ・豊田菜穂子共訳 群像社 平成21年発行) P.190 ● 『辻 まこと・父親辻 潤』(折原脩三 リブロポート 昭和62年発行) P.105-108 ● 『意志と表象としての世界(1)(中公クラシックス)』(ショーペンハウアー 訳:西尾幹二 解説:鎌田康男 平成16年初版発行 平成27年8版参照)P.1-5 ● 『わたしの渡世日記(上)(文春文庫)』(高峰秀子 平成10年初版発行 平成23年12刷参照)P.34-188 ●『福翁自伝』(福沢諭吉 時事新報社 明治32年発行 NDL→)P.193-194、P.201-202 ● 『小林多喜二(新潮日本文学アルバム)』(昭和60年発行) P.37 ● 「川端康成(新潮日本文学アルバム)」(昭和59年発行)P.13 ●「小池真理子さん(作家の読書道 第56回)」(WEB「本の雑誌」→) ●「星野道夫のアラスカとの出会い in 1971(その2)」(Nearest Faraway Place→)
※当ページの最終修正年月日
2025.1.29