| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
大正15年10月3日(1926年。 折口信夫(39歳)が、長野県の上高地(Map→)から、柳田国男(51歳)に葉書を出しています。
うちむかふほたかゞ峰のさむけさよ
雪をかうむる青草のいろ
2人は一
折口は、中学時代、英語や物理・数学に見向きしなかったため成績は68名中65番でしたが、大正9年、新設された「國學院大學」(早稲田、慶應に続く、大学令に基づく3番目の大学)に進むや、国文学と文法研究でたちまち頭角を現します。大学時代後半には、考古学や人類学にまで関心を広げ、柳田の研究論文にも目を通すようになったようです。大学卒業後、郷里の大阪に戻って2年半中学で教鞭をとり、大正3年(27歳)に再上京、その頃、柳田の『遠野物語』に出会いました。
大正2年、柳田(38歳)が雑誌「郷土研究」を創刊するや、折口は大阪の民俗を報告した「
 |
柳田国男 |
柳田は帝大で農政学を学び、卒業後、農商務省の高等官僚になって講演旅行などで東北の農村などの文化に触れ、足を運んで調査・研究(フィールドワーク)するようになります。明治41年、遠野の
『遠野物語』には、
 |
 |
 |
佐々木喜善 |
情報提供者として『遠野物語』成立に貢献した佐々木喜善は、柳田より11歳若い明治19年生まれで、折口の1歳年上です。遠野の土淵村で生まれ、語り部の祖父から民話や妖怪譚を聞きながら育ちました。民話の収集・研究や著述のかたわら土淵村の村長も務めます。
佐々木同様、岩手県出身の宮沢賢治が、『遠野物語』の発行から16年たった大正15年(賢治29歳)、「ざしき
やはり東北出身(宮城県)の石川善助と賢治の仲も「ざしき童子」が取り持っています。大正14年の暮れ近く、善助は花巻の賢治を初めて訪ねました。そのおり賢治から「ざしき童子」の話を聞き、「その夜ひどい雪路を歩きながら再びかの日の怪異に心理を新しくした」と、善助が「
彼らはなぜ同時期に「ざしき童子」に興味を持ったのでしょう。もちろん、『遠野物語』の影響もあるでしょう。が、実は日本、幕末頃から、平田篤胤の死後世界の研究や、黒住教・天理教・金光教といった「神がかり」による新派神道の成立といった超常現象への志向があり、西洋からも心霊主義(スピリチュアリズム。死者の霊との交信など)が伝わり、一種のオカルトブームでもあったようです。近代化(西洋)に対するアンチテーゼの側面もあったかもしれません。「都市化の一番の弊害はどこもかしこも明るくなって、幽霊の出る場所がなくなったこと」と言ったのは泉 鏡花でしたか。佐々木が使っていた筆名の鏡石の「鏡」は鏡花から取っており、 柳田も鏡花の文章を手本にしたそうです。
善助が妖怪の出現について次のように考察しています。
・・・ともあれ人は
今や、人々の感情は、かつてよりは様々が形で記録され表現され残るようになりましたが、それでもなお、言葉にならない(言葉にできない)感情が、“現代の妖怪”を生み出しているかもしれません。
近年、オカルト(神秘的な力の存在を是認するあれやこれや。占いや霊感・霊力や鬼など)がマスコミに無批判にあふれています(金になるのでしょう)。「私は霊感が強い」と豪語する人と、それを真に受けてひれ伏す人々。「科学的精神」を意識的に取り戻さないと、日本は大変なことになりますね。「オカルト」の侵入と「科学的精神」の退潮は、権力のカルトや(似非)宗教の取り込みとか、詐欺(表層の悪用)の蔓延とも無関係でないでしょう。
民俗学に分け入るのなら、当然、「オカルト」に対する批判精神も必要。
 |
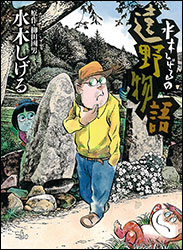 |
| 柳田国男『遠野物語 〜付・遠野物語拾遺〜 (角川ソフィア文庫)』 | 水木しげる『水木しげるの遠野物語』(小学館) |
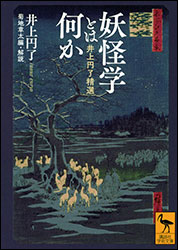 |
 |
| 井上円了『妖怪学とは何か (講談社学術文庫) 』。妖怪博士による妖怪(迷信)退治。著者の井上は、東洋大学を創設した仏教哲学者 | 大塚英志『社会を作れなかったこの国がそれでもソーシャルであるための柳田國男入門 (角川EPUB選書)』 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 石川善助の『亜寒帯』を読む→
■ 参考文献:
●『折口信夫(新潮日本文学アルバム)』(昭和60年発行)P.15、P.20-24、P.31-33、P.68-69、P.72-73、P.105 ●『折口信夫全集 第31巻』(昭和3年初版発行 昭和49年発行新訂再版)P.178 ●「民話 賢治と意外な接点をもっていた、遠野物語の語り手 佐々木喜善」(でくのぼう宮沢賢治の会 代表:熊谷えり子)(宮沢賢治手帳→) ●『詩人 石川善助 そのロマンの系譜』(藤 一也 萬葉堂出版 昭和56年発行)P.160、P.456 ●『鴉射亭随筆 〜石川善助随筆等作品・書簡集〜』(編集:森中秀樹 あるきみ屋 令和5年発行)一〜五丁 ●「「21世紀の民俗学」をはじめよう:気鋭の民俗学者、畑中章宏に聞く、いまどきの「流行」盛衰記」(
※当ページの最終修正年月日
2024.10.3