| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
関東大震災の1ヶ月ほど前の大正12年8月4日(1923年。 堀 辰雄(19歳)が、室生犀星(34歳)に連れられて、軽井沢を初めて訪れています。
その日の感動を堀は、友人の
一日ぢゆう、
これは堀の「西洋」への憧れの表現とみていいでしょう。当時、軽井沢には「西洋」の具体がありました。
旧軽井沢(現在の旧軽井沢銀座あたり)は中山道の
ところが幸運なことに、まもなく(明治19年)、カナダの宣教師ショーが旧軽井沢に別荘を作ったのをきっかけに、在日外国人の避暑地として発展していきます。
 |
 |
| ショーが別荘を建てたあたりに建つ「ショー記念礼拝堂」(長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢57-1 Map→)。右手に写っているのがショーの像 | 大正時代の軽井沢。外国人が多く行き来し、横文字の看板が目立つ ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『軽井沢ものがたり』(新潮社) |
軽井沢は堀によほど鮮烈な印象を残したのでしょう、堀はその後、終生、軽井沢と関係を持ち続けます。最初、「つるや旅館」(長野県北佐久郡軽井沢町旧軽井沢678 Map→ Site→)などに滞在していましたが(「つるや旅館」の主人はショーの別荘建築に協力した)、昭和13年、加藤多恵子と結婚した後は、軽井沢に別荘を借りるようになります。 3度別荘の引越しをし、4度目で初めて別荘を購入。 昭和19年には、近くの
明治政府は、明治13年頃から、文化、制度、技術のみならず、風俗や習慣まで「西洋」を真似ようとしました(「欧化政策」)。その象徴「
堀は明治37年生まれで、欧化政策が取られるようになって20年ほどたっており、もう周りにも「西洋」が散見されたことでしょう。洋服、シルクハット、コウモリ傘、靴、レンガ造りの洋式建築、洋食などは別に珍しいものでなくなっていたことでしょう。人力車が走るようになり、馬車も走り、鉄道も開通しました。
当地(東京都大田区)にも、明治9年、「大森駅」(東京都大田区大森北一丁目6 Map→)ができ(新橋-横浜間に日本初の鉄道が開通したのが明治5年なので、その4年後)、大正元年には、西洋人の宿泊を考慮した「
「西洋」をよく取り入れた状態を「ハイカラ」(high collar)と
文学も例外でありません。
坪内逍遥を
しかし、こういった「欧化」には負の面がありました。
「西洋」にひれ伏すことは、すなわち、日本文化や歴史を軽視・蔑視すること。廃仏毀釈は江戸末期からの神国思想や明治政府の神仏分離政策によるとされますが、各地の仏像や仏具の除去・破壊がなされた心情には、日本文化や歴史に対する軽視・蔑視も反映されたことでしょう。
その頃、浮世絵などの日本の芸術作品が海外に大量に流出しました。西欧ではジャポニズム(日本趣味)が流行し、日本の芸術作品をほしがる人がたくさんいたので、自国の文化を軽視していた日本人は「どうぞどうぞ」と安値で売ってしまったのでしょうね。
明治も中程になると、「維新」「文明開化」「富国強兵」といった言葉に浮かれ、成功者になったとのおごりも出てきて、「非文明の他のアジア諸国とは手を切って、日本は西洋の仲間入りをすべき」(脱亜入欧。脱亜論)との考えも出てきます。アジア諸国との深い関係の中で、長年にわたって文化や社会を培ってきたのに、そのアイデンティティーを捨て去ろうというのですから、アホですね。何かにひれ伏してきた者は、今度は、自ら(自国)にひれ伏せされたがるものですかね?
社会心理学者の岸田
現在も、米国が威張っても日本政府はペコペコペコペコ。また同じようなプロセスをたどって“発狂”しまいかと心配になります(え? もう発症している?)。
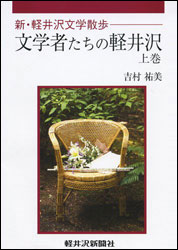 |
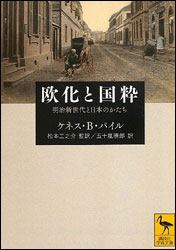 |
| 吉村祐美『新・軽井沢文学散』(軽井沢新聞社) | ケネス.B・パイル 『欧化と国粋 〜明治新世代と日本のかたち〜(講談社学術文庫) 』。監修:松本三之介、訳:五十嵐暁郎 |
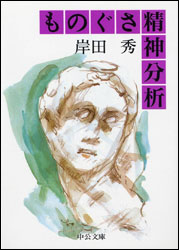 |
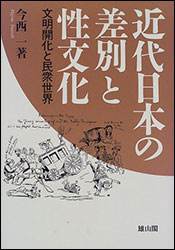 |
| 岸田 秀『ものぐさ精神分析 (中公文庫)』 | 今西 一『近代日本の差別と性文化 〜文明開化と民衆世界〜』(雄山閣出版) |
■ 馬込文学マラソン:
・ 堀 辰雄の『聖家族』を読む→
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 南川 潤の『風俗十日』を読む→
■ 参考文献:
●『評伝 堀 辰雄』(小川和佑 六興出版 昭和53年発行)P.39 ●『堀 辰雄(人と文学シリーズ)』(監修:川端康成・井上 靖 学研 昭和55年発行)P.122 ●「評伝」「略年譜」(小久保 実)※『堀 辰雄(新潮日本文学アルバム)』(昭和59年発行)P.20-21、104-106 ●『軽井沢物語』(佐藤不二男 軽井沢書房 昭和51年発行)P.58-63 ●「堀 辰雄の軽井沢を歩く Ⅱ 【別荘編】」(東京紅團→) ●「堀 辰雄の追分を歩く」(東京紅團→) ●「装いの文明開化 〜官僚から庶民まで〜(知ってなるほど 明治・大正・昭和初期の生活と文化)」(国立公文書館/アジア歴史資料センター→) ●「廃仏毀釈」※「ブリタニカ国際大百科事典」に収録(コトバンク→) ●「浮世絵」(小林 忠)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に収録(コトバンク→) ●「脱亜論」(松永昌三)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に収録(コトバンク→)
※当ページの最終修正年月日
2024.8.3