| {column0} |

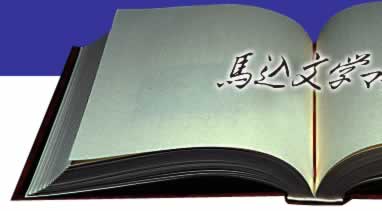







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
日本軍の奇襲によって米海軍の戦艦・アリゾナは、1,177名の米兵とともに沈没した ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:米国国立公文書記録管理局が管理する写真
昭和16年12月8日(1941年。
、日本軍が、ハワイのオアフ島の真珠湾の米海軍太平洋艦隊基地(map→)を奇襲(宣戦布告しないで攻撃)、戦艦5
日本軍は同日(12月8日)真珠湾の攻撃よりも1時間以上も早くに、英国領マレー半島にも上陸、半島沖の英国東洋艦隊の主力を撃滅(英国にも宣戦布告しなかった)、翌昭和17年5月までに東南アジアのほぼ全域を制圧しました(昭和16年12月中にグアム島と香港、翌昭和17年1月にはフィリピンのマニラ、2月にはマレー半島とシンガポール、3月には
 |
山本五十六 |
山本
日本が日米交渉を断念して米国との戦争に踏み切ったのは、米国が「中国と仏印からの全面撤兵」「日独伊三国同盟の空文化」「中国の国民政府(
近衛文麿首相(50歳)は中国から撤兵してでも日米交渉を継続しようとしましたが、陸軍大臣の東条英機(56歳)が撤兵に強く反対し、(第3次)近衛内閣は総辞職に追い込まれました(決断を避けて逃げたとの見方もある)。東条が首相になって(陸軍大臣を兼任)対米英戦争となりました。
当初、真珠湾における日本軍の“戦果”に日本中が沸き立ちました(きっとスポーツの国際試合で日本チームが大勝利したときのようだったのでしょうね)。伊藤 整(36歳)は「今日は人々みな喜色ありて明るい」と書き、小林秀雄(39歳)は「大戦争がちょうどいい時にはじまってくれたという気持ちなのだ。戦争は思想のいろいろな無駄なものを一挙になくしてくれた」と書き、亀井勝一郎(34歳)は「返答であり、復讐だったのである。維新以来我ら祖先の抱いた無念の思いを、一挙にして晴すべきときが来た」と書いています。横光利一(43歳)も、「祖先を神だと信じた民族が勝ったのだ」 「もっとも自然なことだ」と書き、高村光太郎(58歳)などはずばり「十二月八日」という詩で「記憶せよ、十二月八日。この日世界の歴史あらたまる」と戦争を賛美しました。
坂口安吾(35歳)は、真珠湾攻撃の際、小型特殊潜水艇「
社会性を捨象し、勉強しないで書いた「身の回り文学」「自分の思い文学」「思いつき文学」「考えるな文学」「“文学的”文学」の作者が、時代の空気にいかに流されやすいか物語っています。
ドナルド・キーンが言い切っています。
・・・作家たちは戦争勃発の際、ほとんど一致して軍国主義者の背後に立った。彼らは、
日本には戦争に疑問をもったり反対する人はいなかったのでしょうか?
大本営(天皇直属の戦争指導機関)は国策の欠陥を示すことは発表しませんでしたし、マスコミも軍部と癒着し戦意を高揚させるようなことを国民に盛んに垂れ流したので、多くの国民が「大日本帝国バンザイ!」となり日の丸を振りました。国策に反する出版物は排除され、国策に反する学者も排除され、国策に反対する人たちは捕まり、あるものは殺されました。国策に異議を唱えた政治家も排除されました。
しかし、日本軍が勝利を重ねたのは真珠湾攻撃からわずか半年ほどです。昭和17年5月には珊瑚海海戦(珊瑚海 Map→)で米国の機動部隊の反撃にあってポートモレスビー(ニューギニア島。現在、パプアニューギニアの首都 Map→)の攻略に失敗、翌6月にはミッドウェー海戦(ミッドウェー島 Map→)で日本海軍は敗北、翌昭和18年2月には日本陸軍が補給路を断たれてガダルカナル島から退却し、同年5月にはアッツ島(Map→)の日本兵が全滅。翌昭和19年6月にはマリアナ沖海戦で壊滅的打撃を受けて、制海権も制空権も失って、マリアナ諸島のサイパン島(Map→)も占領されます。同年11月頃からマリアナ諸島から飛んでくる大型爆撃機B29によって本土が空襲されるようになりました。
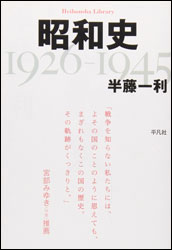 |
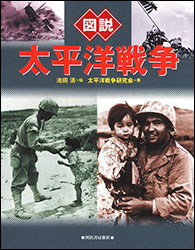 |
| 半藤一利『昭和史(1926-1945)(平凡社ライブラリー)』。満州事変からアジア・太平洋戦争に破れるまでの一連の流れ | 『図説 太平洋戦争(増補改訂版)』(河出書房新社)。編:池田 清。写真図版350点。戦争を避けるためには、戦争がどうだったか知る必要がある |
 |
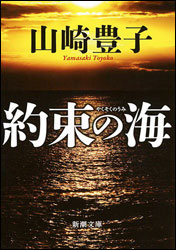 |
| 保阪正康『山本五十六の戦争』(毎日新聞出版)。対米英戦争に反対しながらも、真珠湾攻撃を指揮することになる男の生涯 | 山崎豊子『約束の海 (新潮文庫) 』。「戦争をしないための軍隊」を模索する。山崎最後の作品(未完)。酒巻和男少将をモデルにした人物も登場する |
■ 参考文献:
●『図説 太平洋戦争』(平塚
※当ページの最終修正年月日
2024.12.8