| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
江戸終末、近畿、四国、東海地方で、人々は仮装し、「ええじゃないか」と叫びながら、踊り狂った・・・ ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:「慶應四豊年踊之圖(「絵暦張込帳」より)」(河鍋暁斎)(NDL→)
 |
昭和11年2月29日(1936年。
中野重治(34歳)が『
タイトルにある「昭和11年2月29日」は、「二・二六事件」の3日後にあたり、文章の冒頭に、銃声やラッパの音、万歳の叫び声を聞いたと書かれています。「二・二六事件」は、陸軍の青年将校が1,500名近くの下士官兵を率いて起こした流血クーデター (暗殺・暴行などの恐怖手段に訴えた「テロ」)で、天皇に上奏できる立場の重臣を殺害して、天皇親政を一挙に実現しようとしたものです。昭和天皇の断固とした拒絶によって未遂となりますが(被害者は出た)、「軍部は怖い」「軍部に反対したらただでは済まない」との恐怖の観念を庶民にも政治家にも根強く植え付け、この後の軍部主導の政治に道をつけることとなりました。
中野は、実態がまだよくつかめていない「二・二六事件」には直接は触れていませんが、この事件が象徴するファシズム(侵略政策をとる独裁制)の台頭と、それを許し、後押ししている文学状況を批判しました。
中野が槍玉にあげたのは、雑誌「文学界」の編集責任者・小林秀雄(33歳)と、新感覚派の騎手・横光利一(37歳)。中野は彼ら2人の「反論理的」な姿勢を厳しく批判しました。
小林は、“日本近代批評の創始者・確立者”として今も言及される文芸評論家です。小林の評論を一言でいうと、“文学的な評論”。自分が美しいと確信したものを、文学的に表現したもの。理詰めでなく、感性に訴えて感動させてしまう文章です。例えば、
・・・嫌いと言うのは
・・・解釈を拒絶して動じないものだけが美しい・・・(小林秀雄「無常といふ事」より)
・・・かなしさは疾走する。涙は追いつけない・・・(小林秀雄「モオツァルト」より)
・・・美しい『花』がある、『花』の美しさという様なものはない・・・(小林秀雄「
といったもので、わけが分からないだけに(論理的でないだけに)、含みが生まれ、確かにうっとりしてしまいそうな言葉たちです。硬直しがちな「論理的」な評論を一つの“文学”にまで高めたという点では、小林にも功績があったのでしょう。
しかし、小林が「論理的」なものを攻撃するとき、彼の問題が明瞭になります。
・・・一体論文といふものが、論理的に正しいか正しくないかといふ事は、それほどの大事ではない、その議論が人を動かすか動かさないかが、常に遥かに困難な重要な問題なのだ・・・(小林秀雄「アシルと亀の子」より)
・・・彼の提出するものは、何んでも、悪魔であれ天使であれ、僕等は信ぜざるを得ぬ。そんな事は御免だと言つても駄目である。・・・(小林秀雄「モオツァルト」より)
坂口安吾が小林の評論を「教祖の文学」と看破しています。小林の言葉は上品でも、言っていることは、つまりは「つべこべ言うな」であり、「人を動かしえるもの(力や権力やブーム)」に従えであり、「信ぜよ」なのです。小林はヒットラーを手放しで賞賛しました。
満州事変の頃からファシズムの台頭が顕著になりますが、それと呼応するかのようにして、小林のような、論理を軽視する、「信ぜよ」「考えるな」「結果オーライ」の言説が、「進歩」「文化」「自由」を装って現れ、ファシズムをアシストしました。中野が「二・二六事件」の3日目に、あえて小林批判をしたのはそのためでしょう。中野はズバリ言います。
・・・そして分らない言い
その後、小林は反論を試みますが、ある意味中野の論を認め、自分の文章は評論ではなく「評論的雑文」なのだと逃げました。
かの時代の「論理的なものに対する嫌悪」は、横光利一の「新しい時代の土俵は、論理の立ち得るような
「論理的なものに対する嫌悪」は大衆に受け入れやすい傾向を持ち、その傾向は、世の中を動かし、実権を握ろうとする者たちに利用されてきましたし、今も利用されています。江戸末期の1867年に吹き荒れた「ええじゃないか」も、討幕軍が、民衆を「反論理」(「世直りええじゃないか」「長州がのぼた、物が安うなる、えじゃないか」)の狂奔に導き、討幕軍のめちゃくちゃには民衆が目をつぶり、結果が出れば「いいじゃないか」といった世論に染め上げようとした悪質な策謀だったのでは?
 |
ソクラテス |
大衆の「論理的なものへの嫌悪」は、どこから来るのでしょう?
「知」「未知」の海が全世界に広がっていますが、私たちは生涯かけてもその一滴ほども知り得ないでしょう。ですから、知識人とか言われる人たちも含め私たちは皆、一生、無知(バカ)です。紀元前400年代(日本では弥生時代)、ソクラテスは「無知の知」という観念でそれを説明しました。
どんなに勉強しても、考え続けても、我々は一生バカですが、それでも生きている限り「知る」ことにつとめ、不完全ながらも考え続ける態度が「知性主義」で、反対に、少々知識を持っている人への妬み心からか、勉強したくないという怠け心からか、自分はバカではないという威張りたい心からか、「知る」ことを軽視し、知ろうとする人をバカにし、冷笑するのが「反知性主義」なのでしょう。つまりは、バカに輪をかけたバカ。
政府が不祥事を重ねている最中なのに、テレビで「文句ばかりの人は嫌ですね〜」とか、「もっと前向きに考えられないのでしょうかね〜」とか言って批判を封じようとする人たちは、不祥事を重ねている政府かそれを支えている組織(社会)からいいものをもらっている人か、バカに輪をかけたバカなのでしょう。
映画「燃えよドラゴン」でブルース・リーが放つ「考えるな、感じろ」という名セリフは、身体性の回復をいっているのであって、バカに輪をかけたバカになれという意味では決してないですね。バカに輪をかけたバカが引用しそうなので、念のため。
人のいい人は、自分も「バカ」(人間の本質としてのバカ)なのだから、人をバカにするのは止めようと思うかもしれませんが、「バカに輪をかけたバカ」(人間の本質としてのバカ性を見ようとしないバカ)は権力者(政治的な権力者、宗教的な権力者、その他、血縁的、地縁的、組織的、暴力的権力者など)に利用され、いいことがないので、後者の「バカ」の方は批判した方がいいです(感染力が強く、無視すると増殖するし)。
 |
 |
 |
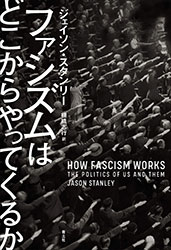 |
| トム・ニコルズ『専門知は、もういらないのか』(みすず書房)。翻訳: |
ジェイソン・スタンリー『ファシズムはどこからやってくるか』(青土社)。訳: |
■ 馬込文学マラソン:
・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→
■ 参考文献:
●「閏二月二九日」(中野重治 昭和11年「新潮」に初出)※『日本近代文学評論選 【昭和篇】(岩波文庫)』(平成16年初版発行 平成17年発行3刷)に収録 ●「はじめての 小林秀雄」(
※当ページの最終修正年月日
2024.2.28