| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
明治9年10月24日(1876年。
熊本の士族(旧武士)の政府に対する反乱「
明治政府は、この3月に「廃刀令」を出して刀を帯びる特権(誇り)を士族から
桜園の後継者と目された
しかし、彼らは国学・神道の信奉者なので、鉄砲といった西洋由来の武具は一切使わず槍と刀を手にしたので、政府軍の兵力の前ではあえなく散るのみでした。太田黒も加屋も戦死し、86名は
三島由紀夫の『
大正8年1月、芥川龍之介(26歳)が『開化の
溝口健二監督の映画に「神風連」 がありますが、フィルムは見つかっていないようです。脚本は出版されています(Amazon→)。
------------------------------------------------------
米国のペリーが4艘の軍艦(黒船)を率いてやってきたのが嘉永6年(1853年)です。いじめっ子に追随するがごとく、英国、フランス、ロシア、それに長年日本と穏やかに国交したオランダまでが、日本に対して強圧的になってきます。圧倒的な暴力(軍事力)をチラつかせて開国を迫まるような“野蛮な国々”をよしとする日本人はいなかったはずです。「帰ってくれ」「さもなくば許さず」といった攘夷の念を、薩長土肥に限らず、朝廷も、幕府も、日本に住むほぼ100%の人が共有したことでしょう。
しばらくすると攘夷の念を爆発させる人が現れ始めます。安政6年7月27日(1859年)ロシアのムラヴィヨフが7艘の軍艦で来航のおり、乗組員の海軍少将・ロマン・モフェト、水兵イワン・ソコロフ、調理師のミハイル・マカロフの3名が横浜で襲われ前者2名が絶命(最初の外国人殺害)、横浜で葬られました(「外国人墓地」(横浜市中区山手町96 Map→)の始まり)(「ロシア人2名殺害事件」)。
幕府も攘夷の念を共有していましたが、列強と折衝に当たらなくてはならない立場にあり、抵抗したならば、強大な軍事力で叩きのめされることも分かっていたので、攘夷の念はいったん脇に置いて、時間を稼ぎ、その間に台場の建設や、軍備の調達、西洋式の軍事技術の習得を急いだのでした。「ロシア人2名殺害事件」はそういった時に起きました。ロシアは全艦隊の砲窓を開いて200門以上の大砲を突き出して威嚇しつつ、下手人と指図した人の捕縛と処刑を迫ってきました。
事態を収束させようとした幕府は、水戸藩の家老・
幕府の厳しい処断に攘夷派は強く反発し、翌安政6年3月3日(1860年)、水戸と薩摩の浪士が大老・井伊直弼(44歳)を殺害(「桜田門外の変」)。この頃になると、攘夷の矛先は外国人だけでなく、外国人と対応する幕府へも向けられていきます。翌文久元年(1861年)には水戸浪士が東禅寺(東京都港区高輪三丁目16-16 Map→)の英国公使館が襲撃されます(「第一次東禅寺事件」)。
翌文久2年(1862年)になると事件の目白押しで、水戸浪士によって老中・安藤信正が襲撃され(1月15日「坂下門外の変」)、東禅寺がまた襲撃され(5月29日「第二次東禅寺事件」)、薩摩藩士によって英国人が斬られました(8月21日「(横浜)生麦事件」)。高杉晋作(23歳)、
「英国公使館焼討ち事件」の17日後の12月29日(文久2年。1862年)には、高杉や久坂とも交流があった土佐の坂本龍馬(26歳)が、江戸氷川の勝 海舟(39歳)を訪ね、話によっては勝を斬るつもりだったようです。1年とんで
薩摩と長州は、文久3年(1863年)の「薩英戦争」、元治元年(1864年)のフランス、米国、英国、オランダによる「下関攻撃」で西洋の軍事力を目の当たりにして、攘夷を引っ込めますが、かといって幕府に協力しません。幕府と一体になって事に当たろうとした皇室にも協力しませんでした。彼らは、もはや、攘夷でも尊皇でもなく、攘夷と尊皇を利用する倒幕勢力。
久坂は「蛤御門の変」で自刃(1864年。24歳)。幕府と一緒にやろうとした孝明天皇も倒幕勢力にとっては邪魔もので、慶応2年12月25日(1867年。35歳)亡きものにされました(異説あり)。高杉は慶応3年(1867年。27歳)、結核で死去します。
高杉や久坂の師匠・吉田松陰は「安政の大獄」の余波で死に追いやられますが(安政6年(1859年)死去。29歳)、松陰が密航に成功し、米国から何がしかを学び、成功の見込みのない攘夷は脇に置き、幕府側の海舟や象山に協力したならば(本当に国のことを思うのならできたはず)、久坂も高杉も伊藤も井上も過激な攘夷に走らず、幕府は存続し、のちに自然な形で解体し、平和
明治になって開国派に転向した倒幕勢力は、攘夷を捨てない彦斎のような人たちが邪魔になります。暗殺事件の嫌疑がかけられ、 明治4年、彦斎は斬首されました。再び攘夷の機運が高まる昭和初年(昭和2年)、有志によって当地(東京都大田区)の本門寺に彦斎の碑が建てられました(Photo→)。碑文を同じく熊本出身の徳富蘇峰が書いています(Photo→)。
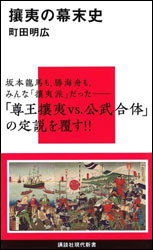 |
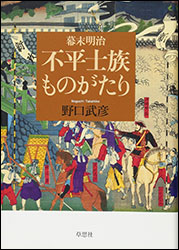 |
| 町田明広『攘夷の幕末史 (講談社現代新書)』 | 野口武彦『幕末明治 不平士族ものがたり』(草思社) |
 |
 |
| 『城下の人 〜新編・ |
島崎藤村『夜明け前(岩波文庫)』。幕末に国学に自らの道を見出した男は、明治になって政府の手のひら返しの政策に絶望、発狂、座敷牢で死にゆく。藤村の父親がモデルだ。神奈川県湯河原で藤村は小説の想が練ったという |
■ 馬込文学マラソン:
・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
■ 参考文献:
●『明治大正史(上)』(中村
※当ページの最終修正年月日
2024.10.24