| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
人力車はこんな山道にも入り込めたのですね。 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:「人力車に乗る女性たち(13)」(撮影:A. ファルサーリ) (長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真データベース→)
明治3年3月22日(1870年。
、
利便性が大いに受け、人力車は、2年後の明治5年に2万台以上となり、5年後の明治8年には全国で11万4,000台にまで増えました。反対に、「
当地(東京都大田区)でも、明治9年、大森駅(東京都大田区大森北一丁目6-16 Map→)ができると、駅前に人力車が着けるようになりました。
大森貝塚の発見者として知られるモースは、明治10年を皮切りに、3度来日しましたが、日本の様々な習俗にも興味を持ちました。人力車にも並々ならぬ関心を寄せ、息子や教え子を乗せた人力車を自分で引いて官舎内を走り回わり、周りを呆れさせたこともあったようですね(笑)。
・・・ホテルの角には、人力車が数台並んで客を待っていたが、我々が出て行くや否や、彼等は「人力車?」と叫んだ。我々は明瞭に要らぬことを表示したが、それにもかかわらず二人我々について来た。 我々が立ち止ると彼等も立ち止る。我々が小さな店をのぞき込んで、何をか見て微笑すると、彼等もまた微笑するのであった。私は彼等がこんなに遠くまでついて来る忍耐力に驚いた。・・・(中略)・・・しかし彼等は我々よりも、やがて何が起るかをよく知っていた。歩き廻っているうちにくたびれてしまうばかりでなく、路に迷いもするということである。果してこの通りのことが起った。・・・(モース『日本その日その日』より)
非常事態だと人力車の需要が高まり、人力車夫は臨時料金で荒稼ぎしたようです。明治11年に起きた「竹橋事件」(近衛兵が明治天皇への嘆願を目的に蜂起)の時も避難民の多くが利用したようです。サラリーマンの月給が30円の時代に、車夫たちは一日に15円も稼いだそうです。長屋の稼ぎ頭で、彼らは仕事を終えると、長屋の人たちに手みやげの寿司やうなぎの折り詰めを用意したとか、粋ですね〜。
それなりにお金のかかる人力車ですから、見栄を張る時にも使われました。昭和の初め、当地(東京都大田区馬込あたり)に文士村の雰囲気が濃厚だった頃、「人力車行列未遂事件」というのがありましたし、宇野千代は初めて原稿料の大枚が手に入った時、郷里の岩国に電報を打って、到着時間を知らせ、岩国駅前に迎えに来た弟妹5人をそれぞれ人力車に乗せ、自分も乗って、車6台を連ねて郷里に錦を飾っています。「お
人力車を日頃の
 |
 |
| 大森駅前に着ける人力車。現在の駅西口でタクシーが着けている辺りだろう(大正8年発表の石井
|
梅の名所「梅屋敷」の茶屋前に停まる人力車。奥にも2台見える。大森駅からのものだろうか。それともお抱えのものか ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『大田区史(下)』(東京都大田区) |
上左の版画が発表された大正8年、芥川龍之介(27歳)が『魔術』を脱稿してますが、その冒頭で、主人公の「私」が人力車に乗ります。大森駅から乗った人力車なのではないでしょうか。
ある
この大正8年は、当地の人力車にとって大きな分岐となる年ともなりました。大森駅〜本門寺間を「乗合馬車(駅馬車)」が初めて走ったのです(旧東海道では、明治初頭より、外国人馬車や「乗合馬車」(横浜・東京間)が走っていた)。49年(およそ50年)して人力車の強敵が現われたのです。
さらに11年(およそ10年)後の昭和5年(1930年)には、「バス」(乗合自動車。池上電鉄)も登場し、「乗合馬車」にとって代わっていきました。その頃を境に、人力車の衰退が顕著になります。大森駅で客待ちしている人力車は門寺への参拝客をバスに取られることとなり、死活問題となりました。バス開通の1年前(昭和4年)、乗合馬車の業者は買収されて早々に撤退しましたが、人力車夫はあくまで抵抗し、大森郵便局(東京都大田区山王三丁目9-13 Map→)の隣にあった大型電気店「内外無線」があったあたりに立てこもって赤旗を立てたそうです。そして、バスの開通日 (昭和5年8月17日)には、 人力車を一斉に出して池上通りに並べて座り込みました。しかし、道路交通妨害罪でことごとく捕まってしまいます。母がたの祖父が当地で人力車夫をしていた作家の小関智弘さんが、そこらへんの経緯を『大森界隈職人往来』(Amazon→)に書いています。昭和17年に徴兵されるまで当地に住んでいた俳優の池部 良もエッセイ『風が吹いたら』(Amazon→)で、この座り込みに触れています。大事件だったのでしょうね。
衰退の一途を辿った人力車ですが、戦後もしばらくは開業医や花柳界の人や著名人などには利用されたようです。大森駅に着けていた人力車夫の橋本 昇さんは、当地(東京都大田区山王一丁目)に家があった芦田 均のことも乗せたことがありました。芦田は気さくに声をかけてくれたそうです。昭和21年、日本国憲法成立時に重要な役割を果たした芦田に、その公布の日、天皇から署名入りの写真が下賜されますが、芦田はその写真を大事に抱えて大森駅から人力車に乗って自宅に向かいました。
 |
 |
| 一番有名な人力車夫だろうか。左が |
映画「無法松の一生」(Amazon→)の一場面。気弱な少年が人力車夫との交流の中でたくましく成長してゆく。左:阪東妻三郎、右:沢村アキヲ(長門裕之)。少年の母役の園井恵子は映画公開2年後に広島で被曝し死去した ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:私の中の見えない炎/山田太一×荒井晴彦トークショー レポート・『無法松の一生』(1)→ |
------------------------------------------------------
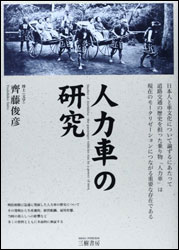 |
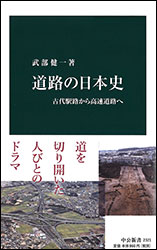 |
| 齊藤俊彦『人力車の研究』(三樹書房)。人力車をになったのは誰か? 人力車で長距離旅行は可能だったか? 戦後に人力車が復活した理由は? | 武部健一『道路の日本史 〜 古代駅路から高速道路へ〜 (中公新書)』 |
 |
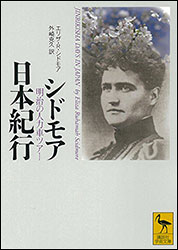 |
| 斉藤俊彦『くるまたちの社会史 〜人力車から自動車まで〜 (中公新書)』 | エリザ・R・シドモア『シドモア日本紀行 〜明治の人力車ツアー〜 (講談社学術文庫)』。訳:外崎克久 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
・ 宇野千代の『色ざんげ』を読む→
・ 片山広子の『翡翠』を読む→
・ 小関智弘『大森界隈職人往来』を読む→
・ 池部 良の『風が吹いたら』を読む→
■ 参考文献:
●「公文書にみる発明のチカラ/特許制度の創設へ/人力車の発明(和泉要助ほか)」(国立公文書館 site→) ●「東京府下和泉要助外二名ヘ人力車発明ニ付賜金」※国立公文書館/『太政類典 第二編(明治4年~明治10年(第百六十四巻)→ ●『乗り物でさぐる日本史(おもしろ日本史入門)』(監修:板倉聖宣、著:長岡 清 国土社 平成5年発行)P.28-30 ●『私たちのモース』(平成2年発行 東京都大田区)P.23 ●『火はわが胸中にあり〜忘れられた近衛兵士の反乱 竹橋事件〜(岩波現代文庫)』(澤地久枝 平成20年発行)P.296 ●『馬込文士村』(榊山 潤 東都書房 昭和45年発行)P.37-46 ●『生きて行く私(中公文庫)』(宇野千代 平成4年発行)P.112-114 ●『大田区史年表』(監修:新倉善之 東京都大田区 昭和54年発行)P.442、P.454 ●「鉄道開設前夜」(川越三千雄)※『大田区史(下)』(東京都大田区 平成8年発行)P.42 ●『大森界隈 職人往来』(小関智弘 朝日新聞社 昭和56年初版発行 昭和56年3刷参照)P.40-43 ●『風が吹いたら』(池部 良 文藝春秋 昭和62年初版発行 平成8年発行8刷参照)P.68 ●『最後のリベラリスト・芦田 均』(宮野 澄 文藝春秋社 昭和62年発行)P.239-244
※当ページの最終修正年月日
2024.3.22