








(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
職人にも生きる「場」があり、場には「歴史」もある。その「場」と「歴史」を描くことを抜きに職人を描くことはできまい。著者(小関氏)は当地(東京都大田区大森)の魚屋に生まれ、高校卒業後は当地の町工場に就職、その後70歳近くまで旋盤工として現場に身をおいて、職人の世界を肌で感じ、自らも体現。つぶさに見てきた当地の「歴史」も作品に織り交ぜている。
小関氏が12歳の時、戦争が終わった。当地にある羽田飛行場では、GHQが同港拡張のために、羽田の3つの町(羽田鈴木町、羽田穴守町、羽田江戸見町)の約1,200世帯3,000人に対して、48時間以内に退去するよう命じた。「戦争に負けたのだからしようがない」と言えばそれまでだが、今や華やかかりし羽田空港。それが、元住人の多大な犠牲の上に成り立っているのを忘れてはならない、と同書は訴える。視点は常に、庶民の側にある。
小関氏が高校卒業後、町工場に就職したのは、自然な成り行きだった。
工業地帯の拡大によって、日本一と謳われた当地の海苔養殖業は追いやられ、また、アジア太平洋戦争の末期には、軍需を支える地域として当地は標的となって大規模な空襲を受けることともなる(昭和20年、小関氏の家も工場の設備を整えたが、試運転の日の空襲で焼けた)。しかし、敗戦後5年して(昭和25年)、朝鮮戦争が起こると、今度は米国からの軍需が高まって、当地の工場は息を吹き返す。小関氏が、就職したのはその頃だ。
町工場を転々としながら、小関氏は、生涯の“師匠”と出会う。“師匠”たちは、本気で取り組む者には仕事の真髄をそっと教えるのだろう。
最初の工場(工場主と旋盤工が3人の小さな工場だった)で小関氏は、工場主の北村さんから、2人の職人が仕上げた製品の違いを問われる。どちらも、同じ鉄を削り、同じ旋盤を使って、規定通りにきれいに仕上がっている。しかし、どこかが違う、それは分かる。でも、どう違うかを説明できない。北村さんは言う。
「そうなんだ。どっちもきれいに仕上がっている。たしかにそうなんだが、岡本のはきれいなだけなんだ。そこいくと、岸田のほうのは、品物が生きて立っている。そこがちがうんだ」
仕上がった製品が「生きて立っている」とはどういうことなのか? リヤカーを引きながら北村さんは言う。
「(岡本のは)ピカピカの塊りだ。それに較べると、岸田のは、メリハリがついている。必要でないところは鈍く光っている。艶が鈍いとは送りが荒いからだが、その分だけ仕事は速い。それなのに品物は生き生きとしている。必要のないところが光っていないから、必要なところがそのぶんだけよりきれいにひき立って見える」
この箇所を読んで、思わず唸ってしまった。この秘訣は、生活のあらゆる場面で応用できそうだ。「本物」を見分ける一つの物差しともなろう。
小関氏は、51年間、旋盤工であり続け、かつ、文筆の筆も取った。この『大森界隈職人往来』も、バリバリ現役時代の作品だ。
現場を外からでなく内側から描いているのも本書の特徴。
たとえば、公害問題。公害を外から告発した本はたくさんあるだろうが、この本は違う。当地の発展に貢献してきた町工場だが、近隣に住宅が建て込むことによって、騒音の苦情を受けるようになり、そして、町を追われていく工場・・・。告発される側(工場側)の苦悩にも言及される。
『大森界隈職人往来』 について
昭和56年に書かれた小関智弘(48歳)のノンフィクション作品。朝日新聞社から出版された。 第8回日本ノンフィクション賞を受賞。
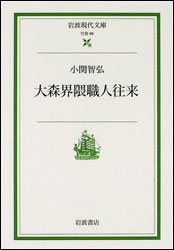 |
| 小関智弘『大森界隈職人往来 (岩波現代文庫)』 |
小関智弘氏について
当地(東京都大田区)で生まれる
昭和8年(多喜二が死んだ年)、当地(東京都大田区)で生まれる。7人兄弟姉妹の5番目だが、上の3人が早死したため次男として育つ。家は「入新井第一小学校」(東京都大田区大森北四丁目6-7 Map→)の横で魚屋(「魚信(うおのぶ)」)をやっていた。一家が埼玉県
空襲で家を焼かれ、極度の貧困も体験。
旋盤工と作家の二足のわらじ
「(都立大学付属)工業高等学校」普通科に在籍。文芸部に所属して小説やエッセイを書くようになる。ロマン・ローラン、マルクス、中野重治、
近所の工場労働者、設計屋、営業マン、商店員、主婦などと文学サークルを作り、手書きの同人誌「塩分」(肉体労働に欠かせない塩から)を発行。毎月1冊の本を皆で読み、語り合う読書会も持ち、現在に到る(平成27年現在)。
「赤旗」(日本共産党の機関誌)の配達をしている頃、配達先だった泡盛屋「河童亭」を知り、常連となる。河童亭に置いてもらった同人誌「塩分」(4号)に掲載された『ファンキー・ジャズ・デモ』(六十年安保闘争の体験が題材)を、店の常連の文芸評論家・久保田正文が認め、彼の手で「新日本文学」に掲載された。野間 宏が16枚にもわたる批評を書き、作家として認められ始める。
河童亭の常連・
当地(東京都大田区)を舞台にした『
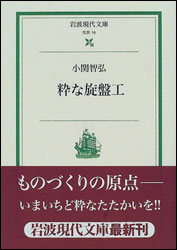 |
 |
| 小関智弘『粋な旋盤工 (岩波現代文庫)』 | 小関智弘『どっこい大田の工匠たち 〜町工場の最前線〜』(現代書館) |
参考文献
●『大森界隈職人往来』(小関智弘 朝日新聞社 昭和56年発行 昭和56年発行3刷)P.10-12、P.29、P.32-34、P.37、P.45、P.66、P.72-73、P.94-95 ●「大田の町工場 伝統と底力(私だけの東京)」(小関智弘 聞き手:小林祥晃)※「毎日新聞(朝刊)」(平成27年10月14日号)に掲載 ●『羽田浦地図<新装版>』(小関智弘 現代書館 平成15年発行)P.41-152 ●「河童亭開店のころ」(小関智弘)※「わが町あれこれ 第2号」(編・発行:城戸 昇 あれこれ社 平成6年発行)に収録 ●「いつもそばに本が(上・中・下)」(小関智弘)※「朝日新聞(朝刊)」(平成15年3月16日〜30日)に掲載 ●「小関智弘『祀る町』 〜大田区・大森北周辺〜(東京物語散歩)」(堀越正光)※「朝日新聞(朝刊)」(平成21年6月10日号)に掲載
※当ページの最終修正年月日
2025.4.21