| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
昭和35年6月30日(1960年。 泡盛屋「河童亭」(「きらぼし銀行」(東京都大田区中央一丁目7-1 Map→)の駐車場あたりにあった)の主人・かのう・すすむ(49歳)が、日記に次のように書いています。
曇。 午後二時室内気温二十九度。 蒸暑。
芭蕉の“おくの細道”読了。
「(芭蕉の)紀行文の五つ」は俳句を志す人がよく読むものなのでしょうね。
 |
かのうは高浜虚子門下の松野
雲間草(元は高山植物)は、“雲の間”の清新なイメージ。遠くなった青春が一瞬よぎり、山肌を流れる雲のようにまた流れ去っていく感じ。
「河童亭」の近くで古書店「山王書房」をやっていた関口良雄(銀杏子)も、この花を愛し、
眠る間も花咲きをるよ雲間草(銀杏子)
と詠んでいます。病いが篤くなってきた頃のもののようです。自分が眠っている間も、そこにそっと咲く雲間草。自らの不在と、時の永遠を思ったのでしょうか。
句会では、季題が示されそれを折り込んだ句を競うといったゲーム的お楽しみもあります(題詠)。「河童亭」界隈のある句会で、雲間草が季題になったのかもしれませんね。「河童亭」の開店が昭和29年で、「山王書房」はその1年前の昭和28年の開店です。両者の歴史はほぼ軌を一にしており、両者の利用者はかなり重複していたのではないでしょうか。
「河童亭」句壇からは、土田河石、矢島童山、遠藤亭々子という俳人が育ち、それぞれ独立して句誌を主宰するまでになったそうです。上記3名はそれぞれ 「河童亭」から一文字ずつ取っています。「河童亭」の常連には当地(東京都大田区山王三丁目)在住の大牧 広という人もいて、彼も句誌「港」を主宰。次のような佳句を残しています。
大根煮て血のすこしづつ老いてゆく(大牧)
かつては大方の作家が俳句を嗜んだのではないでしょうか。
 |
 |
室生犀星の小説『青い猿』(NDL→)に、犀星、芥川龍之介と思しき人物が、芭蕉や凡兆の句を批評し合う場面があります。言葉が喚起するイメージの大きさや距離が与える効果、形容の斬新さなどを論じ、面白い表現に出会うと、芥川と思しき人物が「喜びのあふれた顔いろ」になって飛びついてくる、と犀星と思しき人物がちょっと冷めた目で見ています。
芥川が死の直前に自選した一句は、
水洟が出ぱっなしの鼻に意識があり、その部分だけが暮れ切らない面白さ。物理的にも鼻は顔の中で出っ張っているので暮れ残っているような気がするのかも。俳句評論で活躍されている松王かをりさんは、『鼻』で文壇に出てきた芥川は(帝大在学中、短編小説『鼻』で夏目漱石に認められた)、文学人生を「鼻」で閉じたかったのではないかと書いています。
かつて「大森テニスコート」(現「大森テニスクラブ・テニススクール」(東京都大田区山王二丁目24-12 Map→))の経営者だった西村月杖は句誌「句帖」を主宰。次の句があります。
銃剣とこれの握力 立つ
と、もろ国粋的で、銃剣を向ける相手にも血が流れ涙も流れ家族もいるとは全く思い至らないのでしょうね。昭和11年6月に発表された句で、二・二六事件の3ヶ月後。その頃の国民の意識の一端が表れています。
 |
 |
かたやその頃、やはり当地(「イトーヨーカドー(大森店)」(東京都大田区大森北二丁目13-1 Map→)の近く)にいた俳人・
機関銃
当地には、高浜虚子から「花鳥諷詠真骨頂」と賞された川端
歯医者だった三鬼は患者から句会をすすめられて俳句の道に入り、茅舎も岸田劉生と句会を冷やかしている内にそれが専門になりました。そういった敷居の低さと、17文字に研ぎ澄ましていく難しさとが俳句にはありますね。
戦争も末期の昭和19年より、当地(東京都大田区東馬込二丁目)にいた添田知道を中心に、月に一回、「まごめ句会」が開かれます。ひもじく、惨めな日々を一時でも楽しく過ごそうと催され、南川 潤、尾﨑士郎、山本周五郎、榊山 潤、今井達夫、高木
空襲に
苔の花踏んで仏に近づけり(高木 護)
即興で句をひねり、それを
武士も俳句を嗜みました。討ち入りで有名な赤穂浪士にも詠む人が結構いて、大石内蔵助は可笑、小野寺十内は里龍、岡野金右衛門は放水、と俳号まで持っていました。討ち入り2日前の12月13日、
年の瀬や水の流れと人の身は
源五がついだ句は、
あしたまたるるその宝船
その「宝船」の意味を解さなかった不明を恥じた其角は、討ち入り後の浪士たちの行列を追って源五に詫びたといいます。
平成28年の「俳句甲子園」で印象に残ったのが東京家政学院が詠んだ下の2句。
利口な
詩篇には水爆忌なし
若い俳人がどんどん出てきますね。
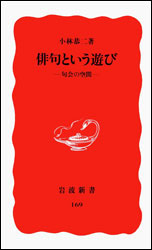 |
 |
| 小林恭二 『俳句という遊び 〜句会の空間〜 (岩波新書)』 | 髙柳克弘『究極の俳句 (中公選書)』。常識への抵抗と、価値の創造 |
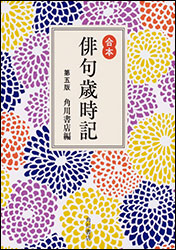 |
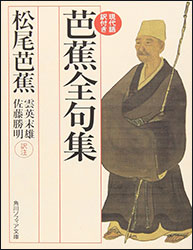 |
| 『俳句歳時記(合本)(第五版)』。編:角川書店 | 『芭蕉全句集(現代語訳付き)(角川ソフィア文庫)』 |
■ 馬込文学マラソン :
・ 関口良雄の『昔日の客』を読む→
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
・ 南川 潤の『風俗十日』を読む→
・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→
・ 山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→
・ 榊山 潤の『馬込文士村』を読む→
■ 参考文献:
●「わが町あれこれ」( 編集・発行:城戸 昇 あれこれ社 平成6年発行)第1号 P.7-10、第2号 P.22-23、第3号 P.40、P.52 ●『関口良雄さんを憶う』(夏葉社 平成23年発行)P.42-44 ●『忠臣蔵99の謎(PHP文庫)』(立石 優 平成10年発行)P.80-81、P.186-189 ●「開成9度目Vの俳句甲子園 強豪に個性で健闘 家政学院「自由でアナーキー」」(川原田喜子)※「東京新聞(夕刊)」平成28年9月2日号掲載 ●「室生犀星の句」(増殖する俳句歳時記→) ●「<水涕や鼻の先だけ暮れ残る>芥川龍之介」(松王かをり)(現代俳句協会→)
※当ページの最終修正年月日
2023.6.30