| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
慶長元年4月26日(1596年。
。「関ヶ原の戦い」の4年前)、当地の本門寺(東京都大田区池上一丁目1 Map→)(32歳という若さで本門寺の第12世に就任した
印刷やコピーが普及するまでは、複製と言えば「書き写す」のが主流だったことでしょう。
印刷の起源は、印刷の定義によって異なりますが、紙に写すことに限定しなければ、紀元前3,000年頃(日本では縄文時代の前期から中期)、メソポタミアやエジプトで、円筒状の岩に絵や文字を刻み、それを粘土の板に転がして転写することが行われていました。
 |
蔡 倫 |
紙の
610年(飛鳥時代)、高句麗の
770年(奈良時代)に印刷された「
印刷が行われるようになったとはいえ、江戸時代までは宗教的な特殊な場合に限られ、文書(
江戸時代になると木版印刷が発達し、商業出版が盛んになって出版の時代を迎えます。井原西鶴の『好色五人女』などの浮世草紙も木版印刷され出版されました。
明治になって活版(活字を並べて印刷する方式)が導入され、印刷がより一般的になります(江戸時代以前もイエズス会の宣教師がもたらした活版印刷機によって印刷された「キリシタン版」があった)。
それでも書き写すことが廃れたわけではありません。
嘉永元年頃(1848年頃)、勝 海舟(25歳頃)が赤城玄意という蘭医から和蘭辞書「ドゥーフ・ハルマ」を1年間10両(現在の120~130万円ほどか)で借りて、2部書き写し、1部は売って借金の返済にあて、1部は自分が使用したという話が伝わっていますが、話の出どころはどこでしょう? 5万語ほど収録されていて58巻あったという「ドゥーフ・ハルマ」を1年で2部書き写すなんてことが実際可能でしょうか? それに、海舟が書き写したという 「ドゥーフ・ハルマ」は今どこにあるでしょう? 出来過ぎた話のような気がします。
江戸後期に緒方洪庵が開いた蘭学の私塾「適塾」(大阪大学の前身とされる)といえども、所有している「ドゥーフ・ハルマ」は1冊のみで、福沢諭吉ら塾生はそれを書き写して利用したそうです。大名などから依頼される「ドゥーフ・ハルマ」の写本づくりが塾生のいいアルバイトになったとか。
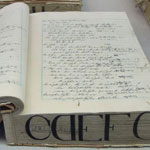 |
「ドゥーフ・ハルマ」の一巻 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 撮影:Babi Hijau 出典 : ウィキペディア/ドゥーフ・ハルマ(平成26年4月5日更新版)→ |
南方熊楠は幼い頃から凄まじい勢いで写本を作っています。写本づくりは、知識を吸収する学習方法でもあったのでしょうね。
昭和30年、北アルプス前穂高岳での「ナイロンザイル切断事件」(井上 靖の小説『氷壁』の題材になった)が起きますが、遭難者を出した山岳会「岩稜会」は、間違った世評を正すために急遽、遭難の報告書を作り、新聞社などに配布しています。原本をメンバーで手分けして7部書き写したようです。謄写版などはあったのでしょうが、10円入れれば複製がスーと出てくるようなコピー機などはなく、急ぎの場合などはまだまだ書き写すことが多かったのでしょうね。
書き写す行為は、写経などもそうですが、精神修養の一貫としても行われます。
当地(東京都大田区)に住んだ
臨書には、
形臨は全く原本どおり形だけに重点をおいて書くこと。意臨は文字の形にこだわらず、古筆の精神を習う方法で、臨書としては比較的上級のものです。背臨は手本の文字や、感じをよく呼吸し、手本は背後におき、個性を生かし、時代の感覚を表わし、古筆の匂いを豊かに表現する、臨書の最上級のものと言えます。(熊谷恒子「臨書の心得」より)
コピーや印刷の技術が進歩し、学ぼうとする者、情報を多方面に伝えたい者には恵まれた時代になりました。しかし反面、簡単に写せる知識や情報が“軽いもの”になり、偽物も増えたようです。便利になることで失われるものがあることを心したい。
 |
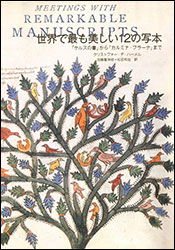 |
| 『萬葉写本学入門(上代文学研究法セミナー)』(笠間書院)。編集:小川靖彦。「本物の万葉集」に近づくための試み | クリストファー・デ・ハーメル他『世界で最も美しい12の写本 〜『ケルズの書』から『カルミナ・ブラーナ」まで〜』(青土社) |
 |
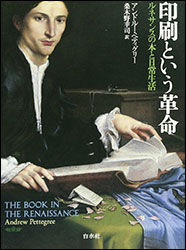 |
| 植村和堂『写経のレッスン』(二玄社)。お経の精神に触れ、字も習い、心も整う | アンドルー・ペティグリー 『印刷という革命 〜ルネサンスの本と日常生活〜(新装版) 』(白水社)。訳:桑木野幸司 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 川口松太郎の『日蓮』を読む→
・ 子母沢 寛の『勝 海舟』を読む→
・ 井上 靖の『氷壁』を読む→
■ 参考文献:
●『大田区史年表』(監修:新倉善之 東京都大田区 昭和54年発行)P.217、P.469 ● 「兄弟抄」(田中本隆)※『池上本門寺』(日本美術社 昭和41年発行)P.192 ●「印刷」(山本隆太郎・中村 幹)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に収録(コトバンク→) ●「羊皮紙」 ※「世界大百科事典」(平凡社)に収録(コトバンク→) ●「ドゥーフ・ハルマ」※「世界大百科事典」(平凡社)に収録(コトバンク→) ●『氷壁・ナイロンザイル事件の真実』(石岡繁雄、相田武男 あるむ 平成21年発行)P.48-52 ●『書道 かな 〜基礎から創作まで〜』(熊谷恒子 マコー社 昭和53年発行)P.110
※当ページの最終修正年月日
2024.4.25