








(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
『昭和初年のインテリ作家』には表題作の他にも6編の短編が収録されているのに、表題作と、あと一、二編ちょろっと読んだきりで、一冊まるまる読んだ気になっていた。著者・広津和郎の偉大さ(後述)が少しは分かってきたので、今回10年以上ぶりに、彼の作品をこの一冊だけでもきちんと読んでみようという気になった。
最初の話では、第一次世界大戦の大戦景気でぼろ儲けして12部屋ある家に住みお手伝いさんを3人と書生を1人置くほど羽振りの良かった男が、戦後の不景気と関東大震災で会社を潰し、どんどん没落していく。ご自慢の妻も逃げ、新しく始めた仕事で奔走する自身の地味な姿を、前の彼を知る人に見られないかビクビクしているのだった。そんな彼なのだが、かつての彼よりも、ひょっとしたら幸せなのかも?
次の話には、父の世話に明け暮れる娘さんが出てくる。神経質な父が眠るとやっと自分の時間。ホッとしていると、夜中の決まった時刻に、自室の窓の下を気持ち良さそうに吹く口笛が通り過ぎていく。彼女は、外界の空気を漂わすこの口笛に心を踊らせ、口笛を吹く人は好ましい青年に違いないと想像を膨らますのだった・・・。
さらなる話では、惚れやすい女が次々と男に惚れ、彼らの子を次々に孕み、カラッと子どもをもらわれていくのだった。ところが、最後のケースは違う。なぜか、彼女が涙を流す。
上記3話には、クスッと笑わせたり、ホロっとさせるオチがあるが、4話目は違う。愛する夫が事故で働けなくなり、家賃を払うため、米を買うため、夫の薬を買うため、夫を転地療養させるためにと、妻は体を売って金を稼ぐようになる。最初は躊躇しながらだったが、こだわりがどんどんなくなり、積極的にもなっていく。こうなった場合、果たして、夫への愛は保ち得るものだろうか? 最後、ズドンと来る。
このあと2話、謎めいた話が続き、そして、最後が、表題作の「昭和初年のインテリ作家たち」だ。本のタイトルにしているのだから、一番打ち出したかった小説だろう。
昭和初期の当地(東京都大田区馬込)の作家たちのことが書かれている。巻末に解説と言える「文士の生活を
この小説には2本柱があり、1つは、出版界に幅を利かせてきた売れてなんぼの風潮(コマーシャリズム、大資本主義)によって隅に追いやられつつある純文学の状況で、もう1つは、当地を沸かせた須永夫人の行動を巡る風聞。広津は北川の口を借りて、双方に批判を加える。
北川は、出版社の大資本主義から作家たちの独自性を守るために、作家たちからなる芸術協会の力を強めて出版社に交渉することを作家たちに訴える。が、作家たちは、金づるである出版社に意見することをためらい、北川に同意しない。彼らの自分だけよければいいという態度に、特権意識と嫉妬心が表れているのだった。
また、須永夫人の行動(宇野千代が湯ヶ島で梶井基次郎と親しくなったことを指す)に尾ひれがついて、当地で「須永夫人が一番悪党」「須永が気の毒」という話になって広がっていく。事実を確かめもしないで須永夫人にお冠の白井に須永は反論。実際にもこの件で、広津は朔太郎を
様々な人の様々な事情に心を寄せるだけでなく、その現実的な成り行きを見届けようとする著者の冷徹な視線も感じられる作品たちだった。
『昭和初年のインテリ作家』について
 |
昭和9年、改造社から発行された広津和郎(43歳)の作品集。 「過去」「口笛と犬」「訓練されたる人情」「落葉」「何が彼女を怒らせたか」「うしろすがた」「昭和初年のインテリ作家」「文士の生活を嗤ふ」を収録
広津和郎について
 |
| 広津和郎 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『昭和文学アルバム(1)』(新潮社) |
多額の負債を、円本の印税で返済
明治24年12月5日(1891年)、東京牛込で生まれる。 父親は永井荷風が弟子入りを申し込むほどの小説家・広津柳浪。泉 鏡花や尾崎紅葉が身近にいた。
麻布中時代から書き始め、早稲田大学在学中からは翻訳で稼ぐ。大正元年(21歳)、葛西善蔵らと同人誌「奇蹟」を創刊。卒業後、評論などを書く。大正6年(26歳)、『神経病時代』で認められた。大正12年(32歳)、『武者小路実篤全集』の出版を目的に「芸術社」を興すが、極端に凝った造本にしたため採算が合わず失敗。
周りからの信望があり、女性関係も複雑
大正15年(35歳)、銀座の「カフェー・タイガー」のナンバーワン給仕・松沢はまと当地(東京都大田区南馬込二丁目22-3 Map→)に新居を構えた(広津とはま(Photo→))。当地(東京都大田区山王四丁目2 Map→)にはすでに父親の柳浪(65歳)が住んでおり、その近くに住むことが大きな目的だった(柳浪は昭和3年に死去)。「芸術社」で抱えた負債を返済する目的で「大森書房」を設立するが( 昭和4年、38歳)、それも失敗。多額の負債を負う。しかし、その後の「円本ブーム」の波に乗って無事返済することができた。当地では、麻雀、絵画(二科展に入賞する腕前)、魚釣り、キャッチボール、ダベリングの毎日だったが、菊富士ホテルを仕事場にして相当数の作品も残す。昭和5年(39歳)、世田谷に転居。 当地にいたのは4~5年ほどか。
散文精神を生きる
生活にもっとも緊密な関係にある芸術として散文(韻律や定型にこだわらない文書全般。小説を含む)を評価し、現実に即し、主情(主観)に流されない態度を「散文精神」と命名、それをモットーにした。大正15年に発表した『さまよへる琉球人』に対する抗議への態度や、昭和2年の葛西善蔵の死に臨んでの態度や、 昭和24年の「松川事件」への関わりや、昭和26年(60歳)のカミュの『異邦人』 を巡っての論争などにも、彼の散文精神が発揮されているとみていいだろう。おかしいと思うことはおかしいというし(なあなあにしない)、自分が間違っていると思えばそれもはっきりと認めるのも散文精神なのだろう。
昭和43年9月21日(1968年)、76歳で死去する。墓所は谷中霊園(東京都台東区谷中七丁目5-24 Map→)( )。
■ 広津和郎 評
・ 「無私にして柔軟」(平野 謙)
・ 「数字がわかっているくせに、このくらい数字を超越している人はいない」(尾﨑士郎)
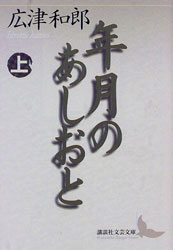 |
 |
| 広津和郎 『年月のあしおと〈上〉 (講談社文芸文庫)』。自伝的文壇回想録 | 松原新一『怠惰の逆説 ~広津和郎の人生と文学~』(講談社) |
参考文献
●「広津和郎」(平野 謙)※『新潮 日本文学小辞典』(昭和43年初版発行 昭和51年発行6版)に収録 ● 『昭和初年のインテリ作家』(広津和郎 改造社 昭和9年発行)P.249 ● 『広津和郎 この人との五十年』(間宮茂輔 理論社 昭和44年発行) P.82-105 ● 『さまよへる琉球人』(広津和郎 解説:仲程昌徳 同時代社 平成6年発行)P.137-139 ● 『馬込文学地図(文壇資料 )』(近藤富枝 講談社 昭和51年発行) P.34-44 ● 『本郷菊富士ホテル(中公文庫)』 (近藤富枝 昭和58年初版発行 平成10年発行4刷)P.157-163 ● 『座談会 昭和文学史 (一)』(編:井上ひさし、小森陽一 集英社 平成15年発行)P.56-66、P.492 ● 『馬込文士村ガイドブック(改訂版)』(編・発行:東京都大田区立郷土博物館 平成8年発行)P.57-59
※当ページの最終修正年月日
2025.4.22