| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和45年8月16日(1970年。 広津和郎(没後2年)の小説『さまよへる琉球人』が沖縄側の要請で復刊されたことを、「沖縄タイムス」が報じました。『さまよへる琉球人』はかつて沖縄側から批判され、広津自身が封印した作品です。
『さまよへる琉球人』は、44年前の大正15年「中央公論」に発表されました(広津34歳)。発表後、沖縄の産業団体「沖縄青年同盟」が、沖縄県人に対する偏見を助長するとして、「報知新聞」の「紙上会議」で抗議したのでした。
私小説的手法で書かれたもので、東京で下宿している「自分」(広津と
この小説で広津はつけこまれる隙だらけの「自分」を自虐的に書き、「彼」を好意的に書いたつもりでしたが、少々違う読まれ方をしたのです。
「沖縄青年同盟」は、「本県民の窮状に同情ある観察をなされた事」には感謝しつつも、題名にわざわざ「琉球人」と書く必要があるのか、それが沖縄県人全体に対する偏見を助長するのではないかと問いました。
以下は、それに対する広津の返答です。
拙作「さまよへる琉球人」に対する御抗議文拝読、あの小説が現実的な意味であなた方には多大な御迷惑をかけようとは、小生の予想せざるところでした、小生は貴県人に対して厚意と友情とを持ちこそすれ、決して貴県人から誤解されることを喜ぶものではありません。あなた方の御抗議文を拝読して、今更のやうにそこまで思ひ及ばなかつた小生の不明を恥ぢ、取返しのつかぬことをしたといふ自責の念に悩まされます。・・・(中略)・・・・数世紀の昔から不当に苦しめられて居る沖縄県といふものを背景に考へる事によつて、あの作に出てくる二人の沖縄県人のなした行為を出来得る限り善意に解釈したかつたのです。・・・(中略)・・・・しかし、それがあなた方沖縄県人に現実的な御迷惑をかける事からくらべれば、小生があの題をあの小説から撤回する事などは、物の数ではありません──いや、むしろ小生は、あれを中央公論に発表してしまつた今日、中央公論をどうすることも出来ませんが、今後あの作を創作集などには再録しない事をこゝに御約束する事によつてあなた方に現実的な危惧を与へたことをせめて謝したいと思ひます。
自らの不明を恥じ、謝罪し、同作を以後の創作集に入れないことを約しています。
『さまよへる琉球人』は他からも批判されました。──
この件から44年が経ちました。──このいわくある小説『さまよへる琉球人』は、上で触れたように、なんと沖縄県側からの要請で、一冊の本になって復活します。少々時間を要しましたが、「批判」は双方の理解を深め、結果として、相互理解に至ったのでした。双方に、良識と、相手への敬意があってのこと。「論破したぜ」とか言って有頂天になるような人たち(つまりは単細胞=アホ)には、この件に関わった広津や沖縄の人たちの爪の垢でも煎じて飲ませたいですね?
ところで、上の広津の言葉にもある「不当に苦しめられて居る沖縄県」とはどういうことでしょう?──以下で、沖縄の概要と、歴史を
琉球列島(南西諸島)は、1,200Kmにもおよび(本州の長さと同じくらい)、鹿児島の方から台湾の方に向けて、大隅諸島、
発見された象の化石などから、縄文時代以前の氷河期には、琉球列島の島々は、日本本島やアジア大陸(大陸)と地続きだったと推測されています。縄文時代に温暖化して海の水位が上がり、現在のように島状になったようです。日本本島に近いか大陸に近いかで、両者からの影響の度合いが異なりますが、縄文文化の影響もみられ、また、弥生文化の影響が少なく、反対に、南方文化(特にインドネシア文化)の影響を強く受けたという特色があります。
600年代に入り大和朝廷は中国文化の輸入を目的に遣唐使を派遣。琉球列島の島伝いに中国に至る南路をとったため、大和朝廷の影響が沖縄の島々にも及ぶようになっていきました。
広大な領土を誇ったモンゴル人の元朝を、1368年漢民族の明王朝が打ち倒すと、明朝は自国を宗主国と崇める国とだけ貿易しました(
ところが、江戸時代になって、徳川家康が薩摩藩に琉球王国への侵攻を許し、慶長15年(1610年)、琉球王国は薩摩藩に支配されてしまいます。清朝(1644年明朝が滅亡し清朝に)との貿易の実権も薩摩藩が握りました。
その後形だけは琉球王国が存続しますが、明治12年、明治政府は、軍隊と警察権力を使って琉球王国を崩壊させ、強制的に沖縄県を設置(「琉球処分」)。明治政府は清朝からの
アジア太平洋戦争の末期、日本は南洋の島を次々に取られ、本土に激しい空襲を受けるようになり、日本本土での決戦も時間の問題となりました。米国は戦略上の要地・沖縄の占領を優先し、昭和20年3月23日より沖縄を攻撃し始めます(沖縄戦)。日本にとっては初めから全く勝ち目のない戦いで、単に「本土決戦への時間を稼ぐため」だけに戦われました。日本軍におよそ94,000人の死者(沖縄県人の正規部隊・防衛隊・鉄血勤皇隊・従軍看護婦を含む)、沖縄県人にもほぼ同数の94,000人ほどの死者が出ました。集団で自決したり、日本人が日本人を殺したり死に追いやったりという事例が多数ありました。
今も政府は基地を沖縄に集中させ、沖縄に犠牲を強いています。
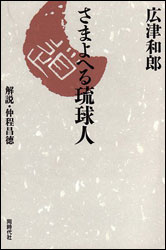 |
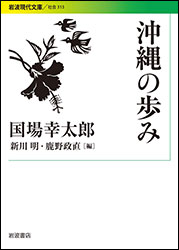 |
| 広津和郎『さまよへる琉球人』(同時代社)。解説: |
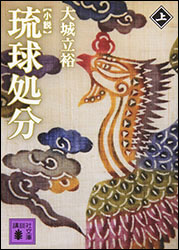 |
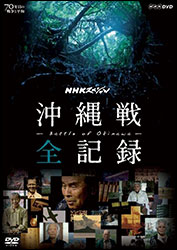 |
| 「沖縄戦 全記録(NHKスペシャル) 」 ●単行本化→ |
■ 馬込文学マラソン:
・ 広津和郎の『昭和初年のインテリ作家』を読む→
■ 参考文献:
●『さまよへる琉球人』(広津和郎 解説:仲程昌徳 同時代社 平成6年発行)P. 96-101、P.104-105、P.120-125 ●『沖縄の歩み(岩波現代文庫)』(国場幸太郎 編:新川 明 鹿野政直 令和元年初版発行 令和4年発行3刷参照)まえがき、P.19-48、P.49-54、P.62-66、P.70-71 ●「琉球処分」(高良倉吉)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)掲載(コトバンク→)
※当ページの最終修正年月日
2025.8.16