| {column0} |

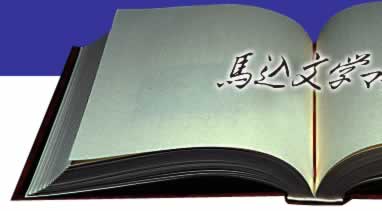







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和26年6月12日(1951年。 広津和郎(59歳)がカミュの小説『異邦人』を、「東京新聞」紙上で批判しました。
 |
カミュ |
カミュの『異邦人』は、戦中の昭和17年(カミュ28歳)に刊行され、日本語訳は戦後6年目の昭和26年の6月に刊行。
きょう、ママンが死んだ。
で始まり、フランス領だった頃のアルジェリアの首都・アルジェ(Map→)に住むムルソーという青年が、同じアパートに住む知り合いのトラブルに巻き込まれ、“偶然”、一人のアラブ人を殺してしまうところで第1部が終了。第2部では、ムルソーが裁かれ、死刑を宣告されるまでが描かれます。
広津にはムルソーの言動の一々が引っかかりました。母親の死に際して、棺の母親の顔を最後に見るかと問われたとき見ないとこたえたこと、母親の年齢を問われても正確に言えなかったこと、通夜の席でミルク入りのコーヒーやたばこを臆面もなく楽しんだこと、葬儀の翌日、海水浴に行って、水の中で再会した恋人(マリイ)と喜劇映画をみて情交までしたこと、マリイが愛しているかと聞いてくると「それは何の意味もないことだが、恐らく愛していないと思われる」とこたえて彼女を悲しませたこと、知り合いの悪事(?)に協力するおりも「別にどうとも思わないが、なかなか面白い話だ」と返答し、きわめつけは、裁判で殺人の動機を尋ねられて「太陽が眩しかったから」とうそぶき、さらには
 |
中村光夫 |
広津のムルソー批判に対し、中村光夫(40歳)は、明治からの西欧の作品をありがたがる日本人の傾向に反発した広津の「精神の健康な弾力」を認めつつも、
・・・氏のムールソオに対する攻撃は、まったく既成道徳の通り一遍の常識をでず、そこらの
かつての「神経病時代」の作者の「神経」も、今ではこういう常識道徳の代弁者になり下ってしまったとしたら、
カミュは、前半でムルソーの「非常識」を撒き散らし、後半ではムルソーを死刑にすることで読者に「だからといって、死刑をないだろう!?」と疑問を持たせることを狙っており、広津はそういった物語運びを「
その後も、論争の場を「群像」(講談社の月間文芸雑誌)に移し、
 |
「『異邦人』論争」といえば広津と中村ですが、広津の最初の批評が発表された昭和26年6月、三島由紀夫(26歳)が「新潮」(6月号)に「「異邦人」を読む」を掲載しています。雑誌は月号数より早く発行されるケースが多いので(変ですね?)、広津の『異邦人』批判より前に書かれたものかもしれません。
三島は『異邦人』を読み解く鍵として、裁判での検事の次の言葉をあげています。
「・・・寛容という消極的な徳は、より容易ではないが、より上位にある正義という徳に姿を変えなければならないのです。とりわけ、この男に見出されるような心の空洞が、社会をも呑みこみかねない一つの深淵となるようなときには・・・」(カミュ『異邦人』より)
「心の空洞」とは虚無的な(虚無的に見える)ありようであり、ムルソーはそれがゆえに裁かれた、と三島は鮮やかに指摘。ムルソーはアラブ人を殺したから死刑になったのではなく、彼の虚無性(そういった人と違った“異邦性”)が憎まれ、死刑になったのだとしました。
『異邦人』を少しよく読むと、ムルソーが、シャイで、外見や職種や人々の評判で人を分け隔てする人でなく、言葉や態度に現れないでも、母親を愛し、恋人(マリイ)も愛し、既成の道徳や宗教や常識にとらわれないで自分の感性を信じ、自然を愛する、新しいタイプの人間であることが浮かび上がってきます。そういった愛すべき人が、どんどん死刑に追い込まれていく恐ろしさ。道徳や宗教や常識が「絶対化」すれば、必ずや暴力が発生するのでしょう。
日本で「『異邦人』論争」のあった6年後の昭和32年、カミュ(44歳)は、史上2番目の若さでノーベル文学賞を受賞しました。
なお、広津は翌年(昭和27年)より、「松川事件」に言及し始め、以後10年以上も判決文に即した裁判批判を展開、被告全員の無罪判決に大きく貢献します。『異邦人』の後半では法廷が描かれます。中村との「『異邦人』論争」が、広津に法廷を意識させ、「松川事件」に向かわせる大きな動機になったに違いありません。
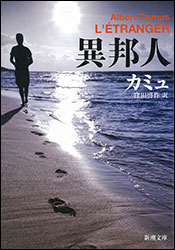 |
 |
| カミュ『異邦人(新潮文庫)』。訳:窪田啓作。ヴィスコンティ監督が映画化しているが、DVD化はまだ? | 中村光夫『異邦人論』(創元社)。広津と中村の「『異邦人』論争」に対する著者カミュのコメントもあり |
 |
 |
| 「アルベール・カミュ」。フランス映画。フランス領だった頃のアルジェリアに生まれたカミュ。貧困と複雑な時代状況が彼の哲学と文学を鍛えていく。祖国フランスへのドイツの侵攻、アルジェリアの独立戦争も体験。融和主義者は双方から攻撃されるのか・・・。彼の女性関係と、それを苦にした妻のうつ病の発症と自殺未遂など私生活の迷いや苦悩も | 久保田早紀『ふたりの異邦人』(いのちのことば社)。大ヒット曲「異邦人」(YouTube→)を作り歌った著者は、芸能界で自分は“異邦人”だったと明かす。現在はキリスト教の音楽宣教師として活躍されているが、そこでも途中から参入した“異邦人”的な感覚を持っておられ、それも受け入れていらっしゃるご様子 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 広津和郎の『昭和初年のインテリ作家』を読む→
・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
■ 参考文献:
●『戦後文学論争(下)』 (監修:臼井吉見 番町書房 昭和47年発行)P.13-20、P.61-62 ●『三島由紀夫のフランス文学講座』(筑摩書房 平成9年初版発行 同年発行2刷参照)P.196-201 ●「広津和郎」(平野 謙 )※『新潮 日本文学小事典』(昭和43年初版発行 昭和51年発行6刷参照)に収録 ●「松川運動史年表」※『松川運動全史 〜大衆的裁判闘争の十五年』(松川運動史編纂委員会 労働旬報社 昭和40年発行)に収録
■ 参考映像:
●「名曲“異邦人”を超えて 〜音楽宣教師 久米小百合〜(あしたも晴れ! 人生レシピ)」(NHK Eテレ 平成30年1月12日放送)
※当ページの最終修正年月日
2023.6.13