| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
大正12年9月1日(1923年。 午前11時58分、関東南部を直下型の巨大地震が襲います(「関東大震災」)。 建物の多くが倒壊し、昼食の準備時だったこともあって方々で出火、延焼して、日本災害史上最大級の被害がでます。約340万人が被災し、10万5千人近くの人が死亡または行方不明となりました。
当地(東京都大田区)も大きく揺れました。特に海に面した所は液状化現象が起きて大きな被害が出ました。
都心はさらに酷く、当地(東京都大田区)などの郊外に人が流れてきます。関東大震災をはさんで大正10年から昭和6年までの10年間で、馬込町は人口が8倍近くにふくれ上がりました。この頃当地で作家が増えたとされますが、増えたのは作家だけではなかったのです。
当地の大林寺(東京都大田区大森中二丁目 7-19 Map→)に震災の供養塔があります。
 |
 |
| 本門寺(東京都大田区池上一丁目 1 Map→)の「帝都震災殃死(おうし)者之霊供養碑」。
|
急流から岸を守る「五十間鼻(ごじゅっけんばな)」(東京都大田区羽田六丁目11-5 Map→)。水難者がたどり着くことも多く、関東大震災のときもそうだった。右手に供養のための仏堂がたつ |
関東大震災のとき、当地(東京都大田区)にゆかりある作家たちは、どうだったでしょう?
宇野千代(26歳)は、大森駅近くの郵便局(現・「大田山王郵便局」。東京都大田区山王二丁目5-7 Map→)から出ようという時、揺れにあいました。尾﨑士郎(25歳)と住んでいた家(東京都大田区南馬込四丁目28-11 Map→)は無事でしたが、朝鮮人が襲ってくるとのデマが飛び交い、2人は恐れて天井裏に隠れ息をひそめました。徳富蘇峰(60歳)は出先の神奈川県逗子で揺れにあって当地に戻ってくる際、抜き身の刀をもつ自警団を見かけ、朝鮮人に間違えられて襲われないかと恐れました。
5歳の池部 良は、家(東京都大田区中央四丁目)の庭で弟と水遊びをしていたそうです。 父(池部
同年(大正12年)7月、5年間の外遊から帰朝した堀口大学(31歳)が当地の「
村岡花子(30歳)は、当地(東京都大田区中央三丁目12-4 Map→)の自宅で遭遇。長男の道雄(2歳)に物語を聞かせたあと昼食の準備に立とうという時でした。家は無事でしたが、夫が経営する「
質屋 「きねや」(現・銀座七丁目)の店員だった山本周五郎(20歳)は店の使いか何かで南麻布の天現寺に来ていて、そこで揺れにあいました。無事でしたが「きねや」 は焼失。新天地を求めて大阪方面へ旅立ち、そのおりに「大阪朝日新聞」に地震の体験記を書き、生まれて初めての原稿料を得ます。
佐多稲子(19歳)は、日本橋丸善で揺れにあいました。当時丸善の洋品部の店員だったのです。 丸善ビルは崩壊しますが、 「外に出ろ!」の指示に従って、危機一髪命拾いしています。
添田知道(21歳)は、東京
北原白秋(38歳)は、妻の菊子と生まれたばかりの長男隆太郎と、小田原の自宅で揺れにあいました。 2階にいた白秋は階下の家族を助けようと階段を降りかけますが、階段が崩壊。 運良く軽傷で済んだようです。小田原は震源が近く(震源は相模湾北部)、都心より揺れが大きかったようです。
今井達夫(19歳)は、東京神田の駿河台辺りを歩いていて遭遇。3日かけて神奈川県鵠沼の実家に戻りますが、家は壊れていました。遺体の焼却を手伝ったそうです。
堀 辰雄(18歳)は、この地震で母親を亡くします。北園克衛(20歳)は銀座でデッサン中でした。辻 潤(40歳)は、川崎で揺れにあったとか。「読売新聞」の記者だった子母沢 寛(31歳)は、新築されたばかりの社屋で遭遇。思わず 「号外、号外」と叫んだら、「号外どころでない!」とどやされたとか。堺 利彦(52歳)は、第一次共産党事件で市谷刑務所の未決監に拘留されており、そこで遭遇。芥川龍之介(31歳)は、東京田端の自宅にいました。家族の救出を妻の
小島政二郎(29歳)も初めての短編集『含羞』の初版2,000部を焼いてしまうなど打撃を受けますが、一冊の本を心の糧にして、苦難を乗り越えます。類焼火災に備え身重だった光子夫人を田端の芥川龍之介の家に預けています。
日本における登山の先駆者辻村伊助(日本人で初めてヨーロッパ・アルプスの厳冬期の4,000m峰に登頂)は、辻村もと子の伯父に当たる人です。彼は箱根湯本に自ら作った高山植物研究のための「辻村高山園」(「湯本幼児学園」の入口手前右手に「辻村伊助邸跡」の案内板がある(Map→ Photo→))で、ローザ夫人と3人の息子とともに被災、土石流に押し流されて5人とも亡くなりました。
大森貝塚の発見者モース(85歳)は、米国で、自らも教鞭をとった東京帝国大学の図書館も壊滅したことを知ります。 彼は一度書いた遺言を書き改めて、自らの全蔵書を東京帝国大学に寄贈しました。
 |
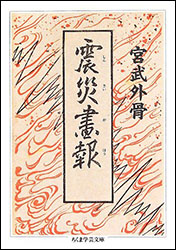 |
| 石井正己 『文豪たちの関東大震災体験記 (小学館101新書) 』 | 宮武外骨『震災画報 (ちくま学芸文庫)』 |
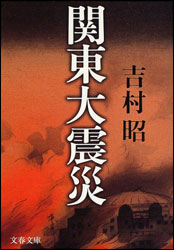 |
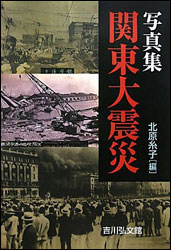 |
| 吉村 昭『関東大震災(新装版) (文春文庫)』 | 『写真集 関東大震災』(吉川弘文館)。編集:北原糸子 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 宇野千代の『色ざんげ』を読む→
・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→
・ 池部 良の『風が吹いたら』を読む→
・ 山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→
・ 佐多稲子の『水』を読む→
・ 北原白秋の『桐の花』を読む→
・ 堀 辰雄の『聖家族』を読む→
・ 『北園克衛詩集』を読む→
・ 辻 潤の『絶望の書』を読む→
・ 子母沢 寛の『勝 海舟』を読む→
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
・ 間宮茂輔の『あらがね』を読む→
・ 小島政二郎の『眼中の人』を読む→
・ 辻村もと子の『馬追原野』を読む→
■ 参考文献:
●「震災の規模と影響」(岡田弘一、山本定男、野村義治)※『大田区史(下)』(東京都大田区 平成4年発行)P.377-381 ●「関東大震災」(木坂順一郎)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に収録(コトバンク→) ●『馬込文士村ガイドブック(改訂版)』(編・発行:東京都大田区立郷土博物館 平成8年発行)P.87-89 ●『生きて行く私(中公文庫)』 (宇野千代 平成4年発行)P.126 ●『風が吹いたら』(池部 良 文藝春秋 昭和62年初版発行 平成8年発行8刷)P.9-11 ●「今は知る人もない中田別荘秘話」※『山王コラム』(後藤浅次郎 平成11年発行)P.1 ●『蘇峰自伝』(徳富猪一郎 中央公論社 昭和10年発行)P.497-498 ●『堀口大学 ~詩は一生の長い道~』(長谷川郁夫 河出書房新社 平成21年発行)P.344-349 ● 『六頭目の馬 ~間宮茂輔の生涯~』(間宮 武 武蔵野書房 平成6年発行)P.97-99 ● 『カバンのなかの月夜 ~北園克衛の造形詩~』(監修:金澤一志 国書刊行会 平成14年発行)P.129 ●『敵中の人 〜評伝・小島政二郎〜』(山田幸伯 白水社 平成27年発行)P.684 ●『物語の娘 宗 瑛を探して』(川村 湊 講談社 平成17年発行)P.163-167 ●『パンとペン ~社会主義者・堺 利彦と「売文社」の闘い~』(黒岩比佐子 講談社 平成22年発行)P.404 ● 『子母澤 寛 ~人と文学~』(尾崎秀樹 中央公論社 昭和52年発行) P.34 ●『大田区の近代文化財(大田区の文化財 第十七集)』(東京都大田区教育委員会 昭和56年発行) P.28-29 ●「文士が体験した関東大震災」(川本三郎)※「図書(751号)」(岩波書店 平成23年発行)に収録 ●『馬込文学村20年』(今井達夫 鵠沼を語る会 平成24年発行)P.153 ●『馬込文学地図』(近藤富枝 講談社 昭和51年発行) P.29 ●『箱根の文学散歩』(箱根文学研究会 かなしん出版 昭和63年発行)P.30-35 ● 『辻村もと子 人と文学』 (加藤愛夫 いわみざわ文学叢書刊行会 昭和54年発行)P.66、P.364 ●「「桃山晴衣の音の足跡」番外篇 東北関東大震災に寄せて」(土取利行)(音楽略記→) ●「[講演要旨] 東京の街に残る関東大震災の跡」(武村雅之)(歴史地震研究会→ ※PDF)
※当ページの最終修正年月日
2024.9.1