| {column0} |

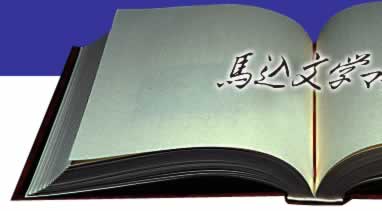







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
13歳頃の室生犀星 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『切なき思ひを愛す(室生犀星文学アルバム)』(
明治35年5月9日(1902年。 室生犀星(12歳)が、高等小学校を3年で中退、金沢地方裁判所(石川県金沢市丸の内7-2 Map→)の給仕になりました。
小学校での犀星は、勉強をしようとせず、文学的才能も示しませんでした。彼の場合は神童伝説といったものとは全く無縁。始業ベルが鳴っても席につかず、級友の前で切腹のまねをしてふざけていて、教師に見つかり 「わしの前でもう一度やってみろ!」 と叱られると、臆面もなく教師の前でそれを繰り返したといいます。大人から見たら、ふてぶてしく、可愛げのない子どもだったことでしょう。「高等小学校を3年で中退」といっても気の毒に思う必要はありません。 彼は学校が大嫌いだったのですから。
そして、裁判所の給仕になりますが、その頃のことを次のように書いています。
・・・自分は
しかし、この裁判所で、犀星は“文学”と出会うこととなります。
裁判所で俳句を愛好する職員の作品を、新聞社の人に渡すのも犀星の役目でしたが、そのうちに自身もまねて俳句を作るようになります。
犀星は自作俳句を、俳句を愛好する監督書記の川越一弥という人の机上にそっとおきます。すると、川越は添削して戻してくれました。その後も繰り返し、20~30句あっても、川越は夕方までにびっちり赤筆が入れて戻してくれたそうです。
犀星は言葉の面白さに目覚めます。夢中になり、そして、めきめき力をつけていきました。しばらくすると作品が地方新聞に掲載されるようになり、 「文壇の一寵児」 とまで評されるようになります。「豚のやうにやくざ」と卑下していた少年は、自分に秘められていた“力”に目をみはり、小躍りしたことでしょう。
後年、犀星は、川越のことを、
生涯に師とよぶに
と書いています。
裸足で通った裁判所が、犀星のかけがえのない“学校”になりました。
 |
山本周五郎にとっての“学校”もふつうの学校ではありませんでした。
周五郎は家族と横浜久保町の二軒長屋に住んでいましたが、小学校を卒業すると、隣に越してきた添田家の長男・貞吉(後年親友になる添田知道の従兄弟。隣家の主・添田辰五郎の兄が添田唖蝉坊)が番頭をしていた質屋「きねや」(東京都中央区銀座七丁目12-6 Map→)で住み込みの徒弟となります。周五郎は中学校への進学を強く望みましたが、家計が許しませんでした。
周五郎は大正5年から大正12年(13歳~20歳)までの7年間、「きねや」で働くこととなりますが、そこの主人がたいへんな人格者で、質素な身なりで店員とともに汗をかき、顧客の苦境をさっしては返金の期限がきても催促せず、また、店員たちが独立して困らないよう彼らを夜学に通わせたといいます。周五郎はこの主人のもとで実学を学ぶとともに、文学の才も磨いていきました。自然と店員たちに向学心が生まれ、彼らだけで同人誌を作ったりもしています。作家山本周五郎の原点は「きねや」にありき、です。周五郎は「きねや」主人を「真実の父」と呼びました。
少しややこしいですが、実は、周五郎のペンネーム“山本周五郎”(本名は
 |
南方熊楠(17歳)は、明治18年の2月1日と5月12日の2回、大森貝塚に採集に来ていますが、その頃、大学予備門(東京大学の前身)の学生でした。山田美妙、正岡子規、秋山
熊楠は、翌明治19年(19歳)には予備門をさっさと退学、単身米国に渡って以後14年間、海外を渡り歩いて“知の巨人”となっていきます。英国では大英博物館に入り浸って英語・仏語・イタリア語・スペイン語・ポルトガル語・ギリシャ語・ラテン語の文献を読みあさり、克明なメモを4万8千枚残し、在英中にすでに、世界的に権威のある科学雑誌「Nature」に寄稿、まずは英国の学会で認められました。熊楠は生涯に51本もの論文を「Nature」に寄稿。 この記録はまだやぶられていないようです。
熊楠は、大の勉強好きでしたが、大の学校嫌いだったのでしょうね。本当に学びたいこと(やりたいこと)を見つけてしまった人には、学校という場は「かったるい」かも?
 |
小島政二郎にとっての学校は、芥川龍之介の2階の書斎「
寺山修司は自身にとっての“学校”を、「歌舞伎町と映画館の暗闇」と表現しました。
世界的な記録を作ってきたクライマーのユージ(平山裕示さん)は、高校のときくらいから、「誰も登れていない岩」の情報を入手すると、飛んでいって、登れるまでは里に下りてこなかったとか。彼の“学校”は、岩場。
ワクワクすることに出会えたら、そこが「学校」であり、そこでの先達が「先生」でしょう。
 |
 |
| イヴァン・イリッチ 『脱学校の社会 (現代社会科学叢書) 』(東京創元社) | 石井 |
 |
 |
| 今井むつみ『学びとは何か 〜〈探究人〉になるために〜 (岩波新書)』 | ピーター・グレイ『遊びが学びに欠かせないわけ 〜自立した学び手を育てる〜』(築地書館)。訳:吉田新一郎 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→
・ 小島政二郎の『眼中の人』を読む→
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
■ 参考文献:
●『評伝 室生犀星』(船登芳雄 三弥井書店 平成9年発行)P.64-84 ●「金石の犀星」展のチラシ(室生犀星記念館 平成19年) ●『切なき思ひを愛す(室生犀星文学アルバム)』(
※当ページの最終修正年月日
2024.5.9