| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
「馬込文士村レリーフ」の一部。「大森駅」(東京都大田区大森北一丁目6-16 map→)の中央改札西口(山側)正面の坂道(「天祖神社」脇の石段。ストリートビューで辿れる(link→))の途中にある。ここを上って、“馬込文士村”へLet's Go!
 |
昭和46年11月6日(1971年。 、当地の「馬込図書館」(東京都大田区中馬込二丁目26-10 map→)で、地域文学の研究家・染谷孝哉(53歳)が、「馬込文学散歩」という演題で講演をしています。
『大田文学地図』は、1年前(昭和45年)の母親の死がきっかけになって編まれ、亡母に捧げられています。
なぜか、この頃(昭和46年前後)、当地の文学に関する本が立て続けに発行されています。
 |
染谷の『大田文学地図』が発行される1年前(昭和45年)出版された榊山 潤(69歳)の『馬込文士村』は、次のように書き出されています。
どういう会であったか忘れたが、久しぶりに広津和郎氏に遇った。私が会場の隅にならんだ椅子にかけてタバコを吹かしていると、入口に広津さんの姿が見えた。広津さんは酒を飲まないから、中央の卓のまわりに群がる人たちの間に、割りこむようなことはない。
せかせか歩いてきて、私に気がつくと、私のとなりの椅子にかけ、馬込はおもしろかったね、と言った。
「馬込があんなにおもしろかったのは、尾崎君がいたせいだね。尾崎君がいなかったら、あんなにおもしろくなかったろうね」
たぶん広津さんは、私の顔を見て馬込を思い出したのではあるまい。何かで馬込のことを考えていて、私の顔を見ると、たまった水がはけ口を見つけたような気持になったのであろう。広津さんの声に弾みがあった。
いきなり馬込を持ち出されて、私はいささか面くらい気味だったが、しかし馬込が意識の上にひろがってくるのに、二秒とはかからなかった。
・・・(榊山 潤『馬込文士村』より)
この「尾崎君」は尾﨑士郎のことで、彼と伴侶の宇野千代とが大正12年、当地に来てから、当地にわんさかと文学畑の人が集まるようになりました。その尾﨑とやはり当地にいた三好達治とが昭和39年に立て続けに死去し、当時の“文士村”的雰囲気を懐かしむ気運となったようです。
榊山の『馬込文士村』と染谷の『大田文学地図』に触発されてか、近藤富枝が、『大田文学地図』の5年後の昭和51年に『馬込文学地図』を出します。 『馬込文士村』は榊山が実際に体験したことが中心に書かれており、 染谷の『大田文学地図』は範囲が大田区全体で、時代の幅もあるので、網羅的ですが一つ一つは詳しくありません。近藤は、“馬込文士村”という地域に限り、時代も尾﨑と宇野が来る大正12年くらいから二・二六事件のある昭和11年頃までに限って、濃密に描いています。
近藤は『馬込文学地図』を出す前にも同じ手法で、『
「菊富士ホテル」を経由して尾﨑士郎、宇野千代、広津和郎らが当地に来て、田端を経由して萩原朔太郎、室生犀星らが当地に来ます。
 |
 |
| 田端にある芥川龍之介の旧居跡。案内板(写真中央)が立っている。“田端文士村は”、大正8年3月、芥川(27歳)が鎌倉から養父母のいる田端に戻ってきたのを機に、犀星(29歳)や朔太郎(32歳)といった作家が集まり、形成された | 在りし日の菊富士ホテル。今は石碑しかない(Photo→)。塔状の部分の屋根裏部屋に坂口安吾が逗留していたことがある ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:クレヤン・コム/伊藤野枝年譜 1914年(大正3年)19歳→ |
“馬込文士村”の作家たちは、あるときは軽井沢に集い(作家がよく集う「つるや旅館」があり、軽井沢に別荘もつ作家も複数名いた)、また、昭和2年頃からは伊豆湯ヶ島にこぞって出かけ(湯ヶ島には川端康成が
 |
 |
| 「湯本館」の窓より。
|
女性だけのコミュニティーも生まれた。左より、林 芙美子、佐多稲子、吉屋信子、宇野千代。昭和11年東京新宿の吉屋邸にて。※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『馬込文士村 〜あの頃、馬込は笑いに充ちていた』(東京都大田区立郷土博物館)原典:日本近代文学館所蔵写真 |
明治の終わり頃から、画家、詩人、作家、作曲家、役者などが集う異分野交流もありました。
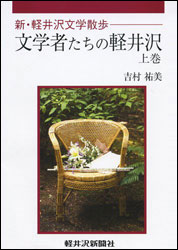 |
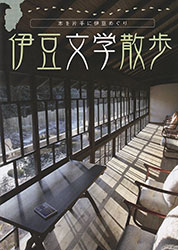 |
| 吉村祐美『文学者たちの軽井沢(新・軽井沢文学散歩)』(軽井沢新聞社) | 『伊豆文学散歩 〜本を片手に伊豆めぐり〜』。発行者:静岡県文化・観光部文化学術局文化政策課(伊豆文学フェスティバル実行委員会) |
 |
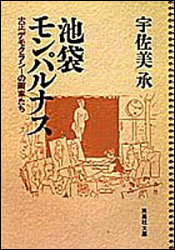 |
| 村上 護『阿佐ケ谷文士村』(春陽堂書店)。井伏鱒二に、太宰 治に、小林多喜二に、亀井勝一郎・・・ | 宇佐美 承『池袋モンパルナス 〜大正デモクラシーの画家たち〜(集英社文庫)』)。画家たちも集った |
■ 馬込文学マラソン:
・ 染谷孝哉の『大田文学地図』を読む→
・ 榊山 潤の『馬込文士村』を読む→
・ 近藤富枝の『馬込文学地図』を読む→
・ 広津和郎の『昭和初年のインテリ作家』を読む→
・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→
・ 宇野千代の『色ざんげ』を読む→
・ 萩原朔太郎の『月に吠える』を読む→
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 小島政二郎の『眼中の人』を読む→
・ 高見 順の『死の淵より』を読む→
・ 川端康成の『雪国』を読む→
・ 子母沢 寛の『勝 海舟』を読む→
・ 真船 豊の『鼬』を読む→
・ 吉屋信子の『花物語』を読む→
■ 参考文献:
●『広津和郎 〜この人との五十年〜』(間宮茂輔 理論社 昭和44年発行)P.82-83 ●「“いま”とのパイプ役果たした人(「馬込文士村」 No.40)」(文:谷口英久)(「産經新聞」平成3年6月11日号に掲載)
※当ページの最終修正年月日
2023.11.6