








(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
食うだけは稼がねば人間日干しだが、だからといって「年収○○○万円のいい仕事」といった仕事観だけでは、悲しすぎる。それじゃ私の立つ瀬がない、といった個人的なことだけではなく、そういった仕事観がもてはやされ、また、もてはやされる恐さがさほど問題にされないのが恐い。ズルする人が絶えないのはそのため?とも思う。収入が多ければ結果オーライな人は、そのプロセスとか、その仕事への志とかはさほど重要でないのかも・・・。
で、そもそも「仕事」とは何なのか?
言い古された感もあるが、やはり文字通り「
そういった考えに立つと、この本『大田文学地図』の著者・染谷孝哉なんかは、素晴らしき仕事人だ。彼の台所事情を心配した友人が彼に仕事を紹介していたというから、彼の稼ぎは多くなかった。それでも彼が素晴らしき仕事人といえるのは、まさに一つの
その「仕事」の集大成が、この『大田文学地図』だ。
半端じゃない。この本の索引には364名(主に作家)の名前がずらりと並ぶ。これらの人物を東京都大田区という一地域に結びつける作業が彼の「仕事」だった。
 |
| 『大田文学地図』の人名索引は8頁にわたる |
『大田文学地図』について
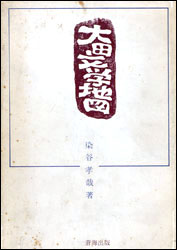 |
染谷孝哉による当地(東京都大田区)の文学案内書。昭和46年(染谷53歳)発行された。
昭和30年頃から日本文学協会京浜支部のニュース「
後に発行される『大田文学地図 II』(染谷の遺稿集。城戸が編集した)と合わせ、緻密さでこれらの本を越える当地の文学案内書は今のところないだろう(令和6年8月13日現在)。
■ 作品評
●「 読者はどこからでも気ままにページをひらけばよい。たちまち、さっき上って来た坂道、すぐそこの街角が、古い文学者、新しい文学者たちの面影をやどして息づきはじめるのを知るだろう」(久保田正文)
●「東京の大田区に関わりのあった作家たちの人と作品を丹念に調べあげた最初の記録」(小関智弘)
染谷孝哉について
 |
| 大田文学地図出版記念祝賀会での染谷孝哉。「ホテルニュージャパン」にて ※『大田文学地図 II』 より |
地域文学研究に捧げられた一生
大正7(1918)年、東京小石川区
著書は、 『大田文学地図』『大田文学地図 II』 の他に、『鎌倉 もうひとつの
島崎藤村の『桜の実の熟する時』『春』『新生』といった自伝的告白小説を、舞台となる東京都品川あたりの坂の描写と絡めて紹介した「坂のある風景 〜岸本捨吉の像〜」、戦前・戦後と池上通りの大森駅から大田区役所(現・「大田文化の森」(東京都大田区中央二丁目10-1))の間くらいまでに7-8軒あったという古書店について書かれた「大森の古書店今昔」、久保 栄、真山青果、木下順二の戯曲の思想面に触れたまとまった文章なども残す。
東京都大田区内の成人学校や図書館などで文学講座の講師も務めた。
昭和61年11月7日、当地の「大田病院」(東京都大田区大森東四丁目4-14 Map→)で死去。死因は肺がんだった。68歳( )。
■ 染谷孝哉評
●「寡黙な人だった。ことに自分のことは殆ど話さない人だった」(佐藤美奈子。染谷が中心にやっていた「日本文学協会京浜支部」に参加していた方)
●「生涯折り目正しく、控え目に、後ろ姿美しく生きた人であった」(かのう・すすむ)
 |
| 染谷孝哉『鎌倉もうひとつの |
染谷孝哉と馬込文学圏
関東大震災で被災したためか、大正13年(5歳)、東京小石川から家族で当地に移転、終生同地(東京都大田区)に住んだ。東京都大田区山王四丁目17の借家で母親と二人で暮らした後、近くの「住吉荘」(「コトー山王」(山王四丁目21-19 Map→)の場所にあった。大森駅前(西口)の「馬込文士村案内」には愛した作家らとともに染谷の名もある Photo→)に転居。 母親の死後も一人そこに住み、終の棲家とした。
 |
 |
| 木原山に上る階段。上り始めてすぐ右手に「住吉荘」があった | 染谷はこの「住吉荘」の2階に住んだ。部屋には本と原稿以外のものはほとんど置かなかった |
参考文献
●「大森バス通りの古本屋」(浜賀知彦)、「大田文学地図 落ち穂拾い(2)」(城戸 昇)、「私の地図 〜小石川界隈〜」(染谷孝哉) ※「わが町あれこれ(第2号)」(編・発行:城戸 昇 わが町あれこれ社 平成6年発行)に収録 P.18、P.46-48、P.55 ●「坂道のある風景 〜岸本捨吉の像〜」(染谷孝哉)※「わが町あれこれ(第1号)」(編・発行:城戸 昇 わが町あれこれ社 平成6年発行)に収録 P.2-5 ●「大森の古書店今昔」(染谷孝哉)※「わが町あれこれ(第3号)」(編・発行:城戸 昇 わが町あれこれ社 平成6年発行)に収録 P.2-4 ●「染谷孝哉さんと『大田文学地図』」(佐藤美奈子)※「わが町あれこれ(第17号)」(編・発行:城戸 昇 わが町あれこれ社 平成10年発行)P.28-29 ●「染谷孝哉さんを偲んで」(かのう・すすむ、阪本芳夫、望月新三郎、浅田石二、浜賀知彦、小関智弘)、「年譜にかえて」「あとがき」(城戸 昇)※『大田文学地図 II(染谷孝哉遺稿 )』(編:城戸 昇 文学同人眼の会 平成5年発行)P.188-203
※当ページの最終修正年月日
2024.8.14