| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
朝夕の新聞小説が楽しみ。新聞小説の山は生きて読んだ証。連載が終わったら、厚紙で箱を作って収める(箱作りで参考にしたサイト:プチプラ手芸の日々、時々ネイル。/作りたいサイズでギフトボックス♪ 作り方その1♪→)。●1年前の山→ ●2年前の山→ ●3年前の山→ ●4年前の山→ ●4年と半年前の山→
 |
昭和31年11月19日(1956年。
、「東京新聞」夕刊で、室生犀星(67歳)の『
戦後、犀星は「過去の作家」になりつつありましたが、1年前(昭和30年)に書いた『随筆 女ひと』(当地(東京都大田区)で犀星の家の斜め向かいに住んでいた小林古径が表紙を描いた)で圧倒的な存在感を示し、この『杏つ子』にも
連載回数は271回。生涯に700篇もの小説を書いた犀星ですが、最長の一篇となりました。
 |
バルザック |
一枚刷りの不定期発行の官報の類の新聞は昔からありましたが、日刊新聞は1660年創刊のドイツの「ライプツィヒ新聞」(「Leipziger Zeitung」)が最初です。新聞が広く読まれるようになるのはフランス革命間近のパリにおいて。1777年創刊の「パリ新聞」(Journal de Paris)を読むことをパリ市民は日課としました。世の中の担い手が自分たちであるとの自覚がそうさせたのでしょう。
1836年に創刊されたフランスの「ラ・プレス」(「La Presse」)にバルザックの小説が連載されるようになり、その第一作『老嬢』(Amazon→)が新聞小説の第一号とされています。その後、他紙にウジェーヌ・シューが『パリの秘密』を連載。前科者、脱獄囚、インチキ医者、泥棒、情婦たちが織りなす波乱万丈の物語が大当たりで、各新聞もこぞって新聞小説を始めました。そして、今もよく読まれるA・デュマ(父)の『モンテ・クリスト伯』(Amazon→)、『三銃士』 (Amazon→)なども新聞小説として生まれます。
日本では、知識人向けの新聞(「
他にも新聞小説から、自由民権思想を啓蒙する「政治小説」、家庭のモラルを考えさせる「家庭小説」なども生まれます。新しい概念や新しい思想を面白く分かりやすく伝えるのに新聞小説が大いに活用されました。
「読売新聞」は坪内逍遥の助言で明治19年から新聞小説を初めて、山田美妙、森 鴎外、泉 鏡花、尾崎紅葉(『金色夜叉』)、田山花袋、与謝野晶子、正宗白鳥、島崎藤村(『家』)、石川啄木、谷崎潤一郎、芥川龍之介、川端康成、菊池 寛、中里介山(『大菩薩峠』)、吉屋信子(『女の階級』)などを起用。「読売新聞」は「文学新聞」と呼ばれた時期もあったそうです。
 |
 |
二葉亭四迷 |
明治12年創刊の「朝日新聞」の小説も最初は戯作調でしたが、明治37年に入社した二葉亭四迷(39歳)が『
幸田露伴の『五重塔』(新聞「国会」)、徳冨蘆花の『
戦後の、井上 靖の『氷壁』(「朝日新聞」)、佐藤春夫の『極楽から来た』(挿絵:芹沢銈介。「朝日新聞」)、寺山修司の『ほらふき男爵』(挿絵:及川
連載回数は増化傾向にあるようで、 昭和25年から17年間「北海道新聞」「東京新聞」などに連載された山岡荘八の『徳川家康』は文庫本で26冊。新聞連載だと何回になったでしょう? 「聖教新聞」に連載された池田大作の『人間革命』『新・人間革命』などは平成30年9月8日に連載を終え、な、なんと計7,978回! (ただし、最後の方は、池田が書いたか疑問の声も・・・)。五木寛之の『親鸞』(Amazon→)も、平成20年9月から平成26年7月までに、40社もの地方紙に1,052回連載されました。山口 晃が挿絵を担当、全1,052枚の挿画と作者の「絵解きコメント」つきの『親鸞 全挿画集』(Amazon→)も発行されています。
新聞小説は、TVドラマや連載マンガなどと同様「続きもの」なのでハマります。今日はどうなるかと、毎日、新聞を開くのが楽しみです。現在注目されている作家と、連載期間中、じっくり“語らう”ことができるのも魅力。直近に書かれたものなので、その時々の時事・現象・発見などが反映され、それを著者がどう料理するかも見ものです。朝刊の小説の著者は同じ新聞の夕刊の小説を意識して読んでいると思われ(逆もしかり)、内容が微妙にリンクしているのも面白いです。意識的にリンクさせている人もいるかもしれません。
新聞小説はフランスと日本以外ではほぼ見られず、日本ではさらに各戸に新聞を配達してくれます。恩恵にあずかりたいもの。
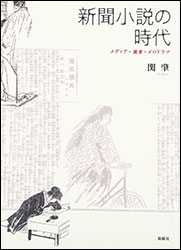 |
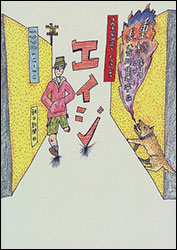 |
| 関 肇『新聞小説の時代 〜メディア・読者・メロドラマ〜 』(新曜社) | 重松 清『エイジ(newspaper version)』(朝日新聞社)。新聞連載時の挿絵を全部収録。挿絵:長谷川集平 |
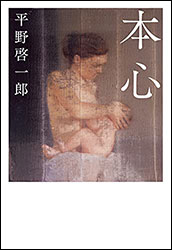 |
平野啓一郎『本心』(コルク)。令和元年から「東京新聞」(朝刊)に連載された小説。著者の意向で、連載中から、ネットでバックナンバーが読めるようになっている。なんでも金、金のあさましい世の中にあって、「文化の無償化」(文化享受機会の公平)の有意義な試み ●東京新聞/連載小説「本心」→ |
■ 馬込文学マラソン:
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
・ 川端康成の『雪国』を読む→
・ 吉屋信子の『花物語』を読む→
・ 井上 靖の『氷壁』を読む→
◾️参考文献:
●『評伝 室生犀星』(船登芳雄 三弥井書店 平成9年発行)P.9、P.268-269 ●「新聞の歴史」(内川芳美、桂 敬一)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に収録(コトバンク→) ●「新聞小説」(高橋春雄)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に収録(コトバンク→) ●『新聞小説史 〜明治篇〜』(高木健夫 国書刊行会 昭和49年発行)はしがき、P.3-14、P.241-244 ●『新聞小説史年表』(高木健夫 国書刊行会 昭和62年発行)P.18、P.88、P.106、P.108、P.125-126、P.129、P.134、P.152、P.154 ●「(読売新聞)の主な連載小説の記録」(読売新聞へようこそ→) ●「新聞小説 135年の物語 〜四迷、純文学への起点/「宮本武蔵」1000回超す/太宰自殺、掲載1話のみ」※「朝日新聞(朝刊)」平成26年4月16日掲載 ●「小説記者・夏目漱石」※「朝日新聞(朝刊)」平成26年4月15日掲載 ●『夏目漱石(新潮日本文学アルバム)』(昭和58年初版発行 平成13年発行18刷)P.95
※当ページの最終修正年月日
2023.11.19