| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
昭和30年(1955年。
、新潮社の文芸誌「新潮」の編集者・小島千加子さん(27歳)が東京四谷の
二人のやりとりが傑作です。
川端 「驚いたね。まだ待っているの? それで、間に合うかしら」
小島 「はあ、待っています。目次にちゃんと刷りこんでありますから、無くなると大変なことになります」
川端 「へえ、目次に? なんて?」
小島 「雨だれ」
川端 「あまだれ? かなで?」
小島 「雨だけ漢字で、だれ、と平がなです」
川端 「それじゃ、それで書きましょう」
小島 「は? あの、雨だれ、で?」
川端 「え、雨だれ。正月早々、不景気な題ですね。そうと決まれば書けるでしょう。でも、作文みたいなものかもしれませんよ。明日の晩には終わるでしょう」
編集者は時には強引に作家の背中を押すことも必要なようです。川端は翌日の午後2時半すぎには冒頭の原稿を小島さんにわたし、午後6時までに原稿用紙14枚を仕上げて彼女をホッとさせました。全編雨だれの音がするような一夜の出来事を通し戦後直後の一風景を活写した佳作で、作品集『富士の初雪』(日本の古本屋→)に収められています。
小島さんは敗戦直後の昭和23年頃編集者になり、室生犀星、檀 一雄、野上弥生子など多くの作家を担当。森
 |
波多野秋子 |
大正12年、売れっ子の芥川龍之介(31歳)に作品(『『猿蟹合戦』』。おとぎ話を芥川流に書き直したスパイシーな作品)を書かせたのが、「婦人公論」の編集者・波多野秋子(29歳)です。波多野は、芥川に『猿蟹合戦』を書かせた数ヶ月後(大正12年6月9日)、有島武郎とこの世を去ります。
 |
 |
| 波多野と有島が心中した軽井沢の有島別荘跡。旧「三笠ホテル」(長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1339-342 Map→)の裏あたり | 有島別荘「浄月庵」は、現在、「軽井沢高原文庫」(長野県北佐久郡軽井沢町長倉塩沢217 Map→)に移築されている |
 |
波多野の上司だった「中央公論」の編集長・滝田樗陰は、名編集長として鳴らした人です。宗教雑誌「反省(会)雑誌」が明治32年「中央公論」と改題、大正元年、樗陰(30歳)が編集長になるや文芸欄と政治評論に力を入れて総合雑誌として急成長します。夏目漱石、森 鴎外、芥川龍之介らに書かせ、新人発掘の手腕にも定評がありました。彼の黒塗りの人力車が止まった家の作家は大概大成するとささやかれ、作家たちは樗陰の人力車に胸をときめかせました。宇野千代も樗陰に見出された一人です。学者・吉野作造を書斎から引き出して檜舞台にあげて、彼の説く民本主義(民主主義、主権在民)を広めた功績もあります。樗陰が編集長を務めた期間はほぼ大正年間(「大正デモクラシー」の期間)と重なります(大正14年(43歳)、腎臓病と喘息で死去)。
 |
中村武羅夫 |
樗陰と並び称された名編集者に「新潮」の中村
大正12年に「新潮」を意識して菊池 寛周辺の人が結集して「文芸春秋」が創刊、翌大正13年にはプロレタリア文学の牙城「文芸戦線」と新感覚派の拠点「文芸時代」も創刊、さらには翌大正14年、中村を中心に文芸誌「不同調」(「新潮」の「不同調欄」からの命名)も創刊しました。明治時代からの自然主義文学の伝統を尊重するタイプから、一人一党主義(既存の派閥や主義などクソ食らえのタイプ)などが結集。岡田三郎、尾﨑士郎、間宮茂輔、佐佐木
 |
小島政二郎も、大正7年、慶応の文学部を卒業すると、創刊当初の児童雑誌「赤い鳥」の編集に携っています。書けない作家の代筆などもやったようです(代筆も編集者の仕事?・・・否、読者を騙してはいけませぬ)。
村松友視さんも、編集者から作家になりました。中央公論社の「婦人公論」「海」の編集者で、文壇外の作家発掘を得意としたそうです。村松が原稿40〜50枚ほどをペラペラっとして、冒頭の10枚ほどをさっと捨てると作品がグッとよくなったといいます(文章の冒頭には余計なことが書かれがち?)。平凡社で編集者だった嵐山光三郎さんがこの話に感心して真似たら、作家に殴られたそうな(笑)。
編集者で自著を出すケースもままあることでしょうし、作家や学者やその他が編集・編纂に携わることも少なくありません。昭和史に関する数多くの佳作を残した半藤一利も文藝春秋社の編集者でしたし、鉄道紀行文学を確立した宮脇俊三も元は中央公論社の名編集長でした(北
編集者がある程度売れる本を企図するのは当然ですが、それ(売れること)を第一にして劣悪な本を生み出している出版社(編集者)もあります。出版社(編集者)で本を選ぶことをお勧めします。
 |
 |
| 小島千加子『作家の風景』(毎日新聞社)。編集者の目線で蘇る作家17名の素顔 | 酒井順子『百年の女 〜「婦人公論」が見た大正、昭和、平成〜』(中央公論新社) |
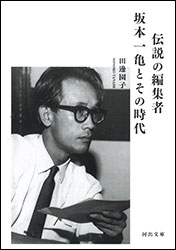 |
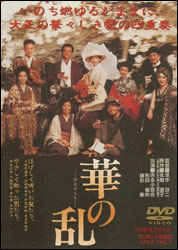 |
| 田邊園子『伝説の編集者 坂本一亀とその時代 (河出文庫)』。三島由紀夫をはじめとする気鋭の作家を世に送り出した人。坂本龍一さんのお父さんです | 映画「華の乱」。監督:深作欣二。波多野秋子(演:池上季実子)と有島武郎(演:松田優作)の心の機微。松田の死の前年(昭和63年。もう相当悪かった)に公開 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 川端康成の『雪国』を読む→
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
・ 宇野千代の『色ざんげ』を読む→
・ 辻村もと子の『馬追原野』を読む→
・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→
・ 間宮茂輔の『あらがね』を読む→
・ 小島政二郎の『眼中の人』を読む→
・ 村松友視の『力道山がいた』を読む→
■ 参考文献:
●『作家の風景』(小島千加子 毎日新聞社 平成2年初版発行 同年発行2刷)P.30-33 ●『断髪のモダンガール(文春文庫)』(森 まゆみ 平成22年発行)P.78-85 ●『生きて行く私(中公文庫)』(宇野千代 平成4年発行)P.97-102、P.109-114 ●「滝田樗陰」(瀬沼茂樹)、「中村武羅夫」(
※当ページの最終修正年月日
2024.12.5