| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
空を見上げ、ふと、故人を思う
 |
昭和34年11月29日(1959年。 出版社「博文館」の社長・大橋進一(74歳)が亡くなりました。大橋の世話になってきた山本周五郎(56歳)も式場に向かいます。が、式場には顔を出さず、電信柱のかげから棺を見送ったとのこと。 “常識人”としてのアリバイ作りで葬儀に出る人も多そうですが、 周五郎はそういった「形だけ」が嫌いでした。聖書の一節「施しや祈りは人に気づかれないようにやりなさい」(『マタイによる福音書』(6章2節~)の実践でもあったのでしょう。周五郎は子どもの頃から聖書に親しんできました。
周五郎は妻が亡くなったとき、自宅の本箱を壊し自ら棺桶を作って、自分たちで火葬場まで
 |
芥川 文 |
芥川龍之介(35歳)は、昭和2年、自宅の2階で大量の薬を飲み、その後、階下で寝ていた妻の
 |
 |
サトウハチロー |
徳田夢声 |
敗戦直後の昭和21年から放送されたNHKラジオの「話の泉」のアナウンサー・和田
室生犀星は妻の一周忌に、二人の思い出の地に二人の空間を作りました。
“究極の墓”は、宮沢賢治が見出した石川善助の“墓”でしょうか。
石川さんを失つてすでに百日を経た。
いまはもう東京の夜の光の
(善助の死後、知人らによって編まれた『
行為による“弔い”はいろいろです。
故人の後をついで物事に取り組むのも“弔い”でしょう。故人の未完作を完成させるのも“弔い”。スケッチを残しながらもその完成を見ることができなかった立原道造の「ヒアシンスハウス」が、没後65年して誕生しました。
山本周五郎の『赤ひげ診療譚』に出てくる佐八が、長屋のみんなのため身を粉にして働くのも、実は亡き妻への“弔い”でした。
『極道の妻たち』の著者・
私事ですが、義弟が急逝したおり、ジャズ仲間が楽器を持って通夜の場に集まりました。それを見たお坊様が、葬祭場に掛け合ってくださり、例外的に、葬祭場でのオールナイト・セッションとなりました。故人の喜ぶ声が聞こえるようでした。
 |
慰霊・追悼することが問題視されることもあります。靖国神社を、日本の首相や大臣、その他の公務員が、「公式」に参拝することにどんな問題があるのでしょう?
その後、日清、日露、日中戦争、アジア太平洋戦争などの対外戦争での戦死者も「神」(英霊)に加えられ、靖国神社はこれらの戦争を正当化する役割も果たしてきたのです(これらの戦争は、日本が仕掛け、戦火を拡大することの連続だったのに)。日清、日露、日中戦争、アジア太平洋戦争で被害にあった国が日本の首相や大臣、その他の公務員による「公式」参拝に反発するのはそのためです。
日本の首相や大臣、その他の公務員が「公式」に参拝することは、公的地位を利用して、これらの戦争の基底にある「明治政府史観」や「特定宗教」を支持することを表明する行為ともいえます。
 |
 |
| 島田裕巳『「墓じまい」で心の荷を下ろす (詩想社新書)』 | 坪内祐三『靖国 (文春学藝ライブラリー)』。靖国神社とは何か? |
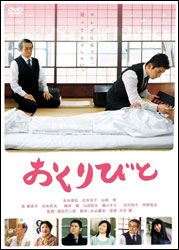 |
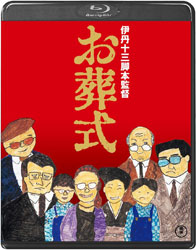 |
| 『おくりびと』(松竹)。監督:滝田洋二郎。出演:本木雅弘、山崎 努、広末涼子、吉行和子ほか。日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞 | 「お葬式」。監督:伊丹十三。出演:山崎 努、宮本信子、菅井きん、大滝秀治、笠 智衆ほか。葬式というタブーに挑戦。その年の映画賞を総ナメにした |
■ 馬込文学マラソン:
・ 山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
・ 片山広子の『翡翠』を読む→
・ 村松友視の『力道山がいた』を読む→
・ 川口松太郎の『日蓮』を読む→
・ 辻 まことの『山の声』を読む→
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 石川善助の『亜寒帯』を読む→
■ 参考文献:
●「木村聖哉「戦時下の山本周五郎」への反論 ~作家像追究の視点をめぐって」(木村久邇典)※「青山学院女子短期大学紀要(43)」(平成元年11月10日刊)P.58-60 ●『断髪のモダンガール(文春文庫)』(森 まゆみ 平成22年発行)P.86-93 ●『大田黒元雄の足跡 ~西洋音楽への水先案内人~』(東京都杉並区立郷土博物館 平成21年発行)P.46-50 ●『詩人 石川善助 ~そのロマンの系譜~』(藤 一也 萬葉堂出版 昭和56年発行)P.406-407 ●『孤独という名の生き方 〜ひとりの時間 ひとりの喜び〜』(家田荘子 さくら舎 平成29年発行)P.92-101 ●「靖国 複雑化する論点(歴史と向き合う 第3部 〜追悼のかたち〜)」(隅田佳孝、西本 秀)※「朝日新聞(朝刊)」(平成18年8月1日号)に掲載
※当ページの最終修正年月日
2024.11.29