| {column0} |

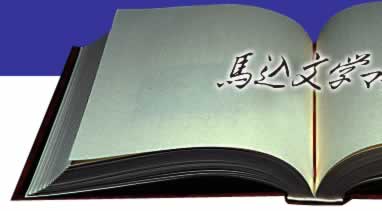







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
中国の重慶を空襲する日本の爆撃機 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:「東京朝日新聞」(昭和15年8月24日号)
昭和12年7月7日(1937年。
の夜中から翌8日の早朝にかけて、北京の西南方面郊外の
英国がしかけた正義0の戦争「アヘン戦争」(1840-1842)に始まる列強の中国侵略に便乗し、日本も、上海を中心に中国での権益を増大させていました。明治27年には日清戦争を引き起こし、中国をさらに圧迫。そういった「帝国性暴力」に抵抗して、明治32年、義和団を中心とする抵抗運動が中国北部を中心に広がりますが(「義和団の乱」と呼ばれるが「義和団の抵抗」とすべき)、日、米、英、露、仏などが軍隊を派遣しそれを鎮圧、中国は北京議定書に調印させられます。そこには、列強が北京などに守備兵を置くことを認める文言がありました。日本も「支那駐屯軍」を置くようになり、「盧溝橋事件」では、その「支那駐屯兵」(6,500名ほど。駐屯兵の域を越す「天津軍」を呼んでもいい規模)が中国軍と衝突したのです。
夜間演習中の「天津軍(支那駐屯軍。日本軍)」に発砲があり、日本軍はそれを中国軍からの発砲として、近くの中国軍を攻撃、戦闘が始まりました。一報を聞いた近衛文麿首相(45歳)や海軍次官の山本五十六(53歳)が直感したように「陸軍の自作自演の可能性」大ですが(「張作霖の爆殺」「満州事変」「第一次上海事変」が皆そうだった)、日本には「中国一撃論」といった戦争待望論があり、戦闘が拡大されていきます。
当初、不拡大方針だった近衛首相も、陸軍に押し切られ、4日後の7月11日に計5師団を中国に送ることを決定。日本軍は北京、天津、上海と占領し、国民政府軍が首都の南京(Map→)に後退したのを追って「南京事件」(中国の捕虜や一般市民も多数殺害。旧陸軍の正規将校の団体・偕行社が発行した『南京戦史』によるとその数3万人超。昭和12年11月〜。12月13日、南京を占領)を起こしました。しかし、中国政府は機能を重慶へ移し(重慶政府)、また米英ソの支援を受けて徹底抗戦、戦争が長期化していきます。中国の国民政府軍(蒋介石)と中国共産党軍(毛沢東)は対立していましたが、前年(昭和11年)の「
日本軍は重慶を無差別攻撃し、1万5,000人前後の市民も殺害しました。日本はこの時「焼夷弾」を使用。悪名高い「焼夷弾」を米国より先に日本が使用したとは知りませんでした(学校は東京大空襲は教えてもそんなことは教えない? というか教師も知らない?)。
日本の攻撃を受けても、重慶政府は、日本が敗戦するまで持ちこたえました(昭和21年5月1日、南京に遷都)。
日本は、国民政府の汪兆銘を重慶から脱出させ、南京に日本の傀儡政権(南京政府)を作り(昭和15年3月)、有利に和平に持ち込もうとしましたが(「東亜新秩序」(「大東亜共栄圏」の類)を提唱し日本の侵略を正当化しようとした)、うまくいきませんでした。
変わらずに重慶政府を支援する米英に対する悪感情が、日本をアジア太平洋戦争へと駆り立てていきます。
この時期、作家たちはどうしたでしょう?
近衛首相は計5師団を中国に送ることを決定した日(昭和12年7月11日)に新聞通信各社、13日には雑誌社の代表を招致し、国策への協力を要請しています。 雑誌社は作家を中国に派遣して現地の様子を書かせ「報告文学」としました。「中央公論」は石川達三、尾﨑士郎、林 房雄、「日本評論」は榊山 潤、「婦人之友」は吉屋信子、「改造」は立野信之、「文藝春秋」は岸田國士、小林秀雄、「東京日日新聞」は吉川英治を派遣。尾﨑は『悲風千里』で中国人に同情的に書き、また火野葦平の『麦と兵隊』(ベストセラーになった)も戦争賛美ではありませんでしたが、戦争そのものを批判する言説はなく、戦勝しか伝えない新聞報道と相まって、国民の戦争への肯定感(あるいは否定しない感)を強めるのに一定の役割を果たしました。
「盧溝橋事件」の翌年(昭和13年)の1月、石川達三が南京を訪れたときは、まだ虐殺が行なわれており、 石川は目撃したことを『生きている兵隊』(Amazon→)に書いて発表。ただちに発禁となり、懲役刑(執行猶予つき)をいい渡されます。石川に対する当局の仕打ちは、“いい見せしめ”になったことでしょう。
昭和13年8月23日、政府(内閣情報部)は、12名の作家と懇談し、出席作家は全員、作家の従軍に賛成。それを受けて、「ペン部隊」が結成されました(計22名)。
 |
| 「ぺン部隊」の面々。左より菊池 寛、小島政二郎、浜本 浩、北村小松、吉屋信子、吉川英治。羽田飛行場にて ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典 :『馬込文士村 ~あの頃、馬込は笑いに充ちていた~』(東京都大田区立郷土博物館)原典:日本近代文学館所蔵資料 |
同年(昭和13年)結成された 「農民文学懇話会」を皮切りに、文学の国策団体も次々にできます。昭和16年には、北原白秋と佐藤春夫が中心に「大日本詩人協会」が発足、他にも「文壇新体制準備委員会」「日本文学者会」「日本文芸中央会」「女流文学者会議」「日本俳句作家協会」「大日本歌人会」といった会ができます。昭和17年には情報局の指導で「日本文学報国会」(会長:徳富蘇峰)が結成、文壇全体を支配しました。作家たちは「身の潔白」(戦争に反対でない)を表明していったことでしょう。
そんな中、山本周五郎は陸軍からの要請を拒絶し続けました。周五郎は尾﨑士郎らから「曲軒」(へそ曲がり)とからかわれますが、そのぐらいでないと信念は貫けないのでしょうね。尾崎は「文学非力説」(文学は国民を決起されるには非力である)を主張した高見 順のことを弱虫扱いしました。
昭和13年には「国家総動員法」(企業に対するもの)ができ、翌昭和14年7月には「国民徴用令」(勅令相当)が公布され、徴兵とは別に作家も戦場に駆り出されるようになります。
矢内原忠雄は、「盧溝橋事件」の直後に「中央公論」に「国家の理想」を掲載。軍部の侵略的行為を批判し、同年(昭和12年)12月、東大を追われました(「矢内原事件」)。
 |
 |
| 『日中戦争(決定版)(新潮新書)』。著者:波多野澄雄、戸部良一、松元 崇、庄司潤一郎、川島 真 | 秦 郁彦『南京事件 〜「虐殺」の構造〜 (中公新書)』。日本軍の汚点・南京事件の実態に迫る |
 |
 |
| 前田哲男『戦略爆撃の思想 〜ゲルニカ・重慶・広島〜(新訂版)』(凱風社) | 吉野孝雄『文学報国会の時代』(河出書房新社)。作家たちの戦争加担 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→
・ 榊山 潤の『馬込文士村』を読む→
・ 吉屋信子の『花物語』を読む→
・ 北原白秋の『桐の花』を読む→
・ 山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→
■ 参考文献:
●『詳説 日本史研究』(編集:佐藤
■ 参考映像:
●「戦争のはじまり 重慶爆撃は何を招いたか(NNNドキュメント'17)」※「日本テレビ」で平成29年5月21日に放送
※当ページの最終修正年月日
2023.7.7