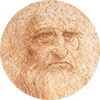| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
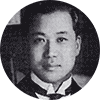 |
昭和22年1月15日(1947年。 映画館「帝都座」(デパート「新宿マルイ 本館」(東京都新宿区新宿三丁目30-13 Map→)あたりにあった)の5階小劇場で、「本邦初の本格的ヌードショウ」が催されました。敗戦から約1年半。これもまた新しい時代の1ページ。
「ヌードショウ」といっても、『ヴィナスの誕生』というヴァラエティショーのほんの一部で、長くても30秒ほど。名画に模して、額縁の前に上半身裸(薄い布で覆っていた)の女性が立つというもので「額縁ショウ」と呼ばれました。「これは芸術なので許してね」という作戦でしょうか?
このショーを企画したのが、当地にゆかりある秦 豊吉(55歳)です(昭和4-12年、東京都大田区山王一丁目に在住)。 東宝の社長を補佐した秦に、東宝が開設した「帝都座」の企画が一任されたのです。
 |
「額縁ショウ」の様子。定員の5倍の観客が押し寄せ、階段にまで長蛇の列ができ、ステージの端にまで押し出される人もいた。ショーには歌やコントやダンスもあったが、殿方のお目当てはやはりこれ? 。出典:『行動する異端 秦豊吉と丸木砂土』 (TBSブリタニカ) |
来歴をみると、秦の多面性が浮かび上がってきます。
帝大法科時代から独語習得に力を入れ、大学2年のとき訳したハウプトマンの『
ところが、大正6年(25歳)、帝大卒業後、三菱商事の社員になってあっさりと実業界に入ります。3年後(大正9年。28歳)にはドイツのベルリン勤務となりました。
翻訳も止めたわけではなく、昭和4年(37歳)にはレマルクの反戦小説『西部戦線異常なし』を翻訳。三菱商事の仕事をこなしながらなので、それこそ寝食を後回しにするような凄まじい生活だったようです。
翻訳にしても、実業にしても、どちらかといえば“お堅い”世界ですが、そこで活躍していた人が、「本邦初の本格的ヌードショウ」を企画したのです。
秦のベルリン滞在は6年半ほどでした。日本からの客を国際的な歓楽街に案内しているうちに色や芸能の世界にも相当詳しくなったようで、丸木砂土(マルキ・ド・サドのもじり)という名でその手の本を書くようになります。昭和6年発行の『女性西部戦線』 (NDL→)では、『西部戦線異常なし』にも出てくる「戦場での性」の問題を考察。
三菱商事を退社して東宝に転職したのが昭和8年、41歳の時です。
 |
 |
ゲーテ |
秦と一高で同期だった山本有三も、文学だけでなく、多方面で活躍しました。山本の行った教育は今からしても斬新なものでしたし、戦後は「国語の民主化」というかの時代の極めて
『ファウスト』(Amazon→)などの名作で知られるゲーテも、政治や自然科学の面でも成果を残しました。「探究しうるものを探究し尽くし、探究しえないものは静かに敬う」のが彼の信条でした。
 |
 |
|
平賀源内 |
レオナルド・ダ・ビンチ |
時代の要請といっても、狂歌三大家の一人・大田南畝が、突然、幕臣になったのは、切迫した政治的な理由からでしょう。
南畝と親交があった平賀源内も好奇心の塊で、長崎に遊学して、蘭学・医学・油絵・鉱山の採掘精錬技術を学び、湯島の聖堂に寄宿して儒学や漢学も学びました。学ぶだけでなく極めて実践的で、鉱床を発見・開発したり、産物や薬や絵暦の博覧会(展示会)を催し商品を広めたり、ブローカー的なこともやっています。エレキテル(静電気発生装置)を復元したことでも有名です。福内鬼外の名で浄瑠璃作家としても活躍しました。当地(東京都大田区)の新田神社にまつわる新田義興の伝承を脚色した『神霊矢口渡』が大ヒットし、当社の再興に寄与したとのこと。破魔矢は新田神社の依頼で源内が考案したとも言われています。
多才の人としてレオナルド・ダ・ビンチを落とすわけにはいきません。「モナリザ」や「最後の晩餐」といった絵画が有名ですが、彫刻家、科学者、技術者、哲学者としても高く評価されています。
 |
 |
北園克衛は詩人またはデザイナー・アーティストとして知られていますが、彼の名刺には「ライブラリアン(図書館員)」とありました。昭和10年(33歳)、「日本歯科大学」(東京都千代田区富士見一丁目9-20 Map→)の図書館に就職し、没年(昭和53年。75歳)まで勤め上げています。図書館長だったこともありました。食い扶持が確保できていたから、世に媚びることなく(売らんかなにならずに)、我が道を行けたのでしょうね。
宮沢賢治も、詩人・童話作家といった一面だけで語れる人ではありません。
様々な理由で、一時期、他の職業を掛け持った作家ならいくらでもいますが(夏目漱石、芥川龍之介、三島由紀夫、間宮茂輔など)、石坂洋次郎は15年近くも女学校・旧制中学校(教え子に「むのたけじ」がいる)の教師をしながら書いていたし、井上 靖も15年間くらい大阪毎日新聞社に務めながら書いていました。小関智弘さんなどは、51年間も旋盤工をしながら書いておられました。
世界的な指揮者のダニエル・ハーディングは年の半分はパイロットをやっているそうです、趣味ではなく仕事として。異なる仕事に関与することで、精神のバランスを取っているようです。
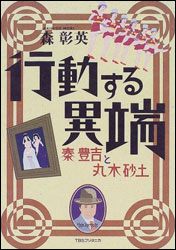 |
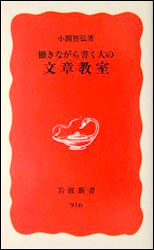 |
| 森 彰英『行動する異端 ~秦豊吉と丸木砂土~』(阪急コミュニケーションズ) | 小関智弘『働きながら書く人の文章教室 (岩波新書) 』 |
 |
 |
| スティーヴンスン『ジーキル博士とハイド氏 (岩波文庫) 』。善良な紳士のジーキル博士は、快楽追及のみに生きる凶暴なハイド氏でもあった。精神病理学的な多面性 | 平野啓一郎 『私とは何か〜「個人」から「分人」へ〜(講談社現代新書)』。「本当の自分」など存在しない。対人関係ごとに存在する様々な自分 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 『北園克衛詩集』を読む→
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
・ 間宮茂輔の『あらがね』を読む→
・ 石坂洋次郎の『海を見に行く』を読む→
・ 井上 靖の『氷壁』を読む→
・ 小関智弘の『大森界隈職人往来』を読む→
■ 参考文献:
●『行動する異端 ~秦 豊吉と丸木砂土~』(森 彰英 TBSブリタニカ 平成10年発行)P.7-16、P.39-45、P.65-69、P.131-137 ●『大田文学地図』(染谷孝哉 蒼海出版 昭和46年発行)P.120-121 ●『馬込文士村ガイドブック(改訂版)』(編・発行:東京都大田区立郷土博物館 平成8年発行)P.82 ●『山本有三(新潮日本文学アルバム)』(昭和61年発行)P.44-48、P.70-77 ●『カバンのなかの月夜 〜北園克衛の造型詩〜』(監修:金澤一志 国書刊行会 平成14年発行)P.130-133 ●「ハーディングはなぜパイロットになったか?(気分はカプリッチョ)」(城所孝吉)※「ぶらあぼ(令和5年12月号)」(ぶらあぼホールディングス)に収録
※当ページの最終修正年月日
2025.1.15