| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:ウィキペディア/新田義興(令和3年9月13日更新版)→ 原典:歌川国芳の浮世絵
 |
義興は、新田義貞の次男ですが、1337年、長男の
かたや、足利尊氏は鎌倉を奪還した後、1353年、北方の義興らを警戒して、鎌倉府を
義興が、弟の義宗、従兄弟の
そして10月10日、義興と12人の従者が、多摩川を東京都大田区側から神奈川県川崎側へ渡ろうという川中にあって、竹沢の息がかかった船頭が船底に仕掛けた穴の栓を抜き、船が沈みかかったところを、川崎側に潜んでいた江戸
謀られたと知ったときは、時すでに遅し。13人の最期を記す「太平記」の一節は凄まじいです。
さる程に、水、舟に
 |
 |
| 江戸時代に描かれた「太平記絵巻」の一部。義興謀殺の場面と、義興の怨霊が江戸遠江守を襲う場面が一続きになっている ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:Google Arts & Culture/太平記絵巻 巻第十→ |
 |
 |
| 義興を祀る「新田神社」(東京都大田区矢口一丁目21-23 Map→ Site→)の狛犬。謀殺した側の人間が近づくと唸るという。当社には義興を埋葬したという
|
13人の首を取った竹沢と江戸は、基氏や国清を喜ばせ、新たに所領を得ます。ところが、江戸が新たな所領に向かう途中「矢口の渡し」近くに来ると、額に角のある馬に乗った義興の
『太平記』は、後醍醐天皇の即位(1318年)あたりから、
鎌倉幕府が滅ぼされ後醍醐天皇の新政となるものの直ぐに鎌倉幕府を滅ぼした同士の新田と足利が対立、足利幕府が成立して朝廷が南北に分裂するといった血で血を洗う乱世をへて、ようやく「太平」の兆しが見えたところで物語は閉じます。第21巻で後醍醐天皇が没すると(1339年)、その後、物語に怨霊がたくさん登場するようになります。かつて白河院が天下泰平を祈願して建立した
「怨霊」は、権力者サイドが
 |
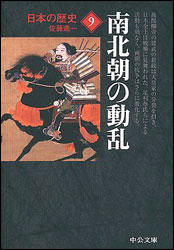 |
| 『太平記(新潮古典文学アルバム)』。著:島田雅彦、大森
|
佐藤進一『南北朝の動乱(中公文庫)』。南北に分かれた朝廷のそれぞれを担ぐ勢力同士が絶え間なくぶつかり合う。楠木正成ら「悪党」(旧勢力側からの呼称)や佐々木道誉らサバラ大名などの新興勢力も入り乱れ |
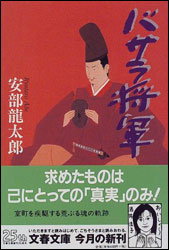 |
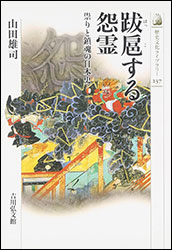 |
| 安部龍太郎『バサラ将軍 (文春文庫)』。収録作「知謀の淵」は、義興の謀殺を竹沢 右京亮の視点で書かれている。著者が当地(東京都大田区)の図書館職員だった頃、館報の記事執筆のための取材中、小説化を思い立ったという。初出は役所の文芸誌。著者の原点の一作 | 山田雄司『跋扈する怨霊 〜祟りと鎮魂の日本史〜』(吉川弘文館)。不運な生涯をたどり、あるいは非業の死を遂げた長屋王、早良親王、菅原道真、崇徳院、平家の人たち、後醍醐天皇らの“怨霊”がいかに恐れられ、いかに鎮魂されたか。「怨霊伝説」から読み取る「敗者の歴史」 |
■ 参考文献:
●「新田義興の憤死とその背景」(新倉善之) ※『大田区史(上巻)』(東京都大田区 昭和60年発行)P.724-746 ●『太平記(新潮古典文学アルバム)』(島田雅彦、大森北義 平成2年発行)P.2-8、P.38-39、P.60、P.62-63、P.66-67、P.70-73、P.108-109 ●『大田区の史跡散歩(東京史跡ガイド 11)』(新倉善之 学生社 昭和53年発行)P.113-124 ●「太平記」(釜田喜三郎)※『新潮 日本文学小辞典』(昭和43年初版発行 昭和51年発行6刷)に収録 ●「師直まで(文庫版あとがき)」※『バサラ将軍(文春文庫)』(安部龍太郎 平成10年初版発行 平成25年発行2刷)に収録 ●新田神社内の案内板 ●「平賀源内が書いた人形浄瑠璃は歌舞伎『神霊矢口渡』となる」(樋口和則)(馬込と大田区の歴史を保存する会→) ●「頓兵衛地蔵」(日本伝承大鑑→)
※当ページの最終修正年月日
2024.10.10