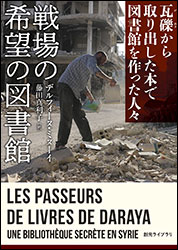| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
昭和31年6月1日(1956年。 当地で初めての公立図書館、「池上図書館」(東京都大田区池上三丁目27-6 Map→)が開館しました。最初は、区民会舘の屋上に4階部分を増築して、図書室にしたそうです。現在は、東急池上線「池上駅」直結の商業施設「エトモ池上」(東京都大田区池上六丁目3-10 Map→)の4階にあります。
「図書館令」が明治32年に公布され、日本にも公立図書館が設置されるようになりますが、閲覧料の徴収が許可されていたり、国策に不都合な図書が排除されたり、利用者が調査されたり、と民主的なものではありませんでした。戦時中は、不要不急の施設として軍需工場などに転用されたり、空襲で焼けたり。
敗戦後1年した昭和21年「日本国憲法」が広布され、その理念に基づいて「教育基本法」が定められ、その精神に則って「社会教育法」ができ(昭和24年)、それを受けて「図書館法」ができ(昭和25年)、全国各地に公立図書館ができていきます。大田区の図書館設置は「図書館法」施行の6年後と出遅れましたが、本棚の本を利用者が自由に手に取れる
「池上図書館」開館の4年後(昭和35年)には「洗足池図書館」(大田区南千束二丁目2-10 Map→)と「蒲田図書館」(大田区東蒲田一丁目19-22 Map→)が開館し、計3館となります。「洗足池図書館」は、来館した国際ユネスコ図書館委員長のD・W・ブライアントが、その開架式書棚、355席もの閲覧指定席、子ども向けスペースなどに注目、図書館の国際的なセミナーで“日本の代表的図書館”と紹介し有名になりました。
大田区は、その後も図書館を着々と増やし、昭和49年には、「歩いて15分以内のところに1館を設ける計15館計画」ができ、昭和61年の「大森西図書館(大田区大森西五丁目2-13 Map→)の開館をもって目標を達成。その後も2館増やして、令和5年現在で18館あります(そのうち「大田文化の森情報館」は図書館類似施設。「田園調布せせらぎ館」は蔵書はなく、予約・受取・返却、レファレンスなどが可能)。
17の図書館にはそれぞれ、力を入れている分野、特色、歴史があります。一部紹介します。
中国・韓国・朝鮮語の図書が豊富。中国語・韓国語コーナーもある
タイムリーな興味深いテーマで本を紹介しているコーナーが秀逸
当地の作家の本を収集した「馬込文士村資料室」(大田区立図書館/特殊コレクション/馬込文士村資料→)がある。個々の作家をとりあげ、定期的に展示・紹介している。城 昌幸の蔵書を保管した「城 昌幸記念文庫」もある
地元に関する特別展示がされる。今までに「池上本門寺歴史展」「池上線のルーツを探る」「池上と文学」「西郷・勝会見 その池上説に迫る」といった展示があった。資料を並べるだけでなく、館独自の考察もなされていた
勝 海舟のコーナーがある。館の近くに、勝 海舟の別荘跡、墓、「勝 海舟記念館」(東京都大田区南千束二丁目3-1 Map→ Site→)がある
大森貝塚の発見者として知られるモースの故郷・米国マサチューセッツ州セーラム(Map→)のコーナーがある。大田区とセーラムとは姉妹都市の関係を結んでいる
ここの職員だった安部龍太郎さんは、33歳で石川県七尾から京に出て本格的な絵師を志した長谷川等伯に、29歳で図書館職員(大田区役所職員)を辞めて作家として立つ決意をした自身の姿を重ね合わせて、『等伯』(平成25年度直木賞受賞作)を書かれたようだ
大田区蒲田出身のジャズ・アルトサックス奏者・矢野沙織さん(第22回「日本ゴールドディスク大賞」を 受賞)も利用されていた。小学校6年の時、当館でCD『ジャコ・パストリアスの肖像』(Amazon→)を借り、その中の「Donna Lee」(YouTube→)(原曲(YouTube→)はチャーリー・パーカー・オールスターズ)を聴いてジャズに目覚める。図書館が人生を変えることも
区内18館の資料は、閉架図書を含め一括してネット検索して予約でき、一番近くの図書館で受取・返却ができるのでとても便利です。一度に図書・雑誌は12冊まで、CDなどの視聴覚資料は6点まで、2週間(他に予約が入っていなければさらに2週間延長できる)借りることができます。DVDも充実してきました。
 |
 |
 |
当地(東京都大田区)の公立図書館の第一号「池上図書館」設立以前より私立の「嶺町図書館」がありました。また、昭和27年、『赤毛のアン』の翻訳者として知られる村岡花子(58歳)が自宅(大田区中央三丁目12-4 Map→)に「道雄文庫ライブラリー」(「道雄」とは、5歳でなくなった村岡の長男の名)を設け、近所の子に開放していました。村岡が目を患って入院したのを機に昭和42年(村岡74歳)閉鎖、蔵書は入新井第二小学校(Map→)と入新井第四小学校(Map→)に400冊ずつ寄贈されたとのこと。
山本有三は当地(東京都大田区山王三丁目)に住む前、三鷹に住んでいました(現在「三鷹市山本有三記念館」(東京都三鷹市下連雀二丁目12-27 Map→ Site→)になっている)。そこで、昭和17年(山本55歳)、私設図書室「ミタカ少国民文庫」を開設、本の乏しい戦時下にあって近所の子どもたちに蔵書を解放しました。
北園克衛の本業は詩人でなく、デザイナーでもなく、図書館の職員でした!
平成19年より、大田区立図書館でも指定管理者制度が導入されて、経営に競争原理が持ち込まれました。その影響か、利用者に対する職員の対応は格段に良くなったように思います。が、危惧されるのは、区が管理者をどう評価するかです。その評価の仕方によっては、図書館の質が大きく低下する可能性があります。来館者数や貸出数の多少が重視されれば、管理者はポピュラーな本ばかり図書館に入れるようになるかもしれません。固定的でない複数の学識者による蔵書チェックが頻繁に行われるべきでしょう。管理者の力量は、司書資格を持つ人の人数や、どのような本をどう配列しているかに明瞭に表れていることでしょう。(参考サイト:Business Journal/ツタヤ図書館、問題多発させた「企業体質」 ただのカフェ併設大型店、関連会社の在庫処分…→)
 |
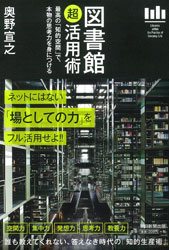 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 城 左門の『怪奇製造人』を読む→
・『北園克衛詩集』を読む→
■ 参考文献:
●「区民のための図書館網」(川城三千雄)※『大田区史(下)』(東京都大田区 平成8年発行)P.841-843 ●『アンのゆりかご ~村岡花子の生涯〜』(村岡恵理 マガジンハウス 平成20年発行)P.271-278 ●「わがまち 新井宿」(平成26年4月1日発行)●『山本有三(新潮日本文学アルバム)』(昭和61年発行)P.48 ●『カバンのなかの月夜 〜北園克衛の造型詩〜』(監修:金澤一志 国書刊行会 平成14年発行)P.130 ●「矢野沙織4@大田区アプリコホール」(syoukopapa)(ユウ君パパのJAZZ三昧日記→)
※当ページの最終修正年月日
2023.5.31