| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和24年2月28日(1949年。 芦田 均(61歳)が日記に、
・・・毎日新聞の“余録”に興味ある一節がある。「日本研究家のルース女史が書いたことに(菊と刀の中に)『日本人は善悪醜美の判断を自分の信念できめず、世間がどうみるかといふことを標準にして行動する国民だ』と言つてゐる。実際そう言はれても仕方がない位、吾々はこれ迄『自主性』に乏しかった嫌がある」とある。
私は今度の疑獄事件にぶつつかつて、全く自己の信念で行動した。然し世間はやはり低級なヂャーナリズムに引づられて私の行動を了解してゐない。私は矢張りもつと強く信念に生きなければならぬ。・・・
と書いています。ルース・ベネディクトの『菊と刀』にある言葉に接し、日本人は、自らの自主的な判断で行動を決めず、「世間がどうみるか」を基準にして行動する傾向があるようなので、そうならないよう、改めて自分の信念に生きようと意を強くしたようです。芦田は前年(昭和23年)に首相を務めましたが、疑獄事件に巻き込まれ、この時点でもまだ被告として裁判にかけられていました。
たしかに今でも、多くの日本人が、「世間がどうみるか」を基準にし、周りから奇異に思われないよう自らの言動を選択しているようです。「前の日と違う服を着るのは恥ずかしい」という“常識”は、おそらく服飾業界が流布させたものに過ぎないのでしょうが、皆がそうしているのなら、「皆と同じ自分」であるように自分もそうする。
なぜ、日本人はそういった傾向を強く持つようになったのでしょう?
まず考えられるのが、農耕文化。かつての農業は、村落が一体になって作業にあたる必要があったので、「村」の統一を乱す「異論」は忌避され、その心性が、日本人のものの考え方に大きく影響したことでしょう。
そして、一つの作業を統一的に遂行するには命令系統が確立されている必要があり、上下関係が尊重されるようになったのでしょう。「下」の者が「上」の者に意見するなどは論外で(たとえそれが正論であっても)、知らず知らず、人々は自分の考えで動くのではなく、「上」の者(あるいは、「上」の者にも匹敵する影響力をもつ「世間」や「立場」)を自らの行動原理として採用していくのが生きやすいという結論に達していったのでしょう。明治以降の国民皆兵(徴兵制)も、兵隊を育てるために整備された学制(「前へならえ」「右向け右」「休め」といった号令にその名残が)も、上意下達を徹底させる装置になりました。天皇制を利用した「国民操縦」の呪縛は強烈で、今もそれに囚われている人もいることでしょう。「出版法」「新聞紙法」といった天下の悪法も「「上」に意見するな」の心性を日本人に刷り込み、物言わぬ日本人を形成していったことでしょう。こういったことを考えると、明治時代は、“坂の上の雲”を目指して歩んだ明るい時代なんかじゃありませんね。
 |
上記のことは、乗り越えていかなくてはならない日本人の心性ですが、大切にしたい、または理解し今に生かしていきたい日本古来の感覚や価値もあります。例えば、「
垢抜けた姿態を崩して客に秋波を送りつつも、金にモノを言わせる客などはぴしゃりと拒絶する芸者などに見られる「粋」や、もの静かな風情を尊ぶ「侘」「寂」。「侘」「寂」から派生した「欠けたものに美を見出す感性」や「簡素なもので高度な美を表現する象徴性」、また、天国や極楽浄土といった妄想を捨て(「莫妄想」。極楽浄土を釈尊(実在したゴータマ・シッダッタ)は説いていない)、目の前の世界(大地)に根ざし(「大地性」)、分別(絶対性)を廃して無分別(無知)を受け入れて安心を得るといった「無分別智」(キリスト教の「原罪」にも通じる)。これらは、高度経済成長やバブル期の名残なのか「イケイケ」体質がいまだ残存する日本社会が見直し、取り戻したい価値観ですね。
 |
日本人の世界観に「中空構造」があるという興味深い指摘もあります。西洋では、「正」があって、それに対する「反」が生まれ、2者がぶつかり合って一つ高い段階に到達する(止揚する)という考え方(弁証法)が主流ですが、日本では最初から3者存在し、その中心が「中空」になっていて、両端を橋渡してバランスを取っているというのです。「中空構図」がぶつかり合う両者を「まあまあ」となだめる役を果たす一方、事が起きた時の責任の所在が曖昧になる原因にもなるようです。「空中構造」(空、無、中心がない構造)に直感的に価値を置く心性が、絵画や書・造園などに「余白」を、演劇(能や歌舞伎など)や茶道的所作に「間」を取り入れ、洗練させていったのかもしれません。
「祖先が子孫を思っているという民間信仰」を日本人の心性の特徴とする人がいるかもしれませんが、それはどうでしょう。確固とした一神教的な「神」を強く意識している人以外は、万国共通して、自分を受け入れ(愛し)、あるいは導いてくれた死者に人は語りかけようとするものではないでしょうか?
嘆かわしいのは、本屋で、こういった日本人論と、海外ヘイト本が、同じカテゴリーにされることが多いこと。日本人の独自性を語ることで、相対的に、海外の文化や人を貶めようとする人がまだいるようです。本屋もその方策に一枚噛んでいるようなのがなんとも。
 |
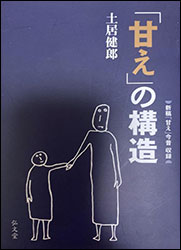 |
| ルース・ベネディクト『菊と刀(講談社学術文庫) 』。訳:長谷川松治 | 土居健郎『「甘え」の構造』(弘文堂)。「甘え」という観点から見た日本人 |
 |
 |
| 九鬼周造『「いき」の構造(岩波文庫)』。「粋だねぇ」とよく言われるが、「粋」とはいったいどういうものか? 媚態、意気地(独立性)、諦めなどの観点から紐解く | 鈴木大拙『日本的霊性(完全版)(角川ソフィア文庫)』 。貴族のために存在した仏教が、鎌倉時代に民衆や武士に浸透、日本人の心性を象った |
■ 参考文献:
●『芦田 均日記(第五巻)』(岩波書店 昭和61年発行)P.255-258 ●『最後のリベラリスト・芦田 均』(宮野
■ 参考映像:
●「日本人論(100分de名著)」(コメンテーター:松岡正剛、赤坂真理、斎藤 環、中沢新一 MC:伊集院 光、武内陶子 NHK Eテレ 平成27年放送)
※当ページの最終修正年月日
2025.2.28