| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
文応元年7月16日(1260年。
日蓮(38歳)が、鎌倉幕府の北条時頼(33歳。5代執権。4年前(1256年)に執権の座を義兄の北条長時に譲るが、変わらず実権を握っていた)に『
旅人と草庵の主(日蓮のこと)との対話の形で、世の中が悲惨な状態なのは(前年(1259年)から全国的な飢饉となり、疫病も流行していた)、人々が「間違った仏教」を信仰しているからと指摘。日蓮に言わせると、釈迦の総決算的な教典『法華経』を最重要視しない浄土宗、禅宗、真言宗、律宗といった既存の各派は、全部ダメなのでした。日蓮の他宗派非難は「
仏教各派にはそれなりの堕落や増長もあったのかもしれませんが、それにしても、「大罪」「地獄に堕ちる」「天魔の所行」と全否定され、さらにはその禁止を権力者(幕府)に直訴したのですから、たまったものではありません。以後日蓮は、仏教各派や権力者(幕府)と対立します。
日蓮は承久3年(1222年)、今の千葉県鴨川市小湊(Map→)に生まれ、11歳頃(1233年)、近くの
辻説法でも他宗批判をしたでしょうし、上記のごとく『立正安国論』の幕府への提出に至って、他宗信者や幕府の怒りはマックスに達し、その後、日蓮は、「松葉ヶ谷法難」を皮切りに、幕府によって伊豆へ流罪となり(「伊豆法難」)、千葉鴨川近くで念仏信者の武士に襲われ(「小松原法難」)、神奈川県藤沢の龍口寺あたりで処刑されそうになり(「
 |
 |
| 日蓮が草庵を結んだとされる場所に建つ妙法寺(鎌倉市大町四丁目7-4 Map→ Facebook→)の名物「苔むす階段」。階段の先に(途中から苔の階段は通行禁止なので回り込む)草庵跡(Photo→)がある | その名も安国論寺(妙法寺の近く。鎌倉市大町四丁目4-18 Map→ Site→)の南面窟。松葉ヶ谷法難のおり、日蓮は白猿に導かれてこの洞窟に避難したという。参考サイト:旅する鎌倉/恐怖の山道 安国論寺→ |
佐渡島への流刑をへて、山梨県の身延に隠棲、その後、病を得て、治療のために下山。その道すがら、当地(東京都大田区)で没しました。享年満60歳です(1282年)。
このように、日蓮の生涯は、挑戦と苦難の連続でしたが、それを生き抜いた勇敢さとパワフルさと不屈の精神に共鳴して、信者が増え、現在に至ります。
日蓮だけでなく、平安時代末期から鎌倉時代中期にかけて、仏教に新風を吹かせた異才が各地に続々と出現、画期的なことでした。この時期に興った宗派を、鎌倉仏教(鎌倉新仏教)と呼びます。
 |
 |
法然 |
親鸞 |
日蓮は、「南無妙法蓮華経」(お題目。(蓮華経)という「素晴らしい教え」(妙法)に「帰依します」(南無))を繰り返し唱えることを推奨しましたが、日蓮以前に(安元元年。1175年頃から)、「南無阿弥陀仏」((阿弥陀仏)に「帰依します」(南無))を繰り返し唱えること(念仏)を推奨したのが法然です。親鸞は法然の考え・精神を継承・発展させました。
貴族社会が崩壊する過程で、ネガティブな末法思想(仏教の教えが衰退し、世の中が乱れていくという予言的言説)が流布します。現に、災害が多発し、武士の台頭に伴い治安も悪化、人々の不安が増大していました。そんな中、法然、親鸞、日蓮は、短い聖句を繰り返し唱える(専修する)ことで、誰しもが、容易に救いに至れる道を示し、多くの人に希望を与えたのです。
禅宗は、500年代、インドの達磨(「ダルマさん」は達磨の「面壁九年」(壁に向かって9年間座禅して悟りを得たという伝説)の姿を象ったもの)が開宗し、中国で発展しましたが(中国の仏教はみな禅宗を名のる)、その五家七宗のうち、曹洞宗、臨済宗が、鎌倉時代に日本に伝わり独自の発展を遂げました。
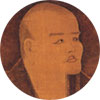 |
道元 |
曹洞宗を伝えたのが道元です。道元は、13歳で出家し、24歳で中国(宋)に渡り、帰国後、それを伝えました。ただし、道元は、曹洞宗という名に限定されることを嫌い、「正伝全一の仏法」としてそれを伝えています。
禅宗では、ひたすら座禅して悟りに達する方法を示しました(
「言語の不十分さを認識している道元」から発せられた言葉は、むしろ含蓄に富み、文学の域に達しています。ノーベル文学賞を受賞した川端康成が、その受賞記念講演(演題「美しい日本の私」)で開口一番に紹介したのが、道元の歌でした。
春は花
夏ほととぎす
秋は月
冬雪さえて
雪がさえて「冷し」(涼しい。心地よい)と言っています。
 |
忍性 |
日蓮の宿敵(?)の忍性も、鎌倉時代に燦然と輝いた異才ですね。
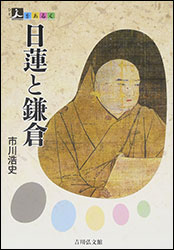 |
 |
| 市川浩史『日蓮と鎌倉 (人をあるく)』(吉川弘文館) | 平岡 聡『鎌倉仏教 (角川選書)』 |
 |
 |
| 吉本隆明『今に生きる親鸞(講談社+α新書)』 | 道元『 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 川口松太郎の『日蓮』を読む→
・ 川端康成の『雪国』を読む→
■ 参考文献:
●「『立正安国論』 抄訳・解説」(小松邦彰)、「日蓮の独自性」(正木 晃 )※「大法輪」(大法輪閣 平成21年8月号)に収録 ●「鎌倉の日蓮をめぐる三つの日付」(寺尾英智)、「関連年表」※『特別展 鎌倉の日蓮聖人 〜中世人の信仰世界〜』(編集:神奈川県立歴史博物館 平成21年発行)に収録 ●「鎌倉仏教」※「百科事典マイペディア」(平凡社)(コトバンク→) ●「浄土宗」(末木文美士)※「日本大百科全書(ニッポニカ) 」(小学館)に収録(コトバンク→) ●「禅宗」(柳田聖山)※「日本大百科全書(ニッポニカ) 」(小学館)に収録(コトバンク→)
※当ページの最終修正年月日
2023.7.16