| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
鑑真 |
仏典は、師から弟子に口承されるもので、師から戒律を受けること(受戒)によって初めて僧侶になることができます。中国の高僧・鑑真からの受戒はたいへん栄誉ことだったでしょう。鑑真は、翌年(754年)の正月にかけて、聖武天皇(45代)、孝謙天皇(46代)をはじめ、僧侶・尼僧など400名に授戒しました。
仏教が、西域・中国・朝鮮半島を経由して日本に伝わったのは、鑑真来日の250年以上も前(400年代)と推測されていますが、公式には、百済の聖明王から欽明天皇(29代)に、釈迦像と経論が送られた538年(もしくは552年。どちらも定かでない)に伝来したとされます。
 |
ブッダ |
仏教の起こりは、さらに、1,000年ほど遡ります。
紀元前463年(異説あり。弥生時代)、コーサラ国のカピラヴァストを都とする王国(ネパールとインドの国境近くにあった。現・ネパール)に、ゴータマ・シッダッタというシャカ族の王子が生まれました。ゴータマは恵まれた生活を送っていましたが、人生の苦悩(四苦(生老病死))に思い至り、その解決を志すようになります。妻子を捨てて出家、6年間の苦行の末に悟りを得て、ブッダの自覚を持ちました。その後ゴータマが説教したものが仏教です。
ブッダは漢字で仏陀と書き、「真理に目覚めた者」の意味です。仏教ではゴータマと同様、ブッダになること(成仏)を目指します。
ゴータマ・シッダッタのことは、「釈迦」(シャカ族の人)、「釈尊」(シャカ族の尊ばれる人)、また、ブッダを代表して単に「ブッダ」(仏陀)とも呼ばれますが、「真理に目覚めた者」複数を「ブッダ」(仏陀)、歴史上の人物・ゴータマ・シッダッタを「釈尊」と区別すると分かりやすいかもしれません。
釈尊も旧来のバラモン教(釈尊が生まれるさらに1,000年ほど前(紀元前1,500年頃)、インドに侵入したアーリア人がカースト制度とともにもたらした宗教。現在ではヒンズー教がその伝統を継ぐ)の影響を受けましたが、仏教にはバラモン教と違ったどういった独自性があるのでしょう?
1つは、「無我説」。バラモン教では、永遠不変で絶対的な宇宙の根本原理「ブラフマン」(梵)と個人存在の本体「アートマン」(我)は1つであり(「
もう1つは、「縁起説」。「ブラフマン」(梵)も「アートマン」(我)も絶対不変でないならば、さまざまな物や現象は、どう生じ、どう存在するというのでしょう。仏教では、さまざまな物や現象が、ある原因(縁)があって生じるとしたのです(「縁起説」)。「アートマン」(我)はその行為(業)という理由(縁)よって性格が規定されます。生まれによって身分が固定されるカースト制度を釈尊が厳しく批判した
仏教では、「縁起説」によって固定的な「アートマン」(我)から自由になって、世の苦しみや悩みの原因(縁)を知ってそれを超克し、釈尊が定めた戒律にしたがって生きることで「ブッダ」(仏陀。真理に目覚めた者)になることを目指します。
 |
釈尊は、ガンジス川流域で、45年間説教につとめた後、紀元前383年頃(異説あり)、85歳で死去(入滅)します。
釈尊の死後、弟子たちが釈尊から聞いた話を書き留め「お経」(経典)が誕生します。釈尊の死後100年ほどすると、戒律の解釈の違いなどから教団内に分裂が生じました。
釈尊の死後400年ほどすると(紀元前後)、旧来の自らの悟りを目指す仏教を「小乗仏教」と呼んで批判し、自分だけでなく世間の人々(衆生)の悟りをも目指す「大乗仏教」の運動が起こります。「大乗仏教」の修行者たちは一般の在家の信者と一緒に暮らしていたため、そのような考えになっていったようです。新たに「般若経」「法華経」といったお経が編まれ、菩薩(利他行(衆生を救うこと)に励む修行者)が慕われ、如来(「ブッダ」(真理に目覚めた者)の別称。阿弥陀如来(極楽浄土に住む)、薬師如来(瑠璃光世界に住む)など)を想定、それらも崇拝されるようになりました。
600年代になると、「密教」が生まれます。大乗仏教で教えが全ての人に開かれた結果、敷居が下がり、悟りのありがたみが少なくなったからなのでしょうか、密教では再び「言葉では表せない神秘的な体験」を経た者だけが悟れるという教えに揺れ戻りました(とは言え、密教も大乗仏教の1つに数えられている)。バラモン教の影響があったようです。「密教」は700年代に中国に伝わり、800年代はじめに空海らによって日本にも伝わりました。
以上のように、日本の仏教は、中国を経由して(または、朝鮮半島を経由して)伝わった「中国仏教」です。中国仏教は、道教の不老不死思想や、儒教の「孝」の思想を色濃く反映しています。
インドから中国へは、紀元67年、
漢訳仏典は、中国、朝鮮、日本の共通テキストであり、東アジア融和のシンボルといえるでしょう。
鎌倉時代になると、中国仏教を土台に、日本で独自に新解釈を加えた新仏教が誕生します。
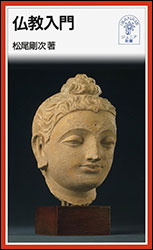 |
 |
| 松尾剛次『仏教入門(岩波ジュニア新書) | 清水俊史『ブッダという男 〜初期仏典を読みとく〜(ちくま新書)』 |
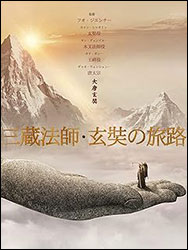 |
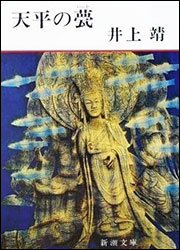 |
| 『三蔵法師・玄奘の旅路」。中国長安からインドへ、仏典を求めて旅立った玄奘(三蔵法師)。その壮絶な生涯。監督:フオ・ジエンチー、出演:黄 暁明(ホァン・シャオミン)ほか | 井上 靖『天平の甍(新潮文庫) 』。遣唐使として大陸に渡った5人の学僧たちの運命。在唐20年の歳月の末、鑑真を伴って帰国できたのは普照ただ一人だった |
■ 馬込文学マラソン:
・ 井上 靖の『氷壁』を読む→
■ 参考文献:
●「隼人たちが駆けた海原・薩摩半島南部」(九州国立博物館振興財団→) ●「仏教伝来」※「山川 日本史小辞典(改訂新版)」に収録(コトバンク→) ●『ブッダという男 〜初期仏典を読みとく〜』(清水俊史 令和5年初版発行 令和6年発行4刷)P.12、P.18-19、P.21-22、P.27 ●「ブッダ」※「山川 日本史小辞典(改訂新版)」に収録(コトバンク→) ●『仏教入門(岩波ジュニア新書)』(松尾
※当ページの最終修正年月日
2024.12.25