| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
大正10年12月3日(1921年。
宮沢賢治(25歳)が、「(岩手県立)花巻農学校」(当時「(
賢治は、6年前(大正4年。18歳)、「盛岡高等農林学校」(現・「岩手大学農学部」(岩手県盛岡市上田三丁目18-8 Map→ Site→))に首席で入学、関 豊太郎教授について地質や土性の調査に携わりました。大正7年(21歳)、論文「腐植質中ノ無機成分ノ植物ニ対スル価値」が認められ、その後2年間の研究課程も修了、関教授から助教授の推薦があります。それを辞退して「花巻農学校」の教師になったのでした。研究職ではなく、農業従事者により近い教育機関を選んだのでした。就職するまでの約1年半は、国柱会で宗教活動をし、童話も猛然と書きました。賢治にとって「生きること」は、「宗教」「労働」「表現」と不可分でした。
岩手県は、寒く、単作しかできず、しかも米穀生産に限られていました。「やませ」(春から夏にかけて太平洋から吹く冷たく湿った風)の影響で、しばしば米の凶作となりました。賢治はこの状態の克服を目指します。「花巻農学校」では、理想を高らかに掲げ、教え子たちに帰農を勧めています。自身も、大正15年(29歳)退職し、実家から1.5kmほど離れた実家の別宅に独居し、そこに「
・・・すべての農業労働を
冷く透明な解(析)によって
その藍いろの影といっしょに
舞踏の範囲に高めよ・・・
(「花巻農学校」の教え子にあてたとされる賢治の詩)
その頃賢治は「農民芸術概論綱要」( Amazon→ 青空文庫→)を書き、「羅須地人協会」での教材にしています。
・・・
乏しいながら
そこには芸術も宗教もあった
いまわれらにはただ労働が
生存があるばかりである・・・(中略)・・・
いまやわれらは新たに正しき道を行き
われらの美をば創らねばならぬ
芸術をもてあの灰色の労働を燃せ
ここにはわれら不断の潔く楽しい創造がある・・・(宮沢賢治「農民芸術概論綱要」より)
芸術と宗教が芸術家と宗教家の独占物になっている、それらを我らの手に取り戻そうと賢治は訴えました。
「羅須地人協会」には教え子を中心に近くの若い農業従事者が集い、開墾や栽培をするだけでなく、勉強会(土壌学、植物生理学、肥料学、エスペラント語、芸術論などの)、レコード鑑賞会、合奏練習などが催されました。賢治は農家に出向いて肥料相談・稲作指導にも奔走、子どもへの自作童話の読み聞かせもしています。農閑期の工芸品作製、本やレコードや農具のバザー、種苗の交換も予定されていました。
 |
 |
| 「花巻農業高等学校」に復元された「羅須地人協会」の建物。妹のトシが療養していた家。写真:S・Fumiho | 「羅須地人協会」の集会場も復元されている。農村の理想を熱く語る賢治の姿が目に浮かぶ 写真:S・Fumiho |
「羅須地人協会」で必要な知識や技能を仕入れるために、大正15年(30歳)再上京。
年が明けて昭和2年、「羅須地人協会」の活動が「岩手日報」で報じられ、治安当局の目にとまるところとなります。賢治は花巻警察の取り調べを受けました。お上からのお達しにハイハイと従う臣民が推奨されていたので、労働者が主体性を持つなど「けしからん」だったのでしょう。「羅須地人協会」はわずか7ヶ月間ほどで活動停止に追い込まれました。
今、日本の農業はどうなっているでしょう?
昭和22年、GHQ主導で、貧富の差を生み出してきた地主制度(小作制度)が解体され、また、農業従事者や農業研究家の絶え間ない努力と研鑽によって(品種改良、肥料の進歩、農業機械や農薬の導入など)、米は同一面積から戦前の約2倍の収穫が可能になります。そして、昭和40年代、元のように米の自給ができるようになりました。
しかし同時期、米国と米国追随の役人・政治家が進めてきた「米偏重の是正政策」(つまりは、日本を米国の余剰農産物の処分地にする政策)により、国民の米離れが加速。今度は米が余り始め、減反政策によって休耕田が増えていきます。国は、農産物の買取制度(価格支持政策)、関税や補助金による保護で農家を守ってきましたが、それらも半ば放棄。今や、人を殺したり脅したりする道具には毎年10兆円以上支出するのに、農水予算はなんとその1/4にも満たない2.3兆円が上限とされてしまいました。生活が成り立たず(米の買取価格よりコストが上回る)、廃業する農家が増え、 今や(平成30年)、農業の国内総生産は全産業の1%ほどしかありません。日本の食料自給率は38%(平成28年。カロリーベース。実質は10%とも)まで落ち込み、食料の安全保障の面でも大問題です(他国から経済制裁されたら餓死者が出る)。
主要作物(米、小麦、大豆など)の優良種子を安定的に供給するための「種子法」がありましたが、民間企業の種子開発を阻害するとの理由で強引に廃止(平成29年。安倍政権下)。大手の多国籍企業が商売に向いた品種に限定して独占的に販売することが懸念され、そうなれば品種の多様性が損なわれ、地域や個々の農家の創造性も阻害されることでしょう。また、品種の国内外への流出を防ぐための「
農業政策を本道に戻すことが何よりも必要です。米国べったりで利権まみれの今の政権では到底無理なので、選挙に行って、状況を変える必要があります。状況が変われば、徐々に、賢明な若者が、地球を壊すだけの虚業(虚しい仕事)などには見向きせずに、エッセンシャルな(本質的で、カッコいい)仕事「農業」に戻ってくることでしょう。
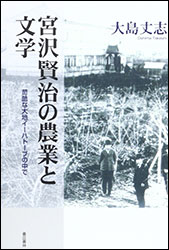 |
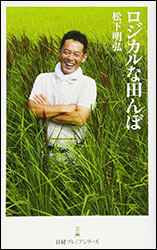 |
| 大島丈志『宮沢賢治の農業と文学 〜苛酷な大地イーハトーブの中で〜』(蒼丘書林) | 松下明弘『ロジカルな田んぼ 』(日経BP)。有機・無農薬での米作り! |
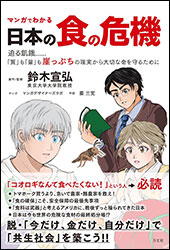 |
 |
| 『マンガでわかる 日本の食の危機 〜迫る飢餓/「質」も「量」も崖っぷちの現実から大切な命を守るために』(方丈社)。半農半漁の家に生まれ、農林水産官僚もへた鈴木 |
『地域を支える農協 〜協同のセーフティネットを創る〜』(コモンズ)。編著:高橋 巌。「今だけ、金だけ、自分だけ」の輩に抗うための、共助・共生の精神。政府やマスメディアが農協を攻撃する理由も分かる? |
■ 参考文献:
●『宮沢賢治(新潮日本文学アルバム)』(昭和59年初版発行 昭和61年発行5刷)P.18-23、P.65-83、P.105-107(評伝・年譜・編集:天沢退二郎) ●『宮沢賢治の農業と文学 〜過酷な大地イーハトーブの中で』(大島丈志 青丘書林 平成25年発行)P.8-14 ●『日本の食の危機』(鈴木宣弘 方丈社 令和5年発行)P.21-23、P.67、P.73-79、P.95、P.103-104 ●「食料自給率(「大図解シリーズ」No.1328)」(
※当ページの最終修正年月日
2023.12.2