| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
大正10年8月25日(1921年。 宮沢賢治(24歳)が 『かしはばやしの夜』(青空文庫→) を書き上げました。妹のトシの病状悪化の知らせを受けて、8ヶ月間の東京本郷菊坂滞在を切り上げて帰郷した頃です。
前年の10月(大正9年。24歳)、法華宗系の在家仏教団体「国柱会」に入会した賢治は、菊坂時代、同会理事の
鋤鍬をとるものはその鋤鍬の上に、ペンをとるものはそのペンのさきに信仰がにじみ出るようでなければならぬ
と。この言葉に感じ入った賢治は、その直後から猛然と童話を書き始めます。
賢治の童話から宗教色はあまり感じられませんが、そこには自然と人間の融和とせめぎ合いがあり、ユーモラスな野放図さがあり、博愛と自己犠牲があります。それら全てが賢治の信仰告白だったのでしょう。
この頃、賢治は月に3,000枚もの原稿を書いたと言われます。なんと一日に100枚。残っている賢治童話の第一稿のほとんどがこの7ヶ月間たらず(1月23日-8月中旬)の菊坂時代に書かれたとも言われます。トランクを原稿で一杯にして賢治は帰郷しました。12月に
ある人の一言で、迷いが払拭され、何かをつかみ、そして、パワー全開となることもあるのですね。
 |
吉屋信子の「奇跡の期間」は大正8年(22歳~23歳)でしょうか。YMCAの寄宿舎で同室だった菊池ゆきえが病気療養のために北海道へ渡るのに同行し、北海道で、3ヶ月ほどで初の長篇『地の果まで』(Amazon→)を書き上げています。また、同年、父親を亡くしますが、その喪の家で、『屋根裏の二処女』(Amazon→)を一気に執筆。吉屋は同性に対してあふれんばかりの愛情を持っていました。しかし、それを書くことを快く思わなかった父親。その父親が亡くなり、抑圧者がいなくなり、彼女の中に眠るテーマが解き放れました。ちなみに、『地の果まで』は菊池のすすめがあって筆をとったものです。吉屋はこれで「大阪朝日新聞」の長編小説懸賞で一位当選。総理大臣の年俸が1,000円だった時代、その2倍の2,000円を賞金として獲得しています。当時は文学がかくも高く評価されたのですね・・・。
 |
室生犀星の大正9年から15年までの7年間(30~37歳)も凄まじいです。前年の大正8年の4月下旬(29歳)から小説を書き始め、初期三部作といわれる『幼年時代』『性に目覚める頃』『
・・・僕は二年ばかりの間に、小説を書くのが商売になり、お金ばかりほしがってゐた。・・・(中略)・・・貧乏人はやつとありついたお金を使ふ面白さのために、おこりに
なんと、まあ、正直なこと! そうとうな駄作もあるようなので、ぜひ、読んでみたい(笑)。
 |
「奇跡の期間」といったら樋口一葉を挙げないわけにいきません。『大つごもり』『たけくらべ』『にごりえ』『十三夜』といった名作をわずか14ヶ月間で書いたというのです。「奇跡の14ヶ月」といわれています。期間でいうと明治27年12月(22歳)~明治29年2月(23歳)。彼女の場合、書きたいから書いたというよりも、17歳で戸主になり、家族の生計を支えるために必死に書いたという感じ。追われて、追われて、それで結果が出ることもあるのですね。
でも、追われることは、体にも心にも負担があるのでしょう。一葉は「奇跡の期間」の1年後、24歳で病没します。
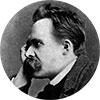 |
 |
ニーチェ |
「神は死んだ」の一節で知られるニーチェの代表作『ツァラトゥストラはかく語りき』も、第1部を10日間、第2部を2週間、第3部を10日間で書かれたようで(第4部の執筆期間は?)、これも相当なもの。「散歩中に啓示を受けた」とされますが、「啓示」などといった神がかった言葉を使わずとも、おそらくは、頭の中にばらばらにあったものがつながりショートして電流が走るようにしてある想念に達したのでしょう。何かがつかめたとき体に漲るパワーはいかほどでしょう。その波に身を委ねて一気に書き上げたのではないでしょうか。
萩原朔太郎(大正5年29歳)の「神を見る」も、おそらく似たような体験でしょう。朔太郎はその感動を手紙に書き、郵便に乗せるのももどかしかったのでしょう、知人の高橋元吉の家に自ら配達しています。高橋は自らのように喜び、2人は以後、人生を語り得る仲となりました。翌年(大正6年)、朔太郎は近代詩の金字塔ともなる『月に吠える』を上梓。
令和元年8月23日、横浜市営地下鉄「センター南駅」から歩いて行ける書斎的カフェ「
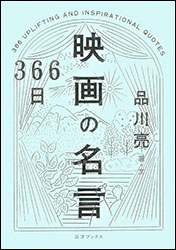 |
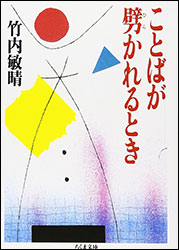 |
| 品川 亮『映画の名言 366日』(三才ブックス)。映画の中の一言が「一生モン」になることがある、きっとある | 竹内敏晴『ことばが |
 |
 |
| 室生犀星『香炉を盗む(短編集)』(隆文館)。多作時代の白眉・表題作「香炉を盗む」を収録 | シモーヌ・ヴェイユ『自由と社会的抑圧 (岩波文庫) 』。社会の抑圧と不正の構造を明らかにし、人間が自由であるための条件を探求 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 吉屋信子の『花物語』を読む→
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 萩原朔太郎の『月に吠える』を読む→
■ 参考文献:
●「出京・花巻農学校教師時代 〜大正10年-大正15年〜」「略年譜」(天沢退二郎)※『宮沢賢治(新潮日本文学アルバム)』(昭和61年発行)P.30-36、106 ●『吉屋信子 ~隠れフェミニスト~』(駒尺喜美 リブロポート 平成8年発行)P.31-33、P.268 ●『評伝 室生犀星』(船登芳雄 三弥井書店 平成9年発行)P.199-208 ●「滞郷の日々 〜大正2年-大正13年」「略年譜」(久保忠夫)※ 『萩原朔太郎(新潮日本文学アルバム)』(昭和59年発行)P.38、P.106
※当ページの最終修正年月日
2023.8.24