| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
昭和16年4月2日(1941年。 辻村もと子(35歳)の父の直四郎(72歳)が死去しました。
辻村は半年前(昭和15年7月)、11年間の夫との共同生活に終止符を打ち、一人、当地(東京都大田区)で、文学一筋に生き始めていました。
一人暮らしをはじめた辻村が早速に書き始めたのが『
自らの結婚解消によって父に与えただろう心痛を思い、すでに病の得ていた父に詫びるような気持ちだったかもしれません。しかし、一人になったからこそ、思うがままに書くことができる。父に読んでもらうことをひたすら願ってペンを走らせました。
完成前に父は死去しましたが、辻村の行動と残した作品『馬追原野』は、父への最大の供養でしょう。
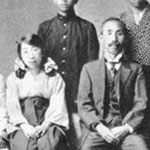 |
辻村もと子(17歳)と父・直四郎(54歳)。大正12年 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『辻村もと子 〜人と文学〜』(いわみさわ文学叢書) |
日本に残存する直系家族構造では、基本、長男が「家」を継承します。父親は自らも継承した「家」を長男に継承すべく、長男を特別扱いするケースが今も見られるようです。特別扱いには、当別な「優遇」もあれば、特別な「干渉」「監視」もあり。
特別に「優遇」されれば、それに腰掛けて“バカ息子”になる場合もあるでしょうし、また、特別に「干渉」「監視」されれば、息子がそれに反発することもあるでしょう。
娘はそういった直系家族構造からくる圧力には比較的無縁でいられ、普通に可愛がられて育つものなのかもしれません。父親を懐かしんで書くのは圧倒的に女性の作家が多いようです。
 |
尾崎一雄(左)と尾﨑士郎(右)。両者の娘たちも、父親たちと同様、早稲田で学び、仲が良かった ※出典:『ふたりの一枝』(講談社) |
尾崎一雄の娘の一枝と、尾﨑士郎の娘の一枝が、2人で『ふたりの一枝』(Amazon→)という本を著しています。2人とも旧姓が「尾崎(尾﨑)」なので、結婚するまでは共に「尾崎(﨑)一枝」。さらには、親同士(尾崎一雄と尾﨑士郎)が若い頃からの大親友ときています。
尾崎一雄も尾﨑士郎も物書きですから、こんな美味しいネタを
 |
萩原朔太郎と親族。左下で頬杖ついているのが朔太郎で、その上の制服(?)の娘さんが萩原葉子 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『萩原朔太郎(新潮日本文学アルバム)』 |
人生に行き詰っていた萩原葉子(36歳)に、父・萩原朔太郎のことを書くのをすすめたのは文芸評論家の山岸
読んだ人たちは驚いたようです。娘しか知り得ない、詩聖・萩原朔太郎の知られざる一面が赤裸々に書かれていたからです。朔太郎は、食べるとき食べ物をボロボロとこぼし(敷物を敷いたり、前掛けをかけたりしていた)、くんくんと鼻を鳴らしながら一人で笑っていたり、寝巻きや女ものの赤い下駄で飲みにいってしまったり、子どもように字が下手だったり、
晩年になって朔太郎(52歳。55歳で死去)は手品の会に入会します。あらゆることに無頓着な朔太郎でしたが、手品に関することだと几帳面にもなり、楽しげでもあるのが、娘の葉子の印象に残りました。下手な手品を何度も何度も葉子に見せようとする朔太郎でした。朔太郎が死んだ後、葉子は、二階の朔太郎の書斎にのぼり、鍵のかかっていた引き出しという引き出しに手品の道具が入っているのを見つけます。
・・・私は父の亡きあと、まもなく一人で二階に行って、それらの入った引出しを見た時、
なんてことだろうと思った。こんなものが、こんなに大切だった父の孤独の心を思うと、しばらく悲しみのため、そこを動くことができなかった。(萩原葉子「手品」(「父と手品」)より)
朔太郎もそうですが、当地(東京都大田区)に住んだ室生犀星・広津和郎の娘(室生朝子・広津桃子)も、父親のことを書き、本にしています。
やはり当地(東京都大田区)に住んだことがある幸田 文も、父親の幸田露伴のことを書くことから文筆活動に入っていきました。文芸評論家の野田宇太郎からのすすめがあってペンを取ったとのこと。
榊山 潤は義父(雪夫人の実父)をモデルに小説『歴史』(Amazon→)を書きました。義父の本名は佐倉
島崎藤村も、やはり“江戸と明治の断層”に翻弄された父の姿を長編小説『夜明け前』に書き込んでいます。父・正樹は青山半蔵の名で登場。
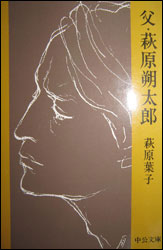 |
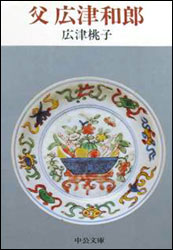 |
| 萩原葉子『父・萩原朔太郎 (中公文庫) 』 | 広津桃子『父 広津和郎(中公文庫)』 |
 |
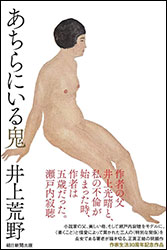 |
| 島崎藤村『夜明け前 (岩波文庫) 』。“明治維新”の裏面を知る格好の教科書でもあり、日本近代文学の金字塔の一つでもある | 井上
|
■ 馬込文学マラソン:
・ 辻村もと子の『馬追原野』を読む→
・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→
・ 萩原朔太郎の『月に吠える』を読む→
・ 萩原葉子の『天上の花』を読む→
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 広津和郎の『昭和初年のインテリ作家』を読む→
・ 榊山 潤の『馬込文士村』を読む→
・ 瀬戸内晴美の『美は乱調にあり』を読む→
■ 参考文献:
●『辻村もと子 〜人と文学〜』(加藤愛夫 いわみざわ文学
※当ページの最終修正年月日
2024.4.2