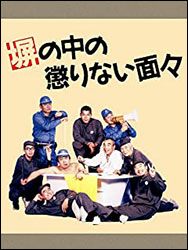| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
 |
市川が収容された「市ヶ谷刑務所」。鍛冶橋監獄を母体とし東京監獄と改称後、市ヶ谷方面(牛込区富久町)に移転、大正11年市谷(市ヶ谷)刑務所と改称された。昭和12年、東京都豊島区に移転し東京拘置所と改称される ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『図鑑 日本の監獄史』(雄山閣出版) |
市川は日本共産党(当時非合法だった)の幹部で、昭和4年28日、当地(東京都大田区馬込)に潜伏中、25〜26名の警官に包囲されて逮捕され、公判中でした(翌昭和9年無期懲役となり、網走刑務所に送られる)。市川は、「三・一五大弾圧」(1,600名におよぶ共産党員とその支持者の検挙)で壊滅状態にあった日本共産党を立て直した有能な人物でしたから、当局としては娑婆で生かしておくわけにいかなかったのでしょう。
市川が残した書簡(『獄中から 〜心優しき革命家・市川正一書簡集〜』(Amazon→))から、獄中での学びの様子や、 周りへの配慮などを読み取ることができます。両親が山口から上京する際(息子の近くにいようとしたのだろう)、旅が楽しいものになるよう、監獄にありながらも旅行案内書の入手につとめ、旅のプランをいろいろと書き送っています。自分の健康状態が悪いこと(全身のむくみ、視力の減退、栄養失調。歯はほとんど失われ米粒を机ですりつぶして食べていた)で両親に心配をかけないよう細心の注意を払っていました。
ずゐ分長らく
僕はいたつて元気ですから御安心下さい。決してカラ元気なのではありませぬ。心に少しもひかんすることがなく、常に自分の歩んだ道が正しかつたと信じてゐるのですから、元気なのはあたりまへであります。度々おたよりは致しませぬが、僕のことは一向御心配にならぬことです。・・・(昭和5年6月11日づけ両親にあてた市川正一の書簡より。収監後1年頃)
 |
戦前は、みんな仲良く平等にと社会主義的(民主主義的)なことを主張すれば、すぐに監獄行きでした。堺 利彦も5度は投獄されています。堺の獄中での読書も凄まじいものがありました。
堺が刑務所に入っている間、妻が髪結いの仕事を始めるというので、獄中からいろいろアドバイスしています。
・・・試みに僕が一二の献策を
今からすると著作権上問題がありそうですが、発想がなんて自由でポジティブなんでしょう。ユーモアもあります。出獄した翌年(明治44年、堺(41歳)は『楽天囚人』(日本の古本屋→)という本を出版。そこに為子あての獄中書簡も14通収録しています。妻への書簡も“仕事”にちゃんと生かしています。
葉山嘉樹も民主主義者(労働運動家)だったゆえに投獄されます。『淫売婦』は獄中で書かれました。
「獄中文学」には、「収監体験を回想したもの」「収監体験を元に獄中を表現(創作)したもの」「収監体験のない著者が獄中を描いたもの」もありますが、「実際に獄中で書いたもの」に限ると、他に、宮武外骨の『鉄窓詞林』、幸徳秋水の『柏木より』、荒畑寒村の『東京監獄より』、石川啄木の『A LETTER FROM PRISON』(「明治43年のフレームアップ事件」(俗称:「大逆事件」)最中の幸徳秋水が獄中から弁護士にあてた弁明書を啄木が密かに入手し写し取ったもの。啄木が前書きと所感を付している)、賀川豊彦の『塵紙に書きつけし歌 〜監房にて〜』、和田久太郎の『獄窓から』、久津見房子の『獄中の女性から』、金子ふみ子の『何が私をかうさせたか(獄中手記)』(Amazon→)、林 房雄の『獄中信』、中野重治の『獄中より』、桐野徳次の『女学生殺人犯の獄中手記』、児玉誉士夫の『獄中獄外(随筆集)』、福本和夫の『獄中十四年』、河上 肇の『獄中贅語』、宮本顕治の『十二年の手紙(宮本百合子との往復書簡)』、平沢貞通の『帝銀死刑囚 〜老てんぺら画家の獄中記〜』(Amazon→)『われ、死すとも瞑目せず』、永山則夫の『無知の涙』、
「収監体験を回想したもの」には他に、植木枝盛の『出獄追記』、田岡嶺雲の『下獄記』、福田英子の『
「収監体験を元に獄中を表現(創作)したもの」には、東海散士の『佳人之奇遇』、神近市子の『下獄二年』、葉山嘉樹の『牢獄の半日』『便器の溢れた囚人』、賀川豊彦の『壁の声きく時』、江口
中でも、正田 昭の『サハラの水』は、死刑判決を受けてから死と向き合う中で書かれたもので、特異な文学性を
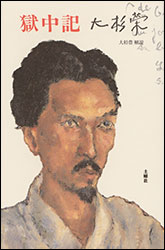 |
 |
| 大杉 栄『獄中記』(土曜社)。監修:大杉 豊。「僕の今日の教養、知識、思想性格は、すべてみな、その後の入獄中に養いあげられ、鍛えあげられた」と | 永山則夫『無知の涙 (河出文庫)』。加賀乙彦、秋山駿が著者・永山を日本文芸家協会会員に推薦したが拒絶される。文学者にも“資格”があるのか? |
■ 馬込文学マラソン:
・ 瀬戸内晴美の『美は乱調にあり』を読む→
■ 参考文献:
●『獄中から』(市川正一 暁書房 昭和22年発行)P.3、P.11-12、P.40-44 ●『不屈の知性 ~宮本百合子・市川正一・野呂栄太郎・河上 肇の生涯』(小林榮三 新日本出版社 平成13年初版発行 平成13年発行2版)P.93、P.120、P.145-149 ●『市川正一集 第三巻』(新日本出版社 昭和60年発行)P.346、P.482-483 ●『日本共産党の研究(1)』(立花 隆 講談社 昭和58年初版発行 平成16年発行22刷)P.316 ●『パンとペン』(社会主義者・堺 利彦と「売文社」の闘い)(黒岩比佐子 講談社 平成22年発行)P.49、P.203-209、P.422-424 ●『〈獄中〉の文学史 〜夢想する近代日本文学〜』(副田賢二 笠間書院 平成28年発行)P17、付録「<獄中>言説年表」(明治期〜1990年代まで) ●「永山則夫」(丸川哲史)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に収録(コトバンク→)
※当ページの最終修正年月日
2024.12.24