| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
正田 昭 |
昭和44年12月9日(1969年。 正田 昭(40歳)が、東京拘置所(葛飾区小菅一丁目35-1 Map→)で処刑されました。
16年前(昭和28年、敗戦後8年)、JR新橋駅近くにあったバー「メッカ」で、1月ほど前まで証券会社に勤めていた正田(24歳)が、住み込みのボーイと共謀し、証券ブローカーの博多 周さんを殺害、現在の金額でいうと250万円ほどを奪ったという事件(「バー・メッカ殺人事件」)で有罪になり、死刑になったのでした。
事件発覚後、彼のエリート性が話題になりました。正田の家は、父が弁護士、母が女学校の体育教師、3人の兄は早大、フェレンツ大学、東大を卒業しており、2人の姉も女子大を卒業するといったエリート一家で、正田も、事件の前年(昭和27年)、慶応大学を卒業したばかりでした。
また、逃亡した正田の捜索段階で、日本で初めてモンタージュ写真が使われ、配布され、その憂いを帯びた美男子ぶりも話題になります。手配写真の希望者が続出するといった変なことになって、それをマスコミが扇情的に書き、彼の“特異性”がきわ立ちました。
さらには、捕まった時、正田は、両手をズボンのポケットに突っ込み、口元にわずかに笑みを浮かべているようでもあり、話す話も「僕は元来おっちょこちょい」とか、「特に母校慶応の名誉を傷つけた」といったもので、殺人の深刻さを感じさせないものでした。裁判では、この“異方性”が、裁かれた面もあったのでしょうか。金閣寺放火事件同様、アプレゲール(戦後世代)の理解不能の犯罪と考えられました。
 |
ところが、収監されてからの正田の変化は著しく、2年後の昭和30年にはカトリックのS・カンドウ神父より受洗、罪を悔い改め、被害者の死後の平安を祈る日々を送ります。「日本の刑法史上、もっとも模範的、理想的な死刑囚」(川村
収監後の正田は、「混沌とした自分の内面」を知ることを熱望、その手段として小説を選び、その執筆に専念します。死刑確定後に書いた中篇小説『サハラの水』は、群像新人文学賞に応募され、最終選考の5編に残りました(「群像」編集長・大久保房雄は作者が死刑囚であることを知っていたが、審査員には知らされなかった)。
『サハラの水』は、国際的調査隊の4名が、本隊からはぐれて、広大なサハラ砂漠のど真ん中に投げだされるという話です。4名に残されたのは、2日分の食料と水。それが尽きた時、4人は死にます。英国人将校のベンと、かつてレジスタンスの英雄だったフランス人のジャックと、従者の「モール人」(北アフリカの現地人を意味する差別語)の男と、そして、日本人の「僕」。それぞれが、それぞれの人生を背負っています。
自己分析の形を取っていませんが、登場する4人が、それぞれに正田の「混沌とした内面」を表出しているようです。人生に挫折し砂漠での死を望んだベンも、ゲシュタポの拷問にあって「精神が肉体についてゆかない」ことを悟り人間嫌いになったジャックも、都会にあって「自己を充たすもの」を問い続けて不安に怯え続けていた「僕」も、正田の一側面なのでしょう。
“モール人”の男だけは、正田の一側面というよりは、正田が牢獄で知った“救い”を象徴しているようです。最後の“モール人”の男の下りは、不思議でもあり、感動的でもあります(「“モール人”は差別語だが、この言葉が作品の中で活きている)。
なお、作中の「2日分の食料と水」は、「牢獄での土曜日と日曜日」の暗喩でしょう。正田は土日には、死刑が執行されないと思い込んでいて、土曜日の朝は、これから2日間は生きることができると晴れやかな気持ちになったそうなのです(実際は土日にも処刑は執行される)。
正田は、心と体が健全になって40歳まで生きることができたことを深く感謝し、かつては不和だった母親とも深い絆を取り戻し、処刑前日には母親へ長い長い手紙を残し、死に赴きました。
このような気づきや改悛があっても、それだけで、即、彼の罪が軽減されるものではありません。が、そんな複雑な人間に、誰が一方的に「死」を与え得るでしょうか?
 |
死刑制度は現在、世界で144カ国が法律上または事実上廃止しています。死刑制度を残している国は55カ国ありますが、経済協力開発機構(OECD)加盟の38カ国に限ると、3カ国(日本、米国、韓国)のみで、死刑制度を国家として統一的に執行しているのは日本のみ(米国では50州のうち23州が死刑を廃止、韓国では平成9年以降死刑を執行していない)。
被害者と被害者の近親者の深い悲しみや絶望、暴力をビジネスにしている人たちの存在、無差別殺傷事件などを考えると、死刑制度を残すのもやむを得ないとの気持ちになりますがが、「死刑制度の是非」を問う前に考えなくてはならないのは、冤罪の問題。「信じられないような冤罪」(冤罪だとわかっていても警察がそれを認めず、証拠の捏造までするようなケース)が少なからず起きている現在、死刑制度を認めることは、「無実の人を死刑にする」少なくない可能性を認めることにもなります。仮に「無実の人を死刑にしてしまった場合」、国家はどうやってそれを償うというのでしょう?「死刑制度の是非」を問う前に、冤罪をなくす方策、たとえべ、取り調べの完全可視化などを実現する必要があります。
被告の犯行が明らかな場合でも、犯人の生育環境や社会環境が酷く、その影響を深刻に受けてきた場合などは、犯人の「自己責任」の追及だけで済ますわけにはいきません。家族の責任、社会の責任、国や政治の怠慢なども当然問われます。上記の正田にも、家庭が極度に乱れ、長兄の暴行があったため(長兄の言い分は「母が冷たかった」)、家出や自殺まで考える一時期がありました。死刑囚作家として著名な永山則夫も、父が失踪、母も5歳の頃出奔し、幼い兄弟だけで北海道網走の一冬を越すような経験をしています。
上述のとおり米国では半数近くの州が死刑を廃止していますが、それを温存している州では、死刑制度が「人種差別の装置」「批判封じの装置」にもなっています。現在(令和6年1月現在)も、アフリカ系の米国人の死刑囚が3,000人近くいます。その中には、ジャーナリストのムミア・アブー=ジャマルなど明らかに冤罪の人も含まれています(アブー=ジャマルはフィラデルフィア警察の体質を厳しく批判していた)。
 |
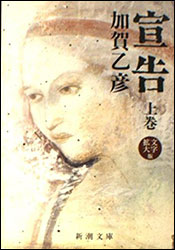 |
| 「サハラの水 〜正田 昭作品集〜』(インパクト出版会)。解説・正田 昭論:川村 湊 | 加賀乙彦「宣告(上)(新潮文庫)』。正田との交流の中から生まれた小説 |
 |
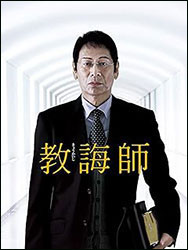 |
| 平野啓一郎「死刑について』(岩波書店)。死刑制度を残すことで社会が失うもの | 「教誨師」。死刑囚の教誨師を務める牧師の迷いの日々。演:大杉 漣。監督: |
■ 参考文献:
●「サハラの水 〜正田 昭作品集〜』(解説・正田 昭論:川村 湊 インパクト出版会 令和5年発行)P.8、P.10、P.13、P.25、P.38-39、P.268、P.270、P.272-273、P.276-281、P.286-287、P.294 ●「戦場の記憶を呼び起こす血なまぐささ「メッカ殺人事件」#1 #2」(小池 新)(文春オンライン→) ●『死刑について』(平野啓一郎 岩波書店 令和4年初版発行 令和5年発行4刷)P.31-32、P.35-37、P.108、付録「死刑に関する世界的な趨勢と日本」 ●「永山則夫」(丸川哲史)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」に収録(コトバンク→) ●『デリダ 〜脱構築と正義(講談社学術文庫)』(高橋哲哉 平成27年1刷発行 令和6年発行8刷)P.47-50
※当ページの最終修正年月日
2024.12.10