| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
明治43年からの「大逆事件」(俗称)の裁判は、秘密裏で行われ、証人の審問は一切なく、第一審(“大逆罪”は一審即結審との決まりがあった)で24名に死刑判決が出る。翌日天皇の恩赦で12人が無期懲役に減刑されるが(「天皇の恩情」を印象付けるためか)、残りの12名は異例の早さで処刑された。裁判記録「公判始末書」の行方も分からない
明治44年3月31日(1911年。 堺 利彦(40歳)が、「大逆事件」(俗に「大逆事件」と呼ばれるが、「明治43年の大でっち上げ事件」と呼ぶ方が正確)で処刑された12名の遺族を慰問する旅に出ました。12名が処刑されたのは2ヶ月ほど前の1月24日と25日。堺は東京を出発して、岡山、熊本、高知、兵庫、大阪、和歌山、三重と巡り、14の遺族を慰問しています。
堺が一句詠んでいます。
行春の若葉の底に生残る
堺は、3年前の明治41年の「赤旗事件」で、山川 均、大杉 栄、荒畑寒村らと共に入獄しており、滑稽な話ですが、俗称「大逆事件」で捕まらずに済んだのです。文字通り「生残った」。もし娑婆にいたら、この3人も中心的な人物なので無事でなかったことでしょう。
「大逆事件」(俗称)とはどんな事件だったのでしょう?
背景に、日露戦争(明治37-38年)に対する反対運動と、その反対運動に対する当局の卑劣な弾圧とがありました。堺 と幸徳秋水が、主戦論に傾く「萬朝報」を辞めて、自由・平等・博愛を掲げた「平民新聞(週刊)」を発行したのが明治36年。「大逆事件」(俗称)に連座した人たちは、この「平民新聞」に共鳴する自由主義者、平等主義者、博愛主義者だったのです。当局はそういった人たちを殺しました。
「平民新聞」では、社説を書いた堺が投獄されたり、罰金・発売禁止が続き、印刷機も没収され、明治38年に廃刊。2年後の明治40年、堺、秋水らが、日刊紙として復刊させましたが、それも発売禁止になったり、編集人や印刷人や筆者が紊乱罪で起訴されたりして、同年(明治40年) 63号をもって廃刊。秋水と管野スガらが出した雑誌「自由思想」も発禁となり、罰金が払えず菅野が換刑として投獄されるというようなこともありました。
攻撃されたのは出版物だけではありません。明治41年、山口孤剣の出獄歓迎会が東京神田で開催されているさい、大杉 栄や荒畑寒村が「無政府共産」と縫い付けた赤旗を振り回し、それを阻止しようとする警察官ともみ合いになります。堺 利彦や山川 均らは仲裁に入りますが、堺や山川らもろとも16名が検挙され、10名に論外に重い実刑判決が下りました。 堺や山川らは仲裁者なのに重禁錮2年です。扇動した大杉は重禁錮2年半、荒畑が重禁錮1年半、その他の者にも半年から1年の重い実刑判決(1人だけ執行猶予つき)がおりました。「赤旗事件」です。
自由・平等・博愛を訴える言論や集会といった手段を奪われ、運動のリーダーたちも根こそぎ牢獄に叩き込まれました。その卑劣な弾圧に対して、仲間の一部に過激な直接行動の発想が生まれました。
 |
宮下太吉 |
突っ走ったのが宮下
 |
 |
 |
 |
管野スガ |
新村忠雄 |
古河力作 |
宮下は爆裂弾投擲を管野スガに呼びかけ、菅野は宮下の考えに共鳴するだろう新村忠雄と古河力作を宮下に紹介しました。ただし爆裂弾は出来上がらず、4人がまともな実行計画を立てた形跡もありません(宮下は古河に会ったこともなかった)。宮下は秋水も誘いましたが、「そういう方法も必要かもしれないが、これからだね」と秋水は言うのみで関わりませんでした。
 |
 |
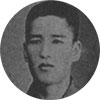 |
 |
大石誠之助 |
森近運平 |
松尾卯一太 |
新美卯一郎 |
秋水と話しただけで「決死の士」(裁く側が勝手に作った造語。調書は得てして“作文”される)と見なされました。米国、カナダ、インドで最新鋭の医学を学び絶大な影響力のあった熊野の医師・大石誠之助や、加温式ガラス温室を作るなど最先端の農業に取り組み地元でも尊敬されていた森近運平、「熊本評論」の松尾
 |
 |
 |
奥宮健之 |
内山愚童 |
成石平四郎 |
自由民権運動の闘士・
 |
12人が処刑された「東京監獄」跡(東京都新宿区 |
墓を作ることも許されず、「墓も許されぬ逆徒」の家族にも過酷な運命が待っていました。
武田
「大逆」とレッテルを貼られた彼らは、今や当たり前の 反帝国主義・民主主義・平和を模索し、そう生きようとしたまっすぐで勇敢な人たちだったのです。現在、森近の故郷岡山県井原市の生家跡には顕彰の記念碑が建ち「森近運平を語る会」も発足、大石の故郷和歌山県新宮市でも大石を名誉市民にする運動がおこり、平成30年1月24日、認定されました。
「東京朝日新聞」の校正部にいた石川啄木(24歳)は、「大逆事件」(俗称)に関連する評論「
徳冨蘆花(44歳)は、「天皇陛下に奉る書」を書き、被告の減刑を訴え、死刑が執行された翌月の2月、一高で同内容の「謀叛論」(青空文庫(草稿)→)と題した講演をしています。
 |
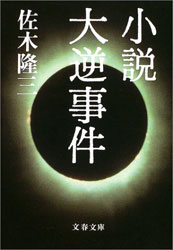 |
| 田中伸尚『大逆事件 〜死と生の群像〜』(岩波書店) | 佐木隆三『小説 大逆事件 (文春文庫) 』 |
 |
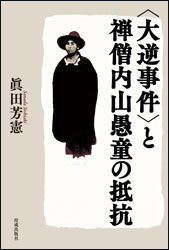 |
| 瀬戸内寂聴『遠い声 〜管野須賀子〜(岩波現代文庫)』。彼女は“国賊”だったのか? 彼女を陥れ殺した人たちが“国賊”(“国”を理由に酷いことをする人)ではなかったか? | 眞田芳憲『〈大逆事件〉と禅僧内山愚童の抵抗』(佼成出版社)。戦争や差別と向き合わなかった多くの宗教者と、向き合った宗教者。どちらが真の宗教者か? |
■ 参考文献:
●『パンとペン 〜社会主義者・堺 利彦と「売文社」の闘い〜』(黒岩比佐子 講談社 平成22年発行)P.16-17、P.23-24、 P.46-47、P.180-201、P.230-231 ●『大逆事件 〜死と生の群像』(田中信尚 岩波書店 平成22年初版発行 同年発行3刷参照)P.35-36、P.58、P.66-67、P.93 ●『明治大正史(下)』(中村隆英 東京大学出版会 平成27年初版発行 同年発行4刷参照)P.175-181 ●「平民新聞」(春原昭彦)※「日本大百科全書(ニッポニカ) 」(小学館)に収録(コトバンク→) ●「石川啄木」(岩城之徳)※『新潮 日本文学小辞典』(昭和43年初版発行 昭和51年発行6刷参照)P.52-55
※当ページの最終修正年月日
2024.3.31