| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
明治29年11月12日(1896年。 牧野信一が、小田原駅近く(神奈川県小田原市栄町二丁目8 Map→)で生まれました。
牧野は、早稲田大学に通い、昭和5年からは当地(東京都大田区山王一丁目 22 Map→)に住まうなど、東京暮らしも長いですが、しばしば小田原に戻りました。彼はほとんど旅をしなかったので、人生の大半を小田原と東京で過ごし、そして小田原で自死。
そんな牧野なので、彼の小説にも繰り返し小田原が出てきます。とはいっても、実験的小説を目指した牧野の文学に出てくる小田原は、小田原であっても実際の小田原とはどこか違う。遠い異国の、古の雰囲気があるのは、プラトンやアリストテレスを耽読していたせいなのでしょう。キラキラとしたギリシャ的な光が射す「彼だけの小田原」が立ち現われます。
温かい眼差しの人々や、家並み、木々、小鳥、虫、花々、空の雲や月や虹、その他のあれやこれやと「初めて出会う」“故郷の季節”。何年たっても、何十年たっても、忘れかけても、その時の驚きや感動は体と心に刻まれていることでしょう。
 |
井上 靖が故郷について書いた文章を読むと、境遇は全く違っても、不思議と自分の子どもの頃の心情が蘇ってきます。「ああ、そうそう、分かる分かる」という感じに。
井上は、父親の仕事の都合で、3歳から13歳まで、母親の郷里静岡県湯ケ島に預けられ、土蔵で、「おぬい婆さん」と2人で暮らしました。
「おぬい婆さん」は曾祖父の
曾祖父亡き後、本妻やその子たち(井上からしたら叔父や叔母)は妾(「おぬい婆さん」)を激しく憎み、「おぬい婆さん」は「おぬい婆さん」で、本家の惣領の娘(井上の父親は入婿だった)の長男(井上)を“人質”に取ってそれに抵抗。
 |
「天城湯ケ島市民活動センター」(旧・湯ヶ島小学校。静岡県伊豆市湯ヶ島117-2 Map→)にある「しろばんばの像」(「おぬい婆さん」と「洪作」の像) |
幼い井上もおぼろげながらにその複雑な関係を感じとり、「おぬい婆さん」側について、本家の人たちに対する反抗心をたぎらせるのでした。そこらへんの子ども心の機微を描いた井上の『しろばんば」には、井上の故郷への思いが詰まっています。
・・・朝眼が覚めると、洪作は必ず、それが朝の挨拶ででもあるように、床の中で、
「おばあちゃん」
と、おぬい婆さんを呼んだ。おぬい婆さんは耳が遠いことになっていたが、不思議にこの“おばあちゃん”と呼ぶ洪作の声だけは、階下にいても、また土蔵の外で炊事をしている時でも、耳さとく聞き分けた。
「おばあちゃん、おばあちゃん」
洪作が二声三声呼んでいるうちに、必ず、
「どっこいしょ、どっこいしょ」
と、階段を上って来るおぬい婆さんのかけ声が聞えて来て、それが終ったと思うと、階段を上りきったところでおぬい婆さんが背を伸ばす姿が見えた。おぬい婆さんはそこで一息入れてから、
「あいよ、あいよ」
とたて続けに返事をして、戸棚をあけ、そにに用意してある紙にひねった駄菓子を持って洪作の
「はい、おめざ」・・・(中略)・・・こうした朝のおめざは、上の家では非難されていた。祖母のたねはよく・・・(井上 靖『しろばんば』より)
故郷・湯ヶ島の井上の文学碑にも、『しろばんば』の一節が刻まれています。
国枝史郎の伝奇小説『
そんな“故郷”とも敢然と決別しようとしたのが、室生犀星です。
ふるさとは遠きにありて思ふもの
そして悲しくうたふもの
よしや
うらぶれて
帰るところにあるまじや・・・
(室生犀星「小景異情」より)
犀星23歳の時の作品です。都会での生活がどんなに苦しくても懐かしい“故郷”に縋ってはならない。独り、強く生きぬかなくてはならないとの決意でしょう。犀星の幼少期は凄まじかったので、「帰るところにあるまじや」には、何割かの悲しみと憎悪が含まれているかもしれません。
これらの犀星の詩に大感動したのが萩原朔太郎です。朔太郎は犀星の詩をほとんど
中原中也も“故郷”に対する複雑な心情を次のように表しています。
・・・これが私の
さやかに風も吹いてゐる
心置なく泣かれよと
あゝ おまへはなにをして来たのだと……
吹き来る風が私に
(中原中也「帰郷」より)
“故郷”は、「慰めが得られる場所」であると同時に、「問われる場所」でもあるのでしょう。その後、お前はどうしたか? と。
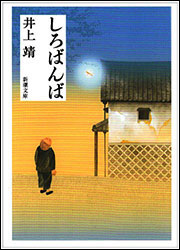 |
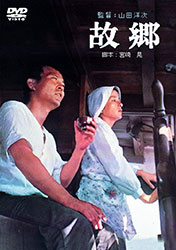 |
| 井上 靖『しろばんば(新潮文庫)』。周り人たちの心の綾と温順な伊豆の自然が心にしみる。自薦の一作。●昭和37年に映画化(おぬい婆さんを北林谷栄)→ | 「 |
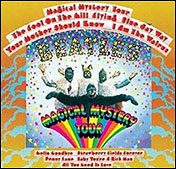 |
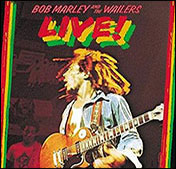 |
| ビートルズ 「マジカル・ミステリー・ツアー」。ビートルズには原点に戻れ(get back)のメッセージが散見される。このアルバムには、ジョンが故郷を歌った「Strawberry Filds Forever」(YouTube→)と、ポールが故郷を歌った「Penny Lane」(YouTube→)が並ぶ | ボブ・マーリー「ライヴ !」。昭和50年の伝説的なロンドン公演を録音「。ボブとウェイラーズの原点「Trench town Rock」(YouTube→)、ジャマイカのトレンチタウンの路上で |
■ 馬込文学マラソン:
・ 牧野信一の『西部劇通信』を読む→
・ 井上 靖の『氷壁』を読む→
・ 国枝史郎の『神州纐纈城』を読む→
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 萩原朔太郎の『月に吠える』を読む→
・ 中原中也の「お会式の夜」を読む→
・ 榊山 潤の『馬込文士村』を読む→
・ 山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→
・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
■ 参考文献:
●『牧野信一全集<第六巻>』(筑摩書房 平成15年発行)P.43、P.632、P.634、P.644-645 ●『牧野信一と小田原』(金子昌夫 夢工房 平成14年発行)P.3-5 ●「井上 靖評伝」(曾根博義)※『井上 靖(新潮日本文学アルバム)』(平成5年発行)P.4-15 ●『切なき思ひを愛す(室生犀星文学アルバム)』(編:室生犀星文学アルバム刊行会(原 祐子ほか)
※当ページの最終修正年月日
2025.1.15