| {column0} |

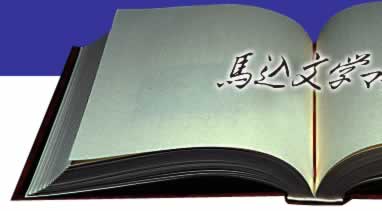







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
孤独でいられる人は強く優しい、ような気がする。 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『宮沢賢治(新潮日本文学アルバム)』
 |
明治44年1月6日(1911年。 志賀直哉(27歳)が日記に、
・・・他人と会ふといふ事は今年の自分にはいけない事であるやうだ、孤独を平気で仕事をするやうに何者かが自分を向けてゐるのかも知れないといふ気がする・・・
と書いています。志賀が武者小路実篤らと文芸・美術雑誌「白樺」を創刊したのが前年(明治43年)の4月(志賀27歳、武者小路25歳)。毎月雑誌を出すのはたいへんなことで、もともと密な関係だった同士が、さらに頻繁に会わなくてはならなくなって、これはちょっとまずいと思い始めたようです。作家は内面にあるものを見つめ、形にする(文章にする)のですから、一人になること、つまり「孤独」 も絶対必要です。
大正2年8月(上の日記の2年半後)、志賀が山手線の電車にはねられたり、その2ヶ月後の同年(大正2年)11月には里見弴の原稿が紛失したり(志賀が奪ったとも)という事件がありましたが、それらは、「仲良くしたい」と「一人でいたい」という2つの感情がこじれたからなのかもしれません。
志賀は、父親の反対を押し切って足尾銅山鉱毒事件に関わろうとし、北原白秋が姦通罪で拘留されマスコミと文壇がこぞって白秋を「文芸の汚辱者」と誹謗したとき白秋を擁護し、非国民と誹謗された頃の共産主義者・小林多喜二と交友し、戦後は体制側の巨悪との戦いだった松川事件に関わりました。「みんなから浮いてはいけない」という日本人を強く縛っていると思われる呪縛を逃れ、志賀は常に「孤独」を恐れず、自らの考えを実践しました。
 |
川端康成の場合は、1歳のとき父が死に、翌年に母が死に、7歳のとき祖母が、10歳のとき唯一の姉弟の姉が死に、15歳のときに祖父が死んで、文字通り天涯孤独となりました。外的要因で「孤独」と向き合わざるを得なくなります。彼の『伊豆の踊子』(27歳)にしても、『浅草紅団』(30歳)にしても、『雪国』(35歳~)にしても、『山の音』(50歳~)にしても、“異邦性”(そこに所属できない悲しみ)、つまり「孤独」が、根底に流れている、そんな気がします。
ここでも「孤独」は必ずしもネガティブではありません。自身の“異邦性”(孤独)の自覚が、他の“異邦性”(孤独)への理解・共感の
川端は昭和9年(35歳)より、ハンセン病を患い“異邦性”(孤独)のどん底にあった一青年(北條民雄)と文通し、北条が昭和12年重病室に入る直前までに90通の書簡を交わしています。川端が北条に宛てた書簡に次の一節があります。
・・・ジャアナリズムは君を滅ぼす。文学者になど会いたいと思ってはいけません。孤独に心を高くしていることです。・・・
 |
室生犀星の家庭的な不幸はさらに凄まじく、生まれた直後、名もつけられずに、捨てられています。養母からは
我は張りつめたる氷を愛す
我はそれらの輝けるを見たり
斯る花にあらざる花を愛す
我は氷の奥にあるものに同感す
我はつねに狭小なる人生に住めり
その人生の荒涼の中に
さればこそ張りつめたる氷を愛す
斯る切なき思ひを愛す
 |
戦後、「鎌倉文庫」の仕事と、執筆活動との間で、高見 順が苦しんでいます。性格がそうさせるのか、どうしても周りの要望に(過剰に)応えようとしてしまう。日記に、次のような言葉が並んでいます。
原稿依頼を片端から断った。
それでも原稿に追われている。
その程度の追われ方なら、まあ、いいだろう。
ほんとうの仕事をするためには、
人々から(読者から)嫌われねばならぬ。
そうして己れを守らねばならぬ。
まだ嫌われ方が足らぬ。
「孤独でもいい」ではなく、時には積極的に「孤独が必要」と考える必要があるかもしれません。
 |
勝 海舟は人と人を「
・・・ナニ、誰を味方にしようなどと
誰しも生老病死は避け得ないし、遅かれ早かれ「孤独」と向き合うことになるでしょう。日頃から、自身の“異邦性”(孤独)に気づいていたいです。帰属意識にどっかりあぐらをかいていると、じわじわと迫り来る根源的な「孤独」にいつか打ちのめされそう。
「孤独」であることは、ある意味、あらゆる関係に線引きをしないこと。誰とでも繋がれる開かれた身体を持つことでもあります。イエスや
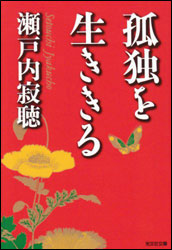 |
 |
| 瀬戸内寂聴『孤独を生ききる (光文社文庫) 』 |
 |
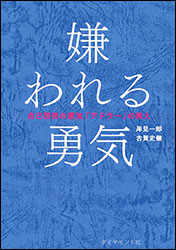 |
| 岡本太郎『孤独がきみを強くする』(興陽館) | 岸見一郎、古賀史健『嫌われる勇気 〜自己啓発の源流「アドラー」の教え〜』。「自由とは他者から嫌われることである」と(ダイヤモンド社) |
■ 馬込文学マラソン:
・ 志賀直哉の『暗夜行路』を読む→
・ 川端康成の『雪国』を読む→
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 高見 順の『死の淵より』を読む→
・ 子母澤 寛の『勝 海舟』を読む→
・ 瀬戸内晴美の『美は乱調にあり』を読む→
■ 参考文献:
●『志賀直哉(新潮日本文学アルバム)』(昭和59年発行)P.25-27 ●『川端康成(新潮日本文学アルバム)』(昭和59年発行)P.4-7 ●『評伝 室生犀星』(船登芳雄 三弥井書店 平成9年発行)P.22-29 ●『それからの海舟(ちくま文庫)』(半藤一利 平成20年初版発行 平成25年発行15刷)P.151
※当ページの最終修正年月日
2024.1.6