| {column0} |

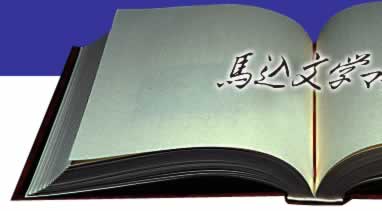







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
当地(東京都大田区南馬込一丁目18-5 map→)の書斎でくつろぐ山本周五郎(昭和14年頃。36歳頃)。この部屋に周五郎を執筆に掻き立てる仕掛けがある ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『山本周五郎(新潮日本文学アルバム)』
昭和16年9月19日(1941年。
山本周五郎(38歳)が、歌人で小説家の
・・・実はちょっと御相談があるのですが、去年から仕事が出来ないので、大いに
下村に前借り交渉を頼んだのですね。 下村は、周五郎より9歳年長で、娯楽雑誌で人気がありました。下村の言うことなら出版社も聞いてくれると踏んだのでしょう。
この頃、周五郎の前借りはすでに常習化していたようです。周五郎の書斎には、二葉亭四迷が書いた原稿料催促の手紙が表装されぶら下がっていました(上の写真の右手に注目)。周五郎は編集者が来るとこの掛け軸を黙って指差したと言います。ふてぇ野郎です(笑)。ま、何が何でも周五郎に書いてもらいたい編集者たちは、「はい、はい」とそれを承諾したのでしょう。誰にでもできる芸当ではありませんね。
周五郎の前借りには訳がありました。お金に余裕があってはいいものが書けないというのが彼の持論だったようです。 原稿料を前借りしてほぼ使い切ってから、つまり経済的ににっちもさっちもいかなくなってから書く。周五郎の小説は弱者に対する温かいに眼差しがあります。「安心」「余裕」があっては、弱者は描けないと思ったのかもしれません。
あと、経済的に断崖絶壁に自らをもっていって、強引にでも創作エンジンをかける意図もあったかもしれません。追い込まれないと重たい腰が上がらないのは誰しも同じですもんね?
周五郎以外の職業作家たちは、どうやって、創作への気持ちを高めていったでしょう? 1、2作目、または数年間は感興に任せて筆が運んだにしても、それが長期にわたる“仕事”ともなれば、そうもいかないでしょう。ネタ切れもあろうし、気乗りしないことだって・・・。
 |
そんなことが何でできるのでしょう? その“秘訣”らしきことを次のように書いています。
・・・修養時代には多作して筆を慣らし、想を枯らすことが肝腎であるのだ、筆を慣らせば即ち
最初はともかくガンガン書いて書くことに慣れること。そして、持っている発想が枯れるまで吐き出せば、また新鮮な何かが入ってくるだろうと。ポジティブですね!
 |
 |
 |
中原中也は「毎日毎日歩き通」し「時折、詩を書いた」ようですし、真船 豊も
反対に自らを“缶詰”にしたのがヴイクトル・ユゴー。彼は『ノートル=ダム・ド・パリ』を書くにあたって、変な服を一着買って着て、あとの服が入っているタンスには鍵をかけ、外出したくなる気持を萎えさせたとか!
 |
ユニークなのは志賀直哉で、「不快と疲労」を味方につけています。
・・・御祭りで稲荷を皆おがむ。自分はどうでもいゝと思つて、カン主から
『
満ちたりていたら、あえて何かを生み出そうと思わないでしょうから、知らず知らず“不幸”を求めてしまう作家も多そうです。太宰 治とか無頼派の連中はそういった傾向が強そう。
 |
手堅いのが、「習慣の力」を使うこと。少しずつでもともかく毎日やる。2年3年も続けると、「よし、やろう」と自分を叱咤しないでも、「やらないと気持ちが悪い」といった心境になることでしょう。宇野千代は言います。小説が書けないでも、「毎日、ちょっとの時間でも、机の前に座ること」と。秘訣は、仮に興が乗っても、決めた時間・分量しかやらないこと。「もっとやりたい」が明日のモチベーションにつながり、限られた時間・分量の質を高めることともなることでしょう。
あと、すぐに、今から始めること。「いつかやろう」は多くの場合、一生やらない。今、取材先の宿に予約を入れてしまうとかも手かもしれません。
最初、情報でも何でも集め、それを整理していく中で生まれる発想もあることでしょう。
「夢」に頼る作家もけっこういるみたいです。夢は無意識の貯蔵庫。「自分の知らない自分」に出会えます。
 |
 |
| 山本周五郎『泣き言はいわない (新潮文庫)』。権威・権力には見向きせず、常に市井の人々とともにあった周五郎の言葉 | 山口文憲『読ませる技術 (ちくま文庫)』。気軽に読めて面白い。「技術」も知らないよりは知っていた方がいいかと |
 |
 |
| 『〆切本』(左右社)。〆切に間に合わない作家たちの言い訳の数々。胃痛などの肉体反応や自己考察・自己嫌悪から、逆切れまで | 筒井康隆『創作の極意と掟 (講談社文庫)』。「何をどのように書いてもいい」小説という無頼の世界を、いかに生き抜くか |
■ 馬込文学マラソン:
・ 山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→
・ 中原中也の「お会式の夜」を読む→
・ 真船 豊の『鼬』を読む→
・ 川端康成の『雪国』を読む→
・ 志賀直哉の『暗夜行路』を読む→
・ 宇野千代の『色ざんげ』を読む→
■ 参考文献:
●『山本周五郎 馬込時代』 (木村久邇典 福武書店 昭和58年発行) P.85-87、P.227-234 ●『山本周五郎(新潮日本文学アルバム)』(昭和61年初版発行 昭和61年2刷参照)P.47 ●「縄文時代の大田区」(関 俊彦)※『大田区史(上巻)』(東京都大田区 昭和60年発行)P.92-114 ●『ノートル=ダム・ド・パリ(下)(岩波文庫)』P.555-556 ※解説 ●『志賀直哉 上(岩波新書)』(本多秋五 平成2年)P.160 ●『明治文豪創作苦心秘話』(編:
※当ページの最終修正年月日
2024.9.19