| {column0} |

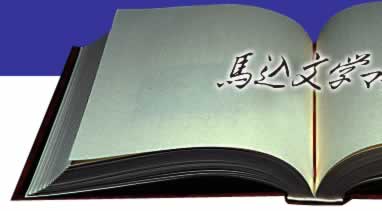







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和14年3月23日(1939年。
「東京市立療養所」(「
立原は元気で、若林が「何か欲しいものがあれば」と問うと、手にしていた洋書を置いて、
五月のそよ風をゼリーにして持って来て下さい、非常に美しくておいしく、口の中に入れると、すっととけてしまふ青い星のやうなものも食べたいのです五月の風をゼリーにして
と言ったそうです。ユーモアがあり美しくもあって、どこまでも“詩人”な立原なのでした。
美しい言葉の響きの中で見落としてしまいそうですが、「五月の風をゼリーにして」と言うからは、今度の5月を迎えるのはもはや難しいとの予感もあったのでしょうか、立原はこの6日後の3月29日、喉に痰がつまり、突如、帰らぬ人となります。
若林と見舞いにきた芳賀を立原が識るのは、4年前の昭和10年(21歳)頃。文芸誌「コギト」(昭和7-19年。「日本浪曼派」の源流)に連載された芳賀の「ナポレオン・ボナパルト」を読んで感銘を受け、その翌日、「コギト」に自作を寄せています。翌昭和11年(22歳)の関西旅行の際には、京都で芳賀と会います。昭和13年(23歳)には、芳賀から献本をされた『古典の親衛隊』を読んで非常に感動しました。
・・・あの御本のなかで呼吸するとき、私の決意は新しくたしかめられます。私もまたひとりの武装せる戰士!・・・(立原の芳賀あて書簡より)
立原を感動させた本の著者・芳賀 檀はいかなる人物で、その『古典の親衛隊』とはどんな内容なのでしょう。
芳賀は明治36年生まれで立原の11歳年上です。父は国文学を文献学的に扱って「近代国文学の開拓者」とされる芳賀矢一(東京帝国大学名誉教授。國學院大學学長)。芳賀(檀)も父・矢一と同様ドイツに留学し、帰国後は三高(第三高等学校(旧制。京都))の教授となり、「コギト」、「日本浪曼派」、「四季」で古典擁護の評論を展開しました。昭和11年のオリンピック・ベルリン大会で国力を誇示したドイツと、日本は、同年、日独防共協定を締結、ナチスが近しい存在になるや、その“力の福音”を
昭和12年発行の芳賀の『古典の親衛隊』には次の一節があります。
・・・私達は、肉体をも変革し得る精神の力を信じよう。しかも、精神をも高貴ならしむるのは愛の力である。それならばもしニイチエが今吾々に『精神だけで人を高貴にすることは出来ない。それは精神をも高貴にする在る物を要するのである。即ち血統を。』と言う時誰も彼を怪しまないであろう。・・・(中略)・・・愛する者等のために琴を、また
このような、「精神」を「愛」で包んで、脈絡なく「血統」と結びつけ、それを「戦い」の原理にしようというお粗末な文章に、立原がなぜ感動してしまったのでしょう? 「古典」を
立原がもっと生きていたら、芳賀らの影響を受けて、多くの文化人同様、戦争に加担したとの見方もありますが、それはどうでしょう。立原が最後の旅で書いた「長崎ノート」には、
・・・コギトたちのあまりにつめたく、愛情のグルント〔ドイツ語で「基礎」〕のない文学者の観念を否定すること。コギト的なものからの超克 ──犀星の『愛あるところに』という詩をふかくおもひいたれ・・・(立原「長崎ノート」より)
とあります。室生犀星の「愛あるところに」には、
その白いむねをつかんで
わたしは永い間語るであらう
どんなに永い間寂しかつたといふことを
(犀星「愛あるところに」より)
とあり、立原はやはり、「どんなに永い間寂しかつた」といった、特定民族に限定されない、特定血縁にも限定されない、普遍的な感情に踏みとどまったような気もします。
芳賀も参加した文芸誌「日本浪曼派」は、昭和10年、神保光太郎、亀井勝一郎、中谷孝雄、保田與重郎ら6人が創刊し、3年後(昭和13年)の終刊までに、太宰 治、檀 一雄、
折口信夫(49歳)が、小谷 恒を連れて、当地(東京都大田区)の室生犀星(46歳)を訪れたのも、そんな折の昭和11年でした。折口も犀星も昭和3年より当地(東京都品川区・大田区)に住んでいました。その後小谷は犀星宅に出入りし、 犀星も小谷・折口から刺激を受け、『
犀星宅に出入りする小谷と親しくなった堀 辰雄も、小谷を介して折口を知り日本回帰していきました。堀はバリバリの西洋志向でしたが、昭和12年頃(33歳頃)、『風立ちぬ』が完結に近づき、『伊勢物語』を勉強をし始め、初めて京都にも行き、古い寺の一室で一月ほど過ごしたり、折口の『
萩原朔太郎も、欧米・ロシアの影響を受けて自らが育ててきた日本近代詩をある意味否定し、昭和8年頃から能を熱心に見るようになり、昭和9年発行の『
「美と古典」を語りながらも軍国主義やナショナリズムと結びついて、国民を死にかりたて、また、多くの他国民を殺す動機を提供した「日本浪曼派」は、戦後、全否定されました。戦後獲得した「個人主義」「自由主義」「民主主義」「平和主義」といった理念のもと、「美と古典」をいかに健全に語り得るか、それが今後の課題でしょう。
 |
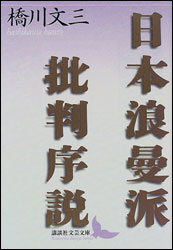 |
| 長山靖生『日本回帰と文化人 〜昭和戦前期の理想と悲劇〜 (筑摩選書)』 | 橋川文三 『日本浪曼派批判序説 (講談社文芸文庫)』 |
 |
 |
| 山崎雅弘『戦前回帰 〜「大日本病」の再発〜(増補版) (朝日文庫)』。近年の戦前回帰に警鐘を鳴らす。間違いを知らない人、間違いを認めない人は、同じ間違いをまた繰り返す・・・ | 「愛国者に気をつけろ! 鈴木邦男」。監督:中村真夕。出演:鈴木邦男、雨宮処凛ほか。新右翼「一水会」顧問の鈴木邦男。彼の“愛国”をたどることで浮かび上がる“偽の愛国”。予告編→ |
■ 馬込文学マラソン:
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・ 堀 辰雄の『聖家族』を読む→
・ 萩原朔太郎の『月に吠える』を読む→
・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
■ 参考文献:
●『立原道造・愛の手紙(文学アルバム)』(小川
※当ページの最終修正年月日
2024.3.22