| {column0} |

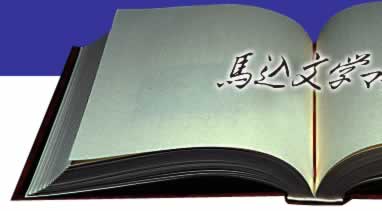







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和30年1月2日(1955年。 井上 靖(47歳)の小説『氷壁』の題材となる遭難が起きました。
三重県鈴鹿の山岳会「岩稜会」の13人(会友含む)が、昭和29年末から、冬期合宿で、穂高の
前穂高東壁のAフェースに取り付いたのが、石原國利(中央大学4年。24歳)、澤田栄介(三重大学3年。21歳)、若山五朗(三重大学1年。19歳)の3人でした。1日の朝3時に奥又白のベースキャンプを出て、B沢をつめ、岩壁基部で安全確保のためザイル(登山用のロープ)で結び合いました。
雪は固まっておらずアイゼン(氷道を歩いたり氷壁を登るため登山靴にはめる器具)の歯は全く効かず、岩の雪を掻き落としながらの登攀となって時間を消耗。岩壁上部で日が暮れて、やむをえず3人はビバーク(外で寝ること)することとなります。岩の窪みに足を入れ、尻が半分乗る程度の岩棚にうずくまり、額を岩に擦り付けるような体勢です。尻がずれたら真っ逆さまなので、それぞれがザイルで体を岩に固定し、厳寒の夜をやり過ごします。
ようやく夜が明けますが、雪は激しく、頂上へ出る最後の難関を突破する術がなかなか見つからず、3人とも消耗してきます。そして、若山が先頭に立ってザイルを伸ばしている最中、事故が起きました。
ザイルを突起にかけてトラバース(岩を横に移動すること)を開始した時、スリップ。ザイルが切れて、若山は墜落してしまいます。
翌年(昭和31年)の11月から、この遭難事故を題材に井上は『氷壁』を「朝日新聞」に連載しますが、小説では、
さらには、小説中の魚津には、題材となった遭難の6年前(昭和24年)、滑落したパートナーとともに同じ北アルプスの北鎌尾根に消えた天才的登山家・松濤 明の面影が濃厚です。当時は集団で登る極地法が主流でしたが、松濤は少人数で、スピーディーに登る方法をとりました。高度な実力が要求され、危険でもありますが、より難しいルートに取り組む上では有効でした。また、スタイル的にも洗練されています(カッコいい)。小説中の魚津も小坂と2人で山に入っています。松濤の遭難のおり、麓で帰りを待つ恋人がいましたが、井上も『氷壁』で、魚津の帰りを小坂の妹が麓で待つというふうに取り入れています。
1つの事件と1人の人物が渾然としているのが井上の『氷壁』で、それが映画化、ドラマ化することで、実際の“モデル”(実際)からさらに離れていきました。映画化された『氷壁』(Amazon→)は魚津のストイックさに忠実でしたが、ドラマ化された『氷壁』(Amazon→)は陳腐なメロドラマに堕してしまいました。 「面白けりゃ、いんじゃね?」という考えも根強いようですが、歴史上の事件や歴史上の人物をモデルにするのなら、真実に迫るアプローチが必要です。
実際に近いことを知るのなら、ザイル切断で遭難死した若山の実兄の石岡繁雄が書いた『氷壁・ナイロンザイル事件の真実』(Amazon→)、松濤 明の手記とエッセイをまとめた『新編・風雪のビヴァーク (ヤマケイ文庫) 』(Amazon→)があります。
井上の『氷壁』連載開始の3年後(映画「氷壁」公開の1年後)の昭和34年、松濤をかなり忠実にモデルにした安川茂雄の『青い星』が発行されました。そのあとがきで安川は、
・・・私は氏の生涯の
とことわっています。モデルを少し知って訳知り顔になるでなく、モデルを心より尊敬しているからこその言葉でしょう。
モデルがある小説、あるいは著者がそう言わないでも読者が特定の人物を想起する小説は、注意しないと、とんだ筆禍となります。事実に即しているのなら表現の自由から許容しなくてはならない場合も多いとは思いますが、著者によってモデルの言動が小説内で改変され、読者がそれを真実と思い込み、そのことによって、モデルが傷つくとしたら罪なことです。
 |
尾﨑士郎の小説『空想部落』の登場人物には特定のモデルはないとされますが、舞台の牛追村は名前からして当地(東京都大田区)の馬込村を連想するし、二科系の洋画家でパリ帰りとくれば東郷青児、共産党の大物と関係があって飲み屋をやっていると言えばいやでも星野幸子が連想されます。モデルが想起されたら、小説の中の
 |
堀 辰雄の『聖家族』にも、九鬼という芥川龍之介を思わせる人物が出てきます。九鬼が芥川なら、細木夫人は片山広子で、その娘の絹子は
 |
徳富蘆花の『
 |
 |
| 安川茂雄『青い星』(山と渓谷社) ※東京都大田区立図書館が所蔵 | 平塚晶人『ふたりのアキラ (ヤマケイ文庫) 』。松濤 明と奥山 章を慕った女性登山家・芳田美枝子の物語 |
 |
 |
| 柳 美里『世界のひびわれと魂の空白を』(新潮社)。『「石に泳ぐ魚」裁判をめぐる経緯について答える』を収録。柳さんの『石に泳ぐ魚』はモデルの女性から訴えられ、最高裁で柳側の敗訴となる | 三島由紀夫『宴のあと (新潮文庫)』。モデルの一人からプライバシー侵害で訴えられ、三島側は「芸術的な価値」と「表現の自由」を盾に争ったが、損害賠償の支払いを命じる判決がおりる |
■ 馬込文学マラソン:
・ 井上 靖の『氷壁』を読む→
・ 尾﨑士郎の『空想部落』を読む→
・ 堀 辰雄の『聖家族』を読む→
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
・ 片山広子の『翡翠』を読む→
・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
■ 参考文献:
●『氷壁・ナイロンザイル事件の真実』(石岡繁雄 あるむ 平成21年発行)P.10-12、P.16-17、P.26-28 ●『井上 靖(新潮日本文学アルバム)』(平成5年発行)P.66-69 ●「松濤 明と芳田美枝子 『風雪のビヴァーク』(愛の旅人)」(今田幸伸)※「朝日新聞」(平成19年8月18日掲載) ●『物語の娘 〜宗 瑛を探して〜』(川村 湊 講談社 平成17年発行)P.20-23、P.118-120
※当ページの最終修正年月日
2025.1.1