| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
昭和30年4月29日(1955年。
ザイル製造会社・東京製綱の工場(愛知県
4ヶ月ほど前の同年1月2日、北アルプス前穂高岳東壁Aフェースで、新品のナイロンザイルが切れて一名が死亡するという事故がありました。従来の麻ザイルより数倍強度があるというふれこみで販売されていたナイロンザイルがあっさり切れてしまったのです。先鋭的な登山を目指していた三重県鈴鹿の山岳会「岩稜会」(前穂高岳東壁Aフェースは冬期にはまだ誰にも登られていなかった)は、ナイロンザイルの高性能を信じて真っ先に登攀に取り入れ、そして、この事故となりました。
事故後、ナイロンザイルの販売者から、遭難者側のザイルの扱い方に問題があったとする見解が示されたのに抵抗し、遭難者を出した岩稜会では、独自に実験(「岩稜会事前実験」)を行います。そして、「(ナイロンザイルの)岩角弱点」をはっきりと確認します。ところが販売者側は「肉親がやった実験は信用できない」としたのです。岩稜会の会長・石岡繁雄(37歳)は遭難死した若山五朗(19歳)の実兄でした。こういった経緯もあって、「蒲郡実験」は公開されることになったのです。
実験結果は「ナイロンザイルは切れず」でした。実験を主導したのは日本山岳会関西支部長の篠田軍治(当時、大阪大学工学部教授)です。そして、参観したマスコミはその実験結果を疑うことなく報道しました。
雑誌「山と渓谷」(昭和30年7月号)には、ナイロンザイルの販売者の言葉で、「(「蒲郡実験」で)あらゆる面が判明しました」「(今回の遭難は)誤れる使用によるザイル切断」「指導者があまりにも、ザイル知識を知らなすぎた」とする記事が掲載されました。「(ナイロンザイルの)岩角弱点」には言及されず、今回の遭難は、ナイロンザイルの製造者・販売者にはなんら問題がなく、あくまでも遭難者の過失によるものとしたのです。岩稜会側は遭難をナイロンザイルのせいにしたとして、世間からも親族からも非難されることとなります。
しかし、岩稜会は泣き寝入りしませんでした。「蒲郡実験」から3ヶ月ほどたった同年8月6日、数名でナイロンザイル切断現場まで岩壁を登り、残されたナイロンザイルの繊維を採取、また、ナイロンザイルが擦れて切断の原因になったと思われる岩角を石膏で型取って持ち帰りました。そして、切断現場の状況を可能な限り再現して再度実験(「岩稜会事後実験」)。落下させる重りの重さは遭難者・若山の生前に記録された最後の体重よりもさらに4kgほど軽くした60kg(重りが重くて切れたとする反論を封じるため)、落下距離も50cmほどと短距離としました。そして、結果はというと、ナイロンザイルは呆気なく切れたのです! 墜落というほどでなくても、体重をかけたくらいでもナイロンザイルが切れることが分かりました。少しでも擦れれば、さらに切れやすくなります。ナイロンザイルは岩角ではかくも弱いものなのでした。
さらに衝撃的なのが、「蒲郡実験」を参観した加藤富雄(三重県山岳連盟理事。墜落死した若山の友人)が同年7月20日に発表した「加藤レポート」。実は、「蒲郡実験」を主導していた篠田は、「蒲郡実験」前に予備実験しており(「篠田事前実験」)、ナイロンザイルが従来の麻ザイルよりも岩角において極めて弱いという結果を得ていたのです。岩角において、直径8mmのナイロンザイルは直径12mmの麻ザイルの1/20の強度しか出ませんでした(「直径8mmのナイロンザイルは直径11mmの麻ザイルの3倍の強度がある」という触れ込みでナイロンザイルは販売されていた)。そんなナイロンザイルが「蒲郡実験」で切れなかったのは、実験用の岩角に参観者に気づかれないほどの丸み(1mmほどの斜角)がつけられていたからと発表。これだけの丸みで、結果に雲泥の差が出たようなのです。当然、自然の岩には、そんな意図的な丸みなどありません。篠田は、ナイロンザイルの利点のみを強調してきた企業、販売サイド、識者の責任が問われないよう、細工したのでしょうか?
岩稜会は「岩稜会事後実験」の結果を持って「蒲郡実験」を主導した篠田に面会。そのおり、篠田は実験結果を認め、「蒲郡実験」で広まった「ナイロンザイルの安全性に問題がない。ザイルが切れたのは登山者のミス」という誤った結論を訂正することも承諾します。ところが、その後、篠田は訂正せず、それどころか、「蒲郡実験」の正当性を補強する論文まで発表したのです。それに呼応して、「中日新聞」「岳人」「毎日グラフ」「山と渓谷」などが、「蒲郡実験」を追認する記事を書き、岩稜会はますます窮地に追い込まれていきました。篠田らから誠意ある対応が期待できないことが明らかになり、翌昭和31年、岩稜会は篠田を名誉毀損で訴えことにします。
また、岩稜会は、事件のあらましとその問題的を書いた310頁もの報告書「ナイロン・ザイル事件」を作成。わら半紙に謄写版で150部印刷して、知人、新聞社、雑誌社、山岳関係者に送付して理解を求めていきました。この報告書が石岡(岩稜会の会長、墜落死した若山の実兄)の知人・安川茂雄にわたり、安川から井上 靖 にわたって小説『氷壁』が書かれました。告訴後、起訴か不起訴か明らかになる前の同年(昭和31年)11月24日から「朝日新聞」に連載され、世間はこの事件を知り、関心を寄せるようになっていったのです。
訴訟自体は、名古屋地検(担当:亀井検事)から大阪地検(担当:斎藤検事)に回されて、さらに年を重ねた昭和32年7月22日、不起訴となります。検察は、東京製綱サイド、篠田、「蒲郡実験」で使用した岩角を加工した石材商からは調書を取りましたが、岩稜会からは聞き取りをしませんでした。
学者も、マスコミも、企業も、一部の有名登山家(山崎安治や近藤 等など)も「ナイロンザイルに問題なし」としましたが(「毎日新聞」は「岩稜会事後実験」を報道し警鐘を鳴らした)、その後もナイロンザイルの切断事故が続き、昭和29年から昭和55年の間に21名が命を落としています。登山者の間では、口コミで、8mmロープは危険で使えないというのが“常識”となり、穂高岳、谷川岳、剣岳といった岩場での登攀では9mmロープを2本使う「ダブルロープ」が一般的になっていきます。仮に1本が切れてももう1本で墜落を止められるようにするためです。
今やフリークライミングがブームですが、自然の岩場を登る場合は変わらずに注意が必要です。岩の鋭角はナイフのようになっていることもあり、擦れれば、今や一般的な直径11mmのロープであっても切れる可能性が十分あるでしょう。
平成元年、日本山岳会は篠田を名誉会員に推挙しました。石岡はその取り消しを訴えましたが、受け入れられませんでした。石岡は日本山岳会の東海支部の創設者ですが、篠田が名誉会員になったのを機に、日本山岳会を退いています。その後も、この「名誉会員問題」は石岡の遺族を中心に取り組まれていますが、どうなったでしょう。参考サイト:石岡繁雄の志を伝える会/「公益社団法人日本山岳会に対して、篠田軍治氏の名誉会員取消しを求める」 活動について→
裁判の結果がどうであれ、企業がどう言っても、学者がどう言っても、マスコミがどう伝えても、ましてや“ロボット芸能人”がどう言おうが、「真実」が他のところにあることがあることをこの「ナイロンザイル事件」が示唆しています。。
 |
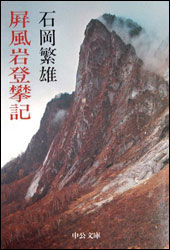 |
| 石岡繁雄、相田武男『氷壁・ナイロンザイル事件の真実 ~石岡繁雄が語る~』(あるむ)。「ナイロンザイル事件」の追究が、「PL(product liability)法」(「製造物責任法」)制定のきっかけとなる | 石岡繁雄『屏風岩登攀記 (中公文庫)』。「ナイロンザイル事件」を追求した石岡は、穂高の屏風岩を初登攀するなど登山家としても大きな実績を持つ |
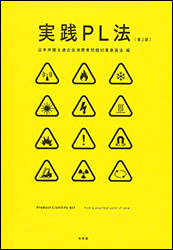 |
 |
| 『実践PL法(第2版)』(有斐閣)。編集:日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 | 安岡孝司『企業不正の研究 〜リスクマネジメントがなぜ機能しないのか?〜』(日経BP) |
■ 馬込文学マラソン:
・ 井上 靖の『氷壁』を読む→
■ 参考文献:
●『石岡繁雄が語る 氷壁・ナイロンザイル事件の真実』(石岡繁雄 相田武男 あるむ 平成21年発行)P.10-12、P.125、P.141-145、P.157-160、P.178-181、P.427-429 ●「ナイロンザイル事件(山岳講演会)」(尾上 昇)」(日本山岳会(JAC)岐阜支部→)
■ 謝辞:
●『石岡繁雄が語る 氷壁・ナイロンザイル事件の真実』の共著者の相田武男氏より、励ましのお言葉をいただき、ご教示もしていただきました。ありがとうございます。
※当ページの最終修正年月日
2025.4.29