| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和12年11月18日(1937年。
火野
汲取り業者の話です。主人公は人から「臭い」と差別されても、やんわりと笑いで返し、また、資金繰りに苦労しながらも、仕事に誇りをもって誠実に踏ん張っていました。しかし、しだいに、地域の政治勢力の対立に巻き込まれていきます。途中、救い主のような人も現れますが、結局はその人にもいいようにされ、読んでいて
糞尿は、どの人にも身近で切実なはずですが(一人平均して1年に2,500回ほどトイレに行き、人生の3年間はトイレにいる計算とか)、「わたしには関係ございません」という顔をされがち。トイレを「はばかり」といいますが、まさに
火野はこの小説で第6回芥川賞を受賞。火野は中国の
 |
芥川龍之介の『好色』も糞尿譚の傑作です。平安前期の
天下のプレイボーイもプライドずたずたで、でもさらに侍従への思いは高じるばかり。50通、60通と手紙を書き続けても返事が来ず悶死寸前となり、彼はある策略に出ます。侍従の“汚いもの”を見れば、100年の恋も冷めて、楽になれるだろうと・・・。 この話、芥川の純粋な創作だと思ったら、『今昔物語』(平安末期頃に成立)や『宇治拾遺物語』(鎌倉前期頃に成立)にほぼ同じ流れの話があるのですね。糞尿譚は昔から人気があったんですね。もっと前(奈良時代)の『古事記』『日本書紀』にも糞尿関係が出てきます。*
 |
 |
 |
レマルク |
当たり前の話ですが、戦争中も、人はウンコもすればオシッコもします。*
当地(東京都大田区)も激しく空襲されますが、そんなさ中も当地に留まった添田知道が、日記に次のように書いています。*
・・・庭の穴に、便所をくみ出して埋める。・・・(中略)・・・それを
戦争をリアルにイメージするには、こういった“臭い”も加味する必要があるでしょう。これだけ見ても、戦争なんてものはカッコいいもんじゃありません。*
戦場での用足しはどんなでしょう。レマルクのベストセラーの反戦小説『西部戦線異常なし』は当地(東京都大田区)に住まう秦 豊吉によって初めて和訳されますが、この作品にも、けっこう排泄の場面があります。*
・・・軍隊の共同便所へはいるのが実に恥かしかったものだ。扉というものはありゃしない。おまけに二十人ばかりが隣り合って汽車の中のように腰掛けるのである。もちろん一と目でずらりと見渡せる。……兵隊というものは、いつでも監視を受けていなければいけないものだ。・・・(中略)・・・こうして戦場へ出ていると、糞をすることなんぞも、まさに一つの快楽だ。・・・(中略)・・・とにかくそうして糞をするときが、実に本当の無念無想の時間だ。頭の上は青空である。遥か地平線には、黄色い
 |
大森貝塚の発見者・モースは、3度日本に来て長期滞在しています。彼は著書『日本の住まい』(Amazon→)で、西欧諸国に無理矢理開国させられ、そればかりかそれらの国から低く見られている日本に痛く同情、日本文化の優れている点を強調してくれました。糞尿処理にも触れ、糞尿を肥やしとして利用するそのリサイクルシステムを賞賛しています。*
一方、日本になかった婦人専用トイレの必要を説きました。東京大学で生物学を教えていたモースは「いずれは女性も入学するだろう」と婦人専用トイレを設置。*
今や、日本のトイレ文化は国際的に高く評価され、国連での「世界トイレの日」制定に貢献したシンガポールのジャック・シムは、「日本の最大の輸出資源はトイレ文化」とまで言い切りました。トイレの不十分さが伝染病やレイプの大きな原因になっているとのことです。*
 |
西岡秀雄 |
西岡秀雄は人文地理学を教える慶應大学の教授ですが、「トイレ博士」としても知られています。40年以上にわたり、世界80ヶ国から700点以上の「お尻を拭くもの」を収集、各種トイレットペーパーはもちろんのこと、トウモロコシの芯や小石まで収集されました。*のちに日本トイレ協会を設立、衛生的な便器の開発にも携わりました。*
西岡が当地の郷土博物館(東京都大田区南馬込五丁目11-13 Map→ Site→)の館長だった平成2年に企画展「トイレ考 〜厠からTOILETへ〜」、平成8年に企画展「考古学トイレ考」を開催、注目を集めました。トイレの遺構から、先史時代の人々の食生活、病気の種類、健康状態、生活環境までが推測できる、といった展示のなされました。*
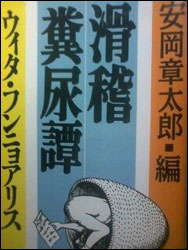 |
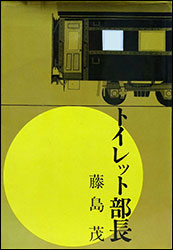 |
| 『滑稽糞尿譚 〜ウィタ・フンニョアリス〜 (文春文庫)』。糞尿にまつわる面白い話の数々。「追いかけるUNKO」(吉行淳之介)、「好色」(芥川龍之介)、「寝小便に泣く男」(安岡章太郎)、「おべんじょ」(田辺聖子)、「モースの便所」(畑 正憲)、「食事と排泄」(星新一)など | 藤島 茂『トイレット部長 』(文藝春秋新社)。国鉄の建築課長だった方のベストセラー。国鉄の4,500ものトイレの修繕維持をする仕事に燃える男はトイレの話しかせず、妻はうんざりするが・・・。昭和36年、池部 良が東宝に企画書を出して映画化。池部が男を演じる |
 |
 |
| ミダス・デッケルス『ウンコの博物学 〜糞尿から見る人類の文化と歴史〜』(作品社)。秘蔵図版(!?)を250点収載とのこと。翻訳:山本規雄 | 湯澤規子『ウンコはどこから来て、どこへ行くのか 〜人糞地理学ことはじめ〜 (ちくま新書)』 |
■ 馬込文学マラソン:
・間宮茂輔の『あらがね』を読む→
・芥川龍之介の『魔術』を読む→
・池部 良の『風が吹いたら』を読む→
■ 参考文献:
●『六頭目の馬 〜間宮茂輔の生涯〜』(間宮 武 武蔵野書房 平成6年発行)P.5-17 ●今昔物語集(現代語訳)/巻三十第一話 美女のウンコを食う話(芥川龍之介『好色』元話)(Site→)* ●『空襲下日記』(添田知道 刀水書房 昭和59年発行)P.6-10、P.33 ●『トレイは世界を救う(PHP新書)』(ジャック・シム 令和元年発行)口絵、P.83-84 ●「追悼「トイレ博士」西岡秀雄が「水に流せなかったもの」」※「週刊新潮」(平成23年8月25日号)掲載* ●「あふれる好奇心 最後まで(追悼抄 西岡秀雄さん)」※「読売新聞」(平成23年9月19日号)掲載* ●『トイレの考古学』(編集・発行:東京都大田区立郷土博物館 平成8年発行)ごあいさつ、P.6、P.12-13 ●『映画俳優 池部 良』(志村三代子、弓桁あや ワイズ出版 平成19年発行)P.360-361
■ 謝辞:
・東京都大森貝塚保存会のNY様より資料をいただきました。ありがとうございます。*
※当ページの最終修正年月日
2024.11.11