| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和21年5月24日(1946年。
未明、辻村もと子(40歳)が、郷里の北海道
いよいよという時、同郷の文学仲間の加藤愛夫(44歳)が、版元の白都書房の社長に頼んで、辻村の新作品集『風の街』を一冊だけ急いで製本、印税の小切手も切ってもらい、病床に届けています。辻村は本を手に取って開き、目をすり寄せたといいます。「よく出来たわ。ありがとう。ありがとう。加藤さんにお夕飯をさしあげて、お母さん」が辻村の最期の言葉となりました。本を置いた後、眠りに入り、次の朝、日が上る前に他界しました。
『風の街』には9つの短編が入っており、その一つ「月影」は、3年に一度は冷害があった北海道でもすくすく育つ米を作るべく品種改良に取り組む若い技師とその妻を描いたもの。昭和20年の芥川賞候補となりますが、戦況悪化のためこの年から芥川賞が中止になり、受賞にいたりませんでした。
『風の街』の中の「花咲く窓」は、戦場に行った夫の帰りを待つ女性産科医を描いたもの。大映で映画にもなっています(映画のタイトルは「別れも愉し」)。敗戦前にクランクインして、敗戦後に公開された珍しい映画で、映画の中で、2年ぶりに帰ってくる夫が最初は原作通り軍人でしたが、敗戦後、それではまずいと遠洋漁業の船員に変更されたようです。監督は松竹蒲田撮影所にも関わりがあった田中重雄。出演は村田知英子、若原雅夫、月丘夢路ほか。フィルムが残っているようです。
芥川賞にノミネートといい、作品の映画化といい、辻村の死は、これからメジャーになろうという矢先でした。
作家の最初の作品と同様、最後の作品も興味深いです。
それなりに長寿の作家であれば、老いを見つめ、病いを見つめ、死を見つめ、人生の壁を見つめ、今までの人生を振り返り、作家の到達点を示している場合も少なくないかもしれません(気力が残っていればの話ですが)。
 |
室生犀星(72歳)の最後の一編は、「老いたるえびのうた」 。
「老いたるえびのうた」
けふはえびのやうに悲しい
角やらひげやら
とげやら一杯生やしてゐるが
どれが悲しがつてゐるのか判らない。
ひげにたずねて見れば
おれではないといふ。
尖つたとげに聞いて見たら
わしでもないといふ。
それでは一体誰が悲しがつてゐるのか
誰に聞いてみても
さつぱり判らない。
生きてたたみを
からだぢゆうが悲しいのだ。
有名になって丸くなってしまう作家も多い中、犀星は、最晩年まで前衛を貫きました。最終連の「えせえび」(似非エビ。偽物のエビ)は「伊勢海老」に掛けているのでしょう。「伊勢海老」の立派さと「似非エビ」の惨めさ。ギリギリの苦痛の中で発せられたユーモアが心を打ってきます。
ケストナーの『飛ぶ教室』(Amazon→)に「子どもの涙は、大人の涙より小さいわけではない」という一節がありますが、老人の涙も決して萎びてもいないし小さくもないようです。
原稿の締め切りに遅れることがなかった犀星ですが、この一編に限っては編集者が原稿を取りにきた時まだでき上がっておらず、 初めて編集者を待せたとのこと。肺癌が進んで悪性の細胞が脳にまで達し、ペンを持つことも厳しくなっていました。犀星はこの詩を書いた1ヶ月後、帰らぬ人となります。
病や事故は人の事情などお構いなしですから、執筆や制作に取り掛かっても、未完に終わる場合も多いです。
 |
山本有三の最後の作品は、近衛文麿について書いた『濁流』です。近衛が日中戦争や日米交渉とどう関わったかを知っているのは自分しかいないという自負が山本にはありました。一人の心優しい男が時代の“濁流”に飲み込まれていく様を描こうとしたようですが、昭和48年4月(山本85歳)より「毎日新聞」に連載されたものの、体調不良のため41回で中断、未完に終わります(翌年1月死去)。
自分にしかできない仕事を最後に手がけたといえば、ミレーもそうでした。
 |
ミレー |
今でこそ、「ミレーの「落ち穂拾い」(Photo→)、キャー」「ミレーの「晩鐘」(Photo→)、キャー」という感じですが、ミレーが農民の姿を描き始めた頃は、世から散々叩かれました。搾取する側からは批判と受け取られ、アカデミズムに地位を得ている画家や彼らの絵こそが素晴らしいと思い込んでいる鑑賞者からも攻撃を受けました。ミレーの代表作「落ち穂拾い」(貧しい者は人の農地から落ち穂を拾っても咎められなかった。その姿を題材にした)は、「貧困の三女神」とからかわれました。今でも「ビンボーくせー」とか口走る人がいますが、ま、そんな感じのことを言われたわけです。
それでも、世の中に、少しずつ、人権とか、民主主義とかいう考えが広まっていき、ミレーの絵画も認められていきました。
これだけでも立派な人生ですが、ミレーの最後の作品がまた突き抜けています。
 |
ミレーの最後の作品「鳥の巣狩り」。明治7年。フィラデルフィア美術館 ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:MUSEY/「鳥の巣狩り」(ミレー)→ |
後年、家庭的にも恵まれ、画家としても高く評価されたミレーですが、彼の最後の作品は異様な印象さえ与えるものです。「落ち穂拾い」「晩鐘」に見られるような
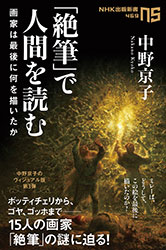 |
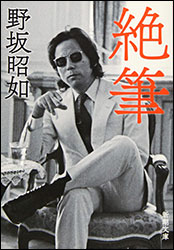 |
| 中野京子『「絶筆」で人間を読む 〜画家は最後に何を描いたか〜 (NHK出版新書)』 | 野坂昭如『絶筆 (新潮文庫) 』。急逝する数時間前まで綴られた日記と、最晩年の渾身のエッセイ |
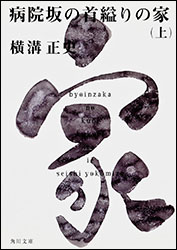 |
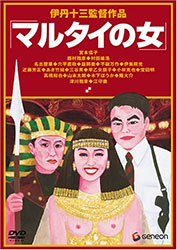 |
| 横溝正史『病院坂の首縊りの家(角川文庫)』。名探偵・金田一耕助が手がけた最後の事件。齢60歳。事件解決後、金田一は、世話になった人たちに巨額の寄付をし、米国に姿を消す・・・ | 「マルタイの女」。伊丹十三監督の遺作。「マルタイ」とは「護衛の対象者」を表す警察用語。殺人を目撃してしまった女優は、「真理の羊」の信者から命を狙われ、マルタイとなる・・・ |
■ 馬込文学マラソン:
・ 辻村もと子の『馬追原野』を読む→
・ 室生犀星の『黒髪の書』を読む→
■ 参考文献:
●『辻村もと子 人と文学』(加藤愛夫 いわみざわ文学叢書刊行会 昭和54年発行)P.196-199、P.202-203、P.321-323、P.367-368 ●「田中重雄「別れも愉し」」(昔の映画)(昔の映画を見ています→) ●『評伝 室生犀星』(舟登芳雄 三弥井書店 平成9年発行)P.273-278 ●『大森 犀星 昭和』(室生朝子 リブロポート 昭和63年発行)P.257-260 ●『山本有三(新潮日本文学アルバム)』(昭和61年発行)P.65-70、P.86-87 ●『濁流 ~雑談=近衛文麿』(山本有三 毎日新聞社 昭和49年発行)P.22-50、P.138-146 ●『「絶筆」で人間を読む 〜画家は最後に何を描いたか〜(NHK出版新書)』(中野京子 平成27年初版発行 平成30年発行4刷)P.240-253
※当ページの最終修正年月日
2025.5.24