| {column0} |

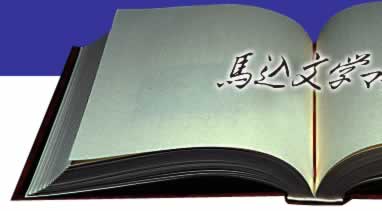







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
山本有三と近衛文麿。軽井沢の近衛邸で(昭和18年8月) ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典: 『山本有三(新潮日本文学アルバム)』
 |
昭和19年1月8日(1944年。 山本有三(56歳)が近衛文麿(52歳)の伝記の執筆を引き受けています。
近衛と山本は第一高等学校時代からの顔見知りで、山本が近衛の代筆をするようになってからは、腹をわって話す間柄になりました(山本は近衛から東条英機の暗殺計画も打ち明けられている)。近衛から書き手の紹介を頼まれますが、近衛を直接知っていて、なおかつ、日中戦争(両国とも宣戦布告をしなかったため太平洋戦争が始まるまで支那事変または日支事変と呼ばれた)や太平洋戦争開戦直前の日米交渉の経緯などを知っているのは自分しかいないとの自負があり、山本は自ら買って出ています。
山本は執筆準備を始めますが、そうこうするうちに日本は敗戦、近衛はA級戦犯に指定され、自死してしまいます。友人として近衛のポジティブな面を書きたくても、この時期に(特に昭和26年まではGHQの占領下)書けば、A級戦犯容疑者の肩をもつようで憚られたでしょう。また、山本は戦後の国語改革の中心になって多忙な日々を送ることになり、なんやかやで近衛伝は頓挫してしまいます。
山本が再び近衛伝の筆をとるのは、引き受けてから29年たった昭和48年。86歳になっていました。「毎日新聞」に『濁流 ~雑談=近衛文麿~』というタイトルで連載し始めます。
近衛は、戦前3度も内閣総理大臣を務め(日中戦争開戦1ヶ月ほど前の昭和12年6月4日より務め、断続的に太平洋戦争開戦2ヶ月ほど前の昭和16年10月18日まで)、戦中は和平交渉に心を砕いたにもかかわらず、近衛の評価は極めて低いといっていいでしょう。盧溝橋事件に始まる日中戦争では不拡大と言いつつ拡大させてしまい(在中国のドイツ大使・トラウトマンの和平工作も突っぱねた)、マスコミを操作して翼賛体勢を作り、日独伊三国同盟(米英を敵に回すこととなった)、大東亜共栄圏を推進して日本を戦争の泥沼にひきづり込みました。近衛を評して杉山元帥は「会して議せず、議して決せず」と言い、戦中、近衛に日独伊三国同盟の必要性を説いた徳富蘇峰も同盟に踏み切りながらも近衛が「やがてはまた盛んに色眼を英米に遣かうようになった」とし、「難局に遭えば、いつも逃げ出す」と厳しく批判、近年でも半藤一利さんが近衛のことを「お坊ちゃん総理」「まことに始末におえない首相」「他人の意見を聞く振りをしながら自分の意見を頑固に押し通し、まずくなるとすぐ逃げ出すという、まことに頼りない人」と書いています。周りの気を損ねたくないので重要事もなあなあにし、結局は声の大きな者に流され、政治家としてはダメでした。敗戦後の自死も同情されるよりは、責任放棄と見なされることが多いかもしれません。
そんな近衛でしたが、山本は鎮魂するかのように筆を運びました。ダメなところはダメとしつつも、山本だけが知っている近衛の人間的な面を書いていきます。
・・・この別荘のなかには、門の横に、加藤という護衛巡査の家があって、そこには、雪枝という、三つか、四つになる女の子がいました。同じ邸内に住んでいることですから、その子は、よく、おも屋のほうに遊びにきました。・・・(中略)・・・近衛も、にこにこしながら、見ていましたが、そういった、はしゃいだ気分に誘われたものか、
「雪ちゃん、お馬になってあげようか。」
「雪ちゃん、お馬、大ちゅき。」
子どもの喜ぶ声を聞くと、近衛は、ほんとうに、ジュウタンの上に、四つんばいになったっていうんですね。これにはふたりとも、あっけにとられたそうです。そして、その子を背中に乗せて、──いいえ、うそじゃありません。その通りにやったんです。
それから、近衛が四つばいのまま、応接室を歩き出したら、妹の温子が、お馬のおしりを、たたくまねをしながら、
「ハイ、ドウ。ハイ、ドウ。」
って、はやし立てたんで、
背中の雪ちゃんも、うれしそうに、
「ハイ、ドウ。ハイ、ドウ。」
と、口まねをしました。
近衛は、その声に合せるかのように、ある時は、早く、ある時は、ゆっくり、ジュウタンの上を、はい回ったっていうんです。なんとも愉快な話で、近衛にも、こういった一面があったんですね。そこには、もう、公爵もなければ、貴族院議長もない。人間近衛だけが、ほのぼのと、浮かんでくるじゃありませんか。・・・(山本有三『濁流』より)
近衛が乗っている車が道行くおばあさんと子どもに泥水を跳ね上げたと知るや車を止めさせ、泥で車内が汚れることもかまわずに2人を車に乗せて送っていったというエピソードも山本は紹介しています。きな臭い時代でなければ(自ら招いた面もありますが)、また不適正な政治家などにならなければ、“いい人”として人生を全うできたかもしれません。
山本は、近衛との約束を果たそうとしたというのもあるでしょうが、それよりもこの「人間近衛」を何が何でも書きたかったのだと思います。悪かったのは近衛など当時の指導者たちで、自分たちは騙されていただけといった多くの国民に、今や声を発することのない近衛になり代わって(近衛が上のようなことを自慢するとも思えませんが)声を張り上げたのです。山本は『濁流』の連載第41回目を書いた後体調を崩し、帰らぬ人となります。よって『濁流』は未完。でも「人間近衛」の一端は我々に届きましたし、山本の鎮魂の思いも伝ってきます。
 |
柳 美里 |
明治11年8月23日、皇居の竹橋附近で駐屯中の陸軍近衛兵259名が、徴兵制や待遇の改善をもとめ、明治天皇に直訴すべく決起した「竹橋事件」が起きました。2時間ほどで鎮圧されたこの事件で(政府側に4名の死者が出る)、参加した55名はまともな裁判を経ないで処刑されています。決起当日に決起を知って付いていった者まで処刑されています。事件からちょうど100年たった昭和53年(1978年)、澤地久枝さんが、墓すら打ち捨てられていた彼ら56名(自死者1名を含む)の「声」を著書『火はわが胸中にあり』で蘇らせました。
マスコミ・メディアの狂奔に晒され(権力の意思も働いたか)、また、人々の好奇の目やら、嫉妬心やら、マウンティング・マインドやら、「他人の不幸は蜜の味」やら、無関心やら、見て見ぬ振りなどによって「声」を奪われた植草一秀さんや小保方晴子さんのような方の「声」にも、また、冤罪者の「声」などにも耳を傾けたいもの。“悪”に加担しないためにも。
 |
 |
| 山本有三『濁流 〜雑談=近衛文麿〜』(毎日新聞社) | 柳 美里『JR上野駅公園口 (河出文庫)』 |
 |
 |
| 『小保方晴子 日記』(中央公論新社)。瀬戸内寂聴さんとの対談も収録。平成30年発行 | 清水 潔『殺人犯はそこにいる〜隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件〜(新潮文庫)』 |
■ 参考文献:
●『山本有三(新潮日本文学アルバム)』(昭和61年発行)P.65-70、P.86-87 ●『濁流 ~雑談=近衛文麿〜』(山本有三 毎日新聞社 昭和49年発行)P.7、P.18-50、P.138-146 ●『徳富蘇峰 終戦後日記 〜頑蘇夢日記〜』(講談社 平成18年発行)P.394-397 ●『昭和史(1926-1945)』(半藤一利 平凡社)P.195-196、275-280、342-344、P.365 ●「他者の声聞き消えた 自分という囲い 〜全米図書賞受賞の柳 美里さん〜」(「朝日新聞(朝刊)」(令和2年12月13日掲載))
※当ページの最終修正年月日
2025.1.8