| {column0} |

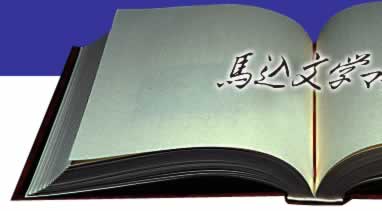







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
明治39年12月19日(1906年。 )、室生犀星(17歳)の短歌が2首が、「二葉会」という短歌の会が出す印刷物に掲載されます。犀星の短歌が活字になるのは初めてでした。
あけ雲に
湖水に白き蓮ひらく時
影を
両首とも慕わしいもの(「白き蓮」「影」)への憧れを詠ったものでしょう。
犀星は4年前(明治35年12歳)高等小学校を退学して、義兄が勤務する金沢地方裁判所に給仕として就職しました。当時の自分を犀星は「豚のやうにやくざな少年」と表現しています。そんな少年に俳句の手ほどきをしてくれたのが、上司(監督書記)の川越一弥という人物です。犀星は夢中になって句作に励み、2年後には年少俳人として知られるようになっていました。俳句と詩はすでに活字になっていました。
「医峰」(金城文誘会という文学サークルの機関誌。医峰とは石川県と富山県の境にある
後に(大正8年)犀星(30歳)は『性に眼覚める頃』という小説を書きますが、この棹影は実名で出てきます。棹影が実名で登場するということは、その他の部分もだいたいは実際に則して書かれていると考えていいかもしれません。棹影の文学的な才能に驚いた犀星ですが、犀星をさらに驚かせたのは棹影の女友達を作る能力でした。 彼は雑踏で見つけた気に入った娘に手紙を渡しその返事をもらうことがなんでもなくできるのでした。今でいえば「ヘイ、彼女!」(ちょっと古いか)と気軽に話しかけ、しかも親しくなってしまうといった感じでしょうか。棹影は「
犀星はというと、幼時から寺に住んでおり(犀星は、父・小畠吉種に仕えていた女性が産んだ子で、生まれてすぐ、雨宝院(石川県金沢市千日町1-3 Map→)住職・室生真乗の内妻・赤井ハツに託された)、やはり「性に目覚め」ており、
・・・彼女の手がその膝がしらと畳との二三寸の宙を
私はそれを見てゐて息が
彼女の行動はエスカレートしていき、賽銭箱の鍵を開けて中の賽銭まで盗むようになります。寺も異変に気づきますが、「私」は「あんな女のひとが盗みをするなんてことはありません」と彼女をかばい、彼女が毎日のように悪さをするようになると、「私」が賽銭箱に自分の金を補充するようになります。自分の金がなくなると、「私」は父親の貯金をくすねて賽銭箱に補充するというところまでいってしまいます。
犀星はこのように「性の目覚め」を赤裸々に書きました。
ちなみに元の題は『発生』。「中央公論」の編集主幹・滝田樗陰が『性に眼覚める頃』と改題したそうです。さすがです。
「性の目覚め」を「いつ・どのようなもの」とするかは、人によっていろいろでしょう。フロイトによればそれこそ生まれ落ちたときから“性欲”があるようなので、マイルドな形での目覚めならば記憶が残っている限り遡れるかもしれません。
個人差は当然あるのでしょうが、小学校の高学年頃から、憧れの対象で頭が満たされ、それこそ犀星の文章にもあるように「樹木にでも
 |
山本周五郎の『樅ノ木は残った』は、伊達騒動(寛文事件)の渦中、伊達藩(仙台藩)を救うために、寝返った風に見せて首謀者の懐に入り、裏切り者として死んでいく伊達藩重臣の原田甲斐の物語ですが(事実とは異なる)、この小説にはもう一つ
騒動の最中、父母を失った宇乃(13歳)と弟の虎之助(6歳)は、甲斐に保護され近くに住むようになります。甲斐は裏切り者を演じなければならなかったので、近しい者が一人また一人と甲斐の元を去っていきました。しかし、宇乃だけは、甲斐の静かで誠実で優しい言葉から、甲斐が胸中に秘めている苦悩を直覚(甲斐はいつも穏やかに笑顔をたたえていたが)。これは、人に対する理解であり、共感であり、あるいは愛とづけてもいいものだったかもしれません。
物語は、最終部に向けてますます緊迫していきます。そして、甲斐は裏切り者として一人死んでゆく。小説は、宇乃と甲斐の“再会”の場面で終わります。思春期の「性の目覚め」をこれほどまでに劇的にかつ清潔に描いた文学がほかにあるでしょうか? しかも、極めて官能的であるところも周五郎です。
宇乃と虎之助は最初、塩沢母子のところに預けられますが、しばらくして良源院(現在の「港区役所」(東京都港区芝公園一丁目5-25 Map→)の敷地にあった)というお寺に移ることとなります。その時塩沢の母が、宇乃にそっと小さな包みを渡します。「もうまもなく、あなたのお
 |
三島由紀夫の「性の目覚め」は異性にたいするものではありませんでした。
 |
 |
| 室生犀星『性に眼覚める頃』(新潮社 大正9年発行)。「日本近代文学館」による復刻 | 有島武郎『一房の葡萄 〜他四篇〜 (岩波文庫)』。先生は叱る代わりに一房の葡萄を少年に渡す |
 |
 |
| アクロストン『思春期の性と恋愛 〜子どもたちの頭の中がこんなことになってるなんて!〜』(主婦の友社) | 「小さな恋のメロディ」。子どもの恋だって切実。徹底的に子ども側に立つ。ビー・ジーズの歌が全編を流れる |
■ 馬込文学マラソン:
・室生犀星の『黒髪の書』を読む→
・山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→
・三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
■ 参考文献:
●『評伝 室生犀星』(船登芳雄 三弥井書店 平成9年発行)P.81、P.85-86、P.202-206、P.279、P.281 ●『性に眼覚める頃』(室生犀星 大正9年発行 新潮社)P.118-138 ●「「浅岡飯炊きの井」─良源院」(夢見る獏)(気ままに江戸♪→)
※当ページの最終修正年月日
2024.12.17