| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
昭和7年7月8日(1932年。 草野心平(29歳)の手紙が宮沢賢治(35歳)に届きました。11日前(6月27日)の石川善助(31歳)の当地(東京都大田区大森駅近く)での死を伝えるものです。
 |
3ヶ月後(昭和7年10月)、賢治から草野にあてて書かれた手紙が興味深いです。東京での善助関係での骨折り(生前、善助は草野の家に居候しており、善助の通夜も草野の家で行われた)を
・・・あなたへも数回手紙を書きかけましたが、主義のちがひですか、何を書いても結局
「雨ニモマケズ」(青空文庫→)などから受ける印象とは異なる賢治の闘争的な一面が伺えます。「主義のちがひ(違い)」は宗教的または政治的なものでしょうか、それとも、詩に対する考えの違いでしょうか。
草野は大正10年(18歳)に中国に渡り「
賢治からすぐ返事が来て、同人になることを承諾、同人費の1円の小為替と心象スケッチ「負景」〔「ふけい」と読むのでしょうか〕二篇が同封されていたとのこと。
同封されていた手紙は失われましたが、草野はその一節を覚えており、40数年後に『私の中の流星群』という本で紹介しています。
・・・わたくしは詩人としては自信がありませんが、一個のサイエンティストとしては認めていただきたいと思います・・・(草野が回想した賢治からの手紙の一節)
賢治は自分を
『春と修羅』の冒頭で「心象スケッチ」を次のように定義しています。
わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしよに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち その電燈は失はれ)
これらは二十二箇月の
過去とかんずる方角から
紙と鉱質インクをつらね
(すべてわたくしと明滅し みんなが同時に感ずるもの)
ここまでたもちつゞけられた
かげとひかりのひとくさりづつ
そのとほりの心象スケツチです・・・(『春と修羅』の「序」より)
 |
かたや草野は、昭和3年(草野25歳)、初の詩集『第百階級』を出しますが、そこには、
みみずのやうに食はれおるわ
つめたくぬるぬるしておいしいわ
わひ わひ わひ
らりらら らりらら
踊れるわ 踊れるわ
脚が生えおるわ
五本 六本 十本 十本
わひ わひ わひ
らりらら らりらら・・・(『第百階級』の「亡霊」より)
といった詩が並び、これは賢治のように「わたくしといふ現象」を凝視するというより、むしろ自身からは
 |
 |
| 賢治の『春と修羅』(復刻版)。目の粗い布に描かれたタンポポが印象的。辻 潤が見出して熱狂し、草野も高村光太郎も夢中になった一冊 | 草野の『第百階級』(復刻本)の「冬眠」。「●」は案外大きく、次の季節に向け、何かを蓄えているかのよう。中央寄りにポツンとある |
国語辞典で「詩」と引くと、
①文芸の一つの形態。人間生活・自然観照から得た感動を、一種のリズムをもつ言語形式で表したもの。(「岩波 国語辞典(第三版)」より)
つづめて言えば、「感動」を「リズム」良く表現したもの。「観照」とは、
①対象の本質を客観的に冷静にみつめること。②美を直接的に認識すること(「岩波 国語辞典(第三版)」より)
とあり、「対象の本質」を、「客観的」に(単なる感想に堕することなく)見つめ、誰かの受け売りではなく「直接的に認識」する。そういった認識によって動いた心(感動の実態)を言葉に表現したものが「詩」といえるでしょうか。「より物事の本質」に迫る、「より他の受け売りでない=新しい」ものに、「詩としての価値」があるといえるでしょうか。
文学が未発達の時代、言葉が代々受け継がれていくには、「リズム」(「韻文」)が必要だったと折口信夫が考察しています。「万葉集」に見られるような「詩」が先にあり、「散文」は平安時代ぐらいからのようです。
「詩」といっても多種多様です。北園克衛のように純粋に造形的な面白さを狙ったと思しきものもあれば、 象徴派的傾向、高踏派的傾向、民衆詩派的傾向もあります。
桑原武夫の「(俳句)第二芸術論」(俳句は他の文芸より劣る)というのがありましたが、俳句にも「詩」たり得ているものがたくさんあります。
柿へえば鐘が鳴るなり法隆寺(正岡子規)
何が面白いのだろうと思っていましたが、これって、柿を食っているとき法隆寺の鐘が鳴ったのではなく、柿を食った
以下は、友川かずきさんの言葉。
・・・あのー、その時、それ、私もふっと、時々ね、ふだんは言葉が好きじゃないけど、時々詩人になりたい時があるんだな、詩書けば誰でも詩人になれるからね、詩人になろうと思って詩を書いたの・・・(友川かずき「Live-MANDA-LA」Special」より)
 |
 |
| 嶋岡 |
渡邊 |
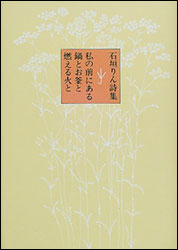 |
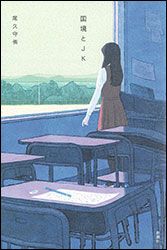 |
| 『私の前にある鍋とお釜と燃える火と(石垣りん詩集)』(童話屋)。石垣りんの第1詩集の再刊。この今の生活実感から |
■ 馬込文学マラソン:
・ 石川善助の『亜寒帯』を読む→
■ 参考文献:
●『詩人 石川善助 そのロマンの系譜』(藤 一也 萬葉堂出版 昭和56年発行)P.387-413、P.456-457 ●『宮沢賢治(新潮日本文学アルバム)』(昭和61年発行)P.46-47、P.70 ●『私の中の流星群』(草野心平 新潮社 昭和50年発行)P.21-27 ●「万葉集の解題」(折口信夫)(青空文庫→) ●「『春と修羅』第二集『命令』とその背景」(木村東吉)(広島大学 学術情報リポジトリ→)
※当ページの最終修正年月日
2023.7.8