| {column0} |

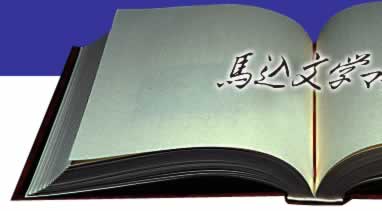







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
昭和13年6月26日(1938年。
「不敗の名人」と謳われた第21世
挑戦者は、
秀哉が「不敗の名人」たり得たのは、当時「名人」と呼ばれるようになると、その名に傷がつかないよう「勝負碁」が避けられたからのようです。秀哉がこの10年で打った碁は2局しかなく、その2局とも途中で秀哉が病に倒れるといったアクシデントがあり、結果としては秀哉が勝ちましたが、病に伏している最中、他の棋士からの入れ知恵があったのではとの噂もありました。そんなこともあったので、秀哉はこの引退碁で、“実力者”と正々堂々と戦い、自身の実力を見せようとしたのでしょう。
 |
秀哉の引退碁を報じる新聞記事。写真は左が秀哉、右上が木谷七段、右下が解説の |
持ち時間はそれぞれが40時間という前例のない長さでした(普通は大きな対局でも2日で打ち切り、一日8時間で計16時間がそれぞれの持ち時間。8時間労働の考え方に基づく)。かつては棋士が思うがままに時間を費やして次の一手を考えていましたが、大正時代末頃から持ち時間制が導入されます。時間の制約の中で戦ってこなかった秀哉に配慮して40時間という長時間が設定されましたが、心臓に持病があった秀哉には、この長時間の持ち時間が文字通り“命取り”となります(対局後1年ほどした昭和15年1月18日死去)。
また、公平性を考え、この対局で初めて「封じ手」が行われました。これまでは
1日目は、昭和13年6月26日芝「紅葉館」で黒一から白二(封じ手)までの2手で形だけのもの(棋譜→)。次の日(6月27日)も「紅葉館」で黒三から黒十一(封じ手)まで打たれました(棋譜→)。
3日目は14日後(7月11日)に箱根の奈良屋旅館で打たれました。以後、秀哉が持病の心臓病悪化のため聖路加病院に入院するまでここで打たれます。6日目(箱根での4日目。7月26日)に木谷七段からの痛烈な一手(黒六十九)があってから秀哉も長考するようになりました。
秀哉の3ヶ月の入院のあと、場所を伊豆の「
 |
 |
この歴史的対局の観戦記を担当したのが川端康成(39歳)です。 「東京日日新聞」に64回に渡って観戦記を連載し、人気を博しました。秀哉の没後2年ほどたった昭和17年には、この対局を題材にした小説『名人』を書き始めます。川端には珍しくかなり忠実な記録小説です。勝敗でいえば秀哉の負けでしたが、去りゆく時代の人の気高さと哀しみと静けさに深く共感して書かれています。公平とか、勝ち負けとかにこだわることで失われるものにも触れられていました。
川端文学の特徴の一つですが、『名人』も複数の雑誌に12年にも渡って分載されました。初めから終わりまで読み通すことにこだわらず、部分部分を味わへばいいんだと思います。次のようば表現に出会うことができます。
・・・床の生花の枝がかすかに揺れるほどの微風はあった。庭の滝と早川の瀬音のほかは、遠くから石工ののみの音が聞えるばかりだ。庭の鬼百合の匂いがはいって来る。なにかしらの鳥が、対局室の余りの静かさに、軒端を大きく飛んだ。・・・(川端康成『名人』より)
碁の観戦記を書くくらいですから、川端も相当打てたのでしょうが、文壇でともかく碁が強かったのが榊山 潤。18年間(昭和28~45年)文壇本因坊の座にあったそうです。榊山はなんせ実家が囲碁将棋クラブを経営していて、幼い頃からクラブを仕切っていた老人より手ほどきを受け、 7~8歳頃には三段の人に三目置かせて(三目の有利を与えて)勝つほどだったとか。昭和36年(60歳)には五段を取得しています。
 |
 |
| 川端康成(左)と村松梢風(右)の対局。観戦するは榊山 潤。昭和10年代後半に撮られた写真。川端が『名人』を書きつないだ頃だろう ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『馬込文士村ガイドブック(改訂版)』(東京都大田区立郷土博物館) | このような二人(川端(左)と村松(右))の写真も。村松邸での写真とのことだが、おそらくは鎌倉。川端も鎌倉に住んでいた。村松も秀哉の引退碁を観戦しており、川端の『名人』にも出てくる ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『川端康成(新潮日本文学アルバム)』 |
囲碁は、巷の電子ゲームなどとは違って一度道具を用意すればお金をかけずに一生楽しめるし、抽象性と奥深さがあって、国籍、言語、男女、老若も問わないのもいいですね(映画「ビューティフル・マインド」に、米国のプリンストン大学院のキャンパスで主人公が学友と囲碁に興じる場面がありました)。対戦相手がいるので、コミュニケーションツールともなります(一通り打てるようになったら、まずは親戚や近所で打てる人に挑んでみては?)。
ほぼ100%実力の世界なので、碁歴何十年という壮年の差し手でも、十歳にも満たない少年少女に負ければ、頭を垂れるしかありません。おべんちゃらやカッコつけなど一切通用しません。電子ゲームばかりしていると終いには親の目がきっと三角でしょうが、囲碁なら大目に見てくれるでしょうか?
やる気にさえなれば、漫画でも学べるし(「ヒカルの碁」 Amazon→)、分かりやすい入門書も多数出てますし(『石倉 昇の囲碁入門 〜囲碁の世界へようこそ〜』Amazon→)、気軽に学べるサイトもあります(「やさしい囲碁入門講座」→)。あと、新聞小説同様お忘れの方が多いと思いますが、多くの新聞が毎日囲碁将棋の連載をしています。部屋の隅に碁盤を置いて、毎日届けられる最新棋譜を並べていって日々研究するのも楽しそう。
 |
 |
| 川端康成『名人(新潮文庫)』。題材になった引退碁の棋譜もあり | 内藤由起子『それも一局 〜弟子たちが語る「木谷道場」のおしえ〜』(水曜社) |
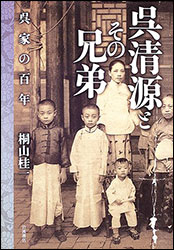 |
 |
| 桐山桂一『呉 清源とその兄弟 〜呉家の百年〜』(岩波書店) | 『 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 川端康成の『雪国』を読む→
・ 榊山 潤の『馬込文士村』を読む→
■ 参考文献:
●『名人(新潮文庫)』(川端康成 昭和37年初版発行 平成24年発行42刷参照)P.34、P.44-45、P.48-49、P.53、P.78-80、P.93-94、P.164-167 ●『川端康成(新潮日本文学アルバム)』(昭和59年発行)P.42-45 ●『馬込文士村 〜あの頃、馬込は笑いに充ちていた〜(特別展カタログ)』(制作・発行:東京都大田区立郷土博物館 平成26年発行)P.47
※当ページの最終修正年月日
2024.6.26